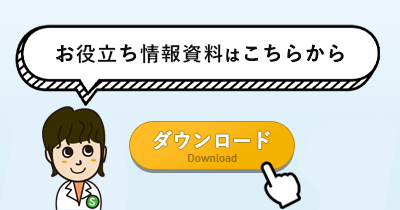2025年社会保険料が値上げされる理由は?予想される影響や値上げ対策を解説

こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。
2025年、年金制度改革によって社会保険料の値上げが行われました。社会保険料の負担は企業や個人で決められるものではないため、必然的に費用負担が発生し、さまざまな方面への影響が予想されます。社会保険料の値上げによって、具体的にどのような影響が予想されるのでしょうか。
本記事では、2025年度の社会保険料の値上げについての詳細や影響、値上げ対策について解説します。
福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉
目次
2025年に社会保険料が値上げに

社会保険とは、企業で働く正社員、または条件を満たすパートやアルバイトが加入する保険です。
一般的に、社会保険とは以下の5種類を指します。
・健康保険
・介護保険
・厚生年金
・雇用保険
・労災保険
健康保険に関しては、年金受給者や自営業者など社会保険に加入できない人が加入しているのが、国民健康保険です。日本は国民皆保険制度を取っており、すべての人が社会保険または国民健康保険いずれかの公的医療保険に加入して医療費を負担することで負担を支え合い、いつでも誰でも医療サービスを受けられる仕組みとなっています。
企業勤めの人が加入する社会保険は、雇用保険と労災保険を除いて勤務先企業と加入者がそれぞれ保険料を半額負担しますが、2025年の年金制度改革では上記5種類の社会保険のうち、健康保険料の値上げが行われます。

2025年からの主な値上げ内容

2025年から値上げされるのは、下記で詳しく述べる主に健康保険料の値上げです。加えて、厚生年金保険料も数年以内に引き上げが検討されています。
健康保険料の値上げ
主に中小企業の従業とその家族が加入する、日本最大規模の健康保険事業者「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の健康保険料は、都道府県ごとの医療水準に基づいて毎年決定されているため、居住地域によって異なる保険料率となっています。値上げ率も地域によって異なり、他地域が健康保険料の値上げが行われていても、引き下げが行われる地域も存在します。
2025年度はすべての都道府県で健康保険料の値上げが行われるわけではありませんが、半数以上の自治体で値上げとなっています。
なお、国民健康保険に関しても、これまでの年間保険料上限の89万円が2025年度より上限が3万円引き上げとなり、年間の保険料が92万円に変更となります。
厚生年金保険料の上限引き上げ検討
厚生年金は、70歳未満の会社員または公務員が加入する公的年金です。全額自己負担となる国民年金に対し、厚生年金は勤務先企業と被保険者が半額ずつ保険料を負担します。国民年金に上乗せして給付されることから、厚生年金の方が将来的に受け取れる年金額が多くなります。
厚生年金保険料は上限が引き上げとなりますが、これは標準報酬月額が引き上げられることによって行われます。標準報酬月額とは社会保険料算出の基本となる金額です。厚生年金では、毎年4~6月の給与を元に算出した標準報酬月額を一定の範囲内で8万8000円~65万円までの間で1~32等級に分けています。
そして保険料は、標準報酬月額にそれぞれの等級に応じて社会保険ごとに設定された保険料率を掛けて計算されています。つまり、標準報酬月額の等級の変更や標準報酬月額の上限が引き上げになると、厚生年金保険の料率も引き上がります。
厚生年金の標準報酬月額の上限引き上げは2025年から予定されていましたが、2027年9月より従来の65万円から75万円に引き上げが検討されています。2025年度からの値上げにはつながらないものの、近い将来上限が引き上げられることにより、年収798万円以上の高所得者の厚生年金保険料増加が見込まれます。
国民年金については、2025年度から月額1万7510円となり、前年比530円引き上げられています。

社会保険料が値上げされる理由

国民年金・国民健康保険を含めて、社会保険料は、なぜこのタイミングで値上げされるのでしょうか。その理由として挙げられるのが、以下の4点です。
少子高齢化
言うまでもなく、日本は急速に少子高齢化が進行している国です。日本の65歳以上の人口が総人口に占める割合を示す高齢化率は、2024年時点で過去最高の29.3%を記録しています。さらに、2025年は団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる「2025年問題」により、高齢化率の上昇とともに医療負担増も予想されています。
その一方で、15~49歳の女性の年齢別出生率を合計した合計特殊出生率は過去最低の1.15でした。この数値からも少子高齢化が進んでいることは明らかで、今後もこの状況が進むことが見込まれます。
高齢化が進むと、社会保険を利用する受給者が増え、医療費や介護費が増大します。保険料を負担するのは現役世代です。つまり、少子高齢化で保険制度を利用する高齢者が増加し、保険料を負担する働く世代が減っていることから、保険制度を維持するために社会保険料の値上げが実施されるというわけです。
参考/総務省「統計からみた我が国の高齢者」
厚生労働省「人口動態統計月報年計(概数)の概況)」
社会保険制度の維持
上記の少子高齢化とつながる理由ですが、今後も少子高齢化が進むと保険料を負担する世代が減る一方にもかかわらず、保険制度を必要とする高齢者が増加することが見込まれます。
このような状況が続くと、当然ながら社会保険制度の水準が下がるばかりか、制度そのものの維持が困難となるでしょう。社会保険を維持するには、保険料を安定的に確保する必要があることから、値上げが実施されます。
将来的にも少子高齢化が進むことが見込まれるため、今後も社会保険料の値上げは続くでしょう。そのため、制度の安定化のためには値上げだけにとどまらず、医療費の削減などの多角的な対策が必要といえます。
医療費増加
高齢者は医療機関や介護サービスを利用することが多いため、高齢者人口が増えると医療費と介護費も増えることは明確です。高齢化率が高まれば、医療費も比例して増加することを意味し、その結果医療費負担の増加により社会保険料の負担増につながります。
中低所得者層への配慮
国民健康保険料の上限引き上げの目的には、中低所得者層への配慮が挙げられます。
中低所得者層の給与がなかなか上がらない中、社会保険料を値上げしてしまうと手取り収入が減少して消費が減退し、全体的に見ると経済の停滞または悪化が懸念されます。.
社会保険は、標準報酬月額に応じた料率で算出されるため、上限を上げて高所得者層の負担を上げることによって、保険制度の維持を目指します。

社会保険料の値上げで予想される影響

社会保険料の値上げは、単なる自己負担の増大だけではなく、企業や社会保険制度そのものに至るまで、さまざまな方面での影響が予想されます。
手取り収入の減少
社会保険料が値上げされると、給与から天引きされる額も増え、手取り収入が減少します。月々わずかの負担増であっても、年間の負担額として見ると1万円以上の負担増となる可能性があり、家計への影響は少なくありません。
特に若い世代の手取り収入が減少することによって、資産形成や生活水準の維持が難しくなるなどの影響が考えられます。
雇用形態の見直し
社会保険の費用は企業と従業員が半額ずつ負担するため、社会保険が値上げされると企業の負担が増加します。社会保険料の値上げが続き負担が増大すると、企業は負担軽減のために自社の従業員の雇用形態の見直しを行う可能性が考えられます。
特に、正社員は社会保険料の負担が大きいため、正社員の雇用を減らしてその他の形態での雇用に切り替えることで負担を減らすこともあるでしょう。
将来的な年金受給額の給付水準低下
後期高齢者が増加する2025年以降も少子高齢化の流れが続くことが見込まれるため、社会保険料を負担する働く世代が年々減少していくにつれて、社会保険制度そのものが圧迫されることも懸念されます。
その結果、年金受給額の給付水準が低下したり、年金受給開始年齢が引き上げられたりすることも十分考えられます。これらの制度変更は生活に大きく影響することから、将来への不安が大きくなる要因となり得ます。

今後も見込まれる社会保険料の値上げ

社会保険制度維持のため、今後も制度の変更や改正が行われるものと考えていいでしょう。特に、社会保険料の負担は今後も増加することが予想されます。つい最近も、基礎年金の給付水準を引き上げるための財源として厚生年金保険料を使う案が出たことについて、否定的な意見が多く出ていたことも記憶に新しいのではないでしょうか。それだけ、社会保険制度の維持が難しくなっているのが現状です。
そこで政府は、社会保険制度の維持を図るためにさまざまな施策を進めています。例えば、社会保険料を負担する人を増やすために社会保険の適用対象者の拡大、ジェネリック医薬品の利用や予防医療の推進による医療費増加の抑制などがその一例です。
社会保険料の値上げは、現役世代の費用負担に直結し、日常生活や将来の人生設計にまで大きな影響を及ぼすものです。現役世代の方は、今後の変化を想定しつつ人生設計の見直しに対応していくことが求められるでしょう。
個人ができる社会保険料の値上げ対策

社会保険料の料率は個人が変えられるものではないものの、働き方を工夫することで社会保険料の負担を抑えることが可能です。恒常的に社会保険料を抑えられる方法はないため、自分自身で資産を見直すことも、社会保険料の値上げ対策となるでしょう。そこで具体的な値上げ対策について、2種類の方法を解説します。
働き方を見直す
社会保険料は、毎年4~6月の給与を元に標準報酬月額を基準として算出する「定時決定」、固定給が大幅に増減した際に見直す「随時改定」、そして賞与に基づいて別途算出される「賞与支給時」の3種類の改定方法があります。この中で、自分自身で調整しやすいのは定時決定です。
4~6月の3ヶ月間の給与が高いとその分標準報酬月額も高くなり、社会保険料の負担も上がります。企業で働いている人の場合、基本給を自分で調整することは難しいため、残業時間を調整して定時決定の保険料の調整を試みてみましょう。標準報酬月額は残業代も含めた額で算出されるため、基本となる4~6月の残業時間を減らすことで、その年9月から1年間の社会保険料を抑える効果が期待できます。
また、昇給や賃上げ交渉を行うケースもあるでしょう。交渉を行った結果、4月から昇給や賃上げが行われてしまうと、標準報酬月額に影響します。昇給や賃上げが7月以降に行われるように交渉を行うと、その年の社会保険料を抑えられます。
資産形成を検討する
社会保険料を抑えるには、上記の標準報酬月額を抑える方法がありますが、翌年4~6月まで同じ水準の給与となった場合は標準報酬月額が上がるため、結果的に翌年以降の社会保険料は値上がりします。
自分自身で社会保険料の負担を抑え続けることは困難であるため、社会保険料の負担増で経済的に不安を感じる場合は資産形成を検討してみましょう。資産形成には、つみたてNISAやiDeCoを活用するなど、さまざまな方法があります。勤務先企業で確定拠出年金の制度が用意されているのであれば、加入を検討してみてもいいでしょう。
自分自身で資産形成を行うには、副業を始めるのも選択肢の一つです。本業の合間に働くこととなるためプライベートの時間が削られることがあり、年間20万円以上の収入が発生した場合は確定申告が必要となりますが、社会保険料の負担をカバーするための対策として有効な手段となるでしょう。

企業ができる社会保険料の値上げ対策

社会保険料の値上げは、企業にとっても大きな負担になり得ます。働く世代が減っている中で企業ができる社会保険料値上げ対策は、まずは人手不足を解消し、その上でできる対策を実施してみましょう。
人手不足の解消
企業に限らず、少子高齢化が進み働き手となる世代が減少傾向にある日本は全体的に人手不足の状態といえるでしょう。前述した通り、今後も日本の少子高齢化は進むことが予想されているため、人手不足はますます深刻となるでしょう。人手不足は社会保険制度維持をますます厳しくする要因で、かつ企業の存続にも大きく関わる問題です。
そこで、企業単位でも人手不足を解消して働き手を増やすことが、社会保険料値上げ対策の基本といえます。「この会社で働きたい」と求職者や新卒者が思えるような魅力的なポイントを作ることが、人手不足解消の方法となるでしょう。後述する対策のほか、働きやすい環境作りのために業務効率化を行うことも、効果的です。
給与引き上げ
上記の人手不足解消のために企業が行えることの一つが、給与の引き上げです。複数の同じ職種の仕事がある場合、誰しもが給与の高い企業を選ぶことは明白です。
優秀な人材を確保するための方法の一つとして、厚生労働省が実施しているキャリアアップ助成金を受ける方法もあります。キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善の取り組みなどのキャリアアップ促進を行った企業に対して行われている助成制度です。
キャリアアップ助成金を受ける条件が整っていれば、非正規雇用の労働者のみならず、すべての従業員の労働環境改善にもつながります。離職率を抑えられる効果も期待できるため、より優秀な人材確保が可能となるでしょう。
充実した福利厚生の導入
優秀な人材確保や従業員の定着率アップには、職場環境の充実が必要不可欠です。そのための施策の一つが、福利厚生の導入です。
福利厚生には、法律で定められている法定福利厚生、企業が任意で行う法定外福利厚生の2種類があります。このうち、法定外福利厚生の充実は、定着率アップ効果が期待できる方法です。求職者や新卒者が求人をチェックする際にも、福利厚生は重要なポイントとなっているため、福利厚生を充実させることによって優秀な人材確保も叶うでしょう。
代表的な法定外福利厚生には、従業員の食費や旅費を削減できる食事補助や旅行割引などがあります。福利厚生を導入するには企業の費用負担が発生しますが、従業員のニーズを満たす福利厚生を充実させることによって従業員エンゲージメントアップが期待できます。
福利厚生にかかる費用は全額非課税となるので、充実した福利厚生の導入は従業員の実質的な費用負担を下げつつ、企業の税負担の軽減も可能となる方法です。
まとめ
2025年度から社会保険料のうち、健康保険料の値上げがすでに行われており、近い将来厚生年金の上限引き上げも検討されています。少子高齢化が進んでいる中、働き手である若い世代が減少している状況で、社会保険の値上げは一人ひとりにかかる負担を増やす要因となっており、働く人と雇用する企業双方に悪影響が予想されます。
社会保険料の負担は個人や企業単位で変えられるものではありませんが、個人での工夫や企業の人手不足の解消で負担軽減効果が期待できます。将来の人生設計にも大きく関わる負担を減らすために、早い段階から負担軽減のための情報を収集し、対策を講じてみましょう。
福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>