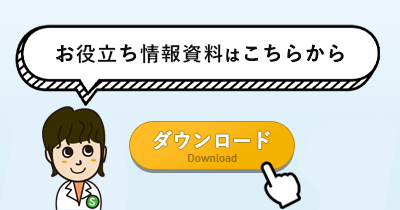軽減税率が企業や消費者に及ぼす影響とは?メリット・デメリットやトランプ関税の影響も併せて解説

こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。
消費税は、食料品や日用品など、毎日生活する上で必要となる物すべてにかかる税金です。前回2019年の消費税増税時、一部の品目に「軽減税率」が適用となり、消費税率は2種類が混在することとなりました。軽減税率とはどのような制度で企業や消費者にどのような影響を及ぼすのでしょうか。
本記事では、改めて軽減税率の基本をおさらいした上で、軽減税率によるメリット・デメリット、消費税の問題とはまた別に、現在進行形で全世界的に世界経済へ大きな影響を及ぼしている「トランプ関税」について解説します。
福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉
目次
軽減税率とは?

軽減税率とは、2019年10月の消費税増税時に低所得者への配慮と税負担緩和を目的として導入された制度です。2019年10月、消費税は8%から10%に引き上げられましたが、軽減税率対象品目に関しては、消費税率が8%と従来の税率に据え置きとなりました。
2025年5月現在も、日常生活で購入する機会が多い物に対する税率として軽減税率の制度は続いています。
軽減税率が導入された経緯と目的
食料品などの生活必需品は、所得にかかわらず生きていためにすべての人が消費しなければならないものです。所得に応じて税率が変わる所得税とは異なり、生活必需品にかかる消費税はすべての人に同じ税率が課されます。低所得者は生活必需品の消費支出の割合が大きいため、高所得者よりも消費税負担が大きくなる「消費税の逆進性」の問題について、消費増税のたびに多方面で議論されてきた経緯があります。
そこで2019年の消費税増税時、低所得者の消費支出の割合が大きい品目の消費税率を据え置くことによって消費税の逆進性を緩和することを目的として、軽減税率が導入されました。
軽減税率の対象となる品目
軽減税率の対象となる品目は、「食品表示法で規定された酒類や外食を除く飲食料品」及び「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」とされています。飲食料品に関してはデリバリーやテイクアウトも対象ですが、単純に酒類以外すべてが軽減税率の対象となるわけではありません。
飲食料品の場合、購入した飲食料品を自宅など店外に持ち帰る場合は軽減税率が適用されます。しかし店内に設置されたイートインスペースで飲食する際は店内飲食を扱われるため、その飲食料品は軽減税率の対象外となり標準税率の10%が課税されます。また、出張料理やケータリングも、「飲食料品の提供」に該当するため軽減税率の対象外です。
その他にも、飲食料品と景品などがセットになった商品などの軽減税率の対象品目と非対称品目のセットは、資産の価格のみが提示されている場合に「一体資産」とされます。一体資産は、税抜価格1万円以下かつ食品の価額が3分の2以上を占める場合はすべてが軽減税率の対象となりますが、それ以外のケースでは原則的に軽減税率の対象外となります。
インボイス制度にも影響が及ぶ軽減税率
2023年10月より、複数税率に対応した仕入れ税額控除方式「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」がスタートしました。
インボイス制度は、消費税額と消費税率を正しく把握するために実施される制度で、軽減税率の導入によって2種類に増えた消費税率によって起こる消費税額の計算間違いや複雑になった事務処理を解決するために導入されました。インボイス制度では、軽減税率の対象品目を明確にし、税率ごとに売上と仕入れを区分して計算を行う必要があります。つまり、軽減税率の導入によって複数の税率となったことで、税額計算が従来よりも複雑となりました。
もし軽減税率の取り扱いを誤ってしまうと、消費税を多く納めなければならない事態も出てくるため、軽減税率はインボイス制度にも影響が及んでいます。

軽減税率のメリット

軽減税率は、文字通り10%の標準税率よりも税率が軽減されているため、適用となる品目の購入に際して以下に挙げるメリットが期待できます。
対象品目の売上低下の抑制
軽減税率によって企業が得られるメリットの一つは、売上低下の抑制です。消費税率が上がると、一般的に購買意欲は低下するといわれます。特に低所得者は消費税増税で出費が増えてしまうため、生活に必要不可欠な飲食料品の消費も抑えてしまう傾向にあります。
そこで軽減税率で飲食料品の税率を据え置きにすることで、消費税増税による消費意欲低下を防ぐと同時に売上低下も防げるのが、軽減税率のメリットといえます。
出前やテイクアウト需要増加が期待できる
前述したように、店内飲食にあたる外食やイートインの消費税には標準税率の10%が課税されることとなります。一方で、テイクアウトや出前などのデリバリーは対象外となるため、軽減税率が適用となります。消費税増税前はすべて同じ税率でしたが、軽減税率導入後は外食よりも税率が低く出費を抑えられるテイクアウトやデリバリーの利用が増えることが期待できるのがメリットです。
特に、テイクアウトや出前を提供している企業や事業者では、出前やテイクアウト需要の高まりによって売上アップも期待できるでしょう。
消費者は出費を抑えられる
軽減税率の導入は、消費者にとってもメリットが期待できます。軽減税率によって毎日の生活に必要な飲食料品にかかる消費税が据え置きとなるため、出費を抑えやすくなるでしょう。外食の頻度を抑えて自炊をする、またはテイクアウトなどを利用するだけでも、標準税率との差額分の節約効果が期待できます。

軽減税率のデメリット

軽減税率が適用となることによっていくつかのメリットが得られることは確かですが、一方で複数の税率が混在することによって、これまでにはなかった手間がデメリットとなると考えられます。
事務処理の手間がかかる
軽減税率の導入によって2種類の消費税率が混在することとなるため、企業や事業所にとっては従来よりも経費管理などの事務処理の手間がかかってしまうことが第一のデメリットです。軽減税率の導入直後は、2種類の税率に対応するためのレジなどの会計システムを一新する必要があり、2種類の税率に対応する手間やコストがかかっていました。
導入後5年以上経過した現在、軽減税率に対応できている企業や事業者がほとんどでしょうが、事務処理にかかる負担は制度がある限り続きます。今後も2種類の税率に対応し続けなければならず事務処理の手間や負担が従来よりもかかってしまう点は、軽減税率のデメリットといえるでしょう。
対象外品目の線引きが難しい
飲食料品のテイクアウトやデリバリーは軽減税率の適用となりますが、コンビニエンスストアやフードコートでの飲食では軽減税率対象外品目の線引きが難しくなってしまいます。
例えば、テイクアウトとして購入後の飲食料品を店内のイートインコーナーやフードコートで食べてしまうケースがあります。本来、店内での飲食は標準税率の10%が適用となりますが、テイクアウトとして扱った飲食物を購入後、店内に持ち込んで飲食した場合であっても、店側が差額分を請求することは困難でしょう。
このようなケースが起こり得るにもかかわらず、軽減税率の対象外に関する明確な線引きがありません。そのため、購入者の自己申告で線引きをしなければならない点も、軽減税率のデメリットの一つです。

軽減税率による企業への影響

軽減税率は、企業へとっても影響が及ぶ制度です。たとえ軽減税率の対象品目を取り扱わない企業であっても、少なからず影響が及ぶことが考えられます。
複数の税率に対する事務処理負担増加
デメリットでも述べたように、軽減税率の導入は企業においての事務処理負担が増加する影響が考えられます。従来1種類のみだった税率が2種類に増えるだけでも、税額記載のための請求書作成・発行の手間は増えます。税率計算においても、2種類の税率で計算しなければならないため、事務処理負担が増えることは明らかでしょう。
企業では取り扱う品目や量が多くなるため、その分事務処理にかかる負担が大きく、コスト増にもつながってしまいます。
対象品目を取り扱わない企業も無関係ではない
軽減税率は、基本的に飲食料品と定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞に適用されます。これらの品目を取り扱わない企業には軽減税率の影響はないと思われがちですが、まったく影響がないわけではなく、無関係とも言えません。
軽減税率の対象品目を取り扱わない企業であっても、飲食料品を取引先へのお土産などとして購入する場面はあるでしょう。また、業務中や休憩中に従業員が自由に飲めるドリンクやウォーターサーバー、お菓子などを購入している企業もあるはずです。これらはすべて軽減税率の対象品目であるため、経理処理を行う時点で軽減税率での対応が必要となる点に注意が必要です。

軽減税率による消費者への影響

軽減税率は、当然ながら飲食料品を日常的に購入する消費者への影響も大きくなります。本来、消費者の負担を軽減するための軽減税率ですが、実際にはそれほど大きなメリットを感じないこともあるでしょう。
外食費の増加
軽減税率は日常的な支出となる飲食料品に適用されるため、食費にかかる負担軽減につながると考えられます。できるだけ自炊をして、テイクアウトやデリバリーを利用することで消費税分の支出を抑えることは可能ですが、まったく外食をしないわけにはいかないこともあるでしょう。
外食をする場合、すべて消費税率は標準税率の10%が適用となります。そのため、外食費だけで見ると消費税率2%の差がそのまま外食費増加につながる点が、軽減税率による消費者への影響の一つといえます。
低所得者の方がメリットが薄い
低所得者の税負担緩和のために導入されている軽減税率ですが、実は低所得者の方がメリットが薄いといわれます。その理由は、食費にかける費用の差です。
飲食料品にかける費用のみで比較すると、高所得者の方が低所得者よりも食費が高いのが一般的です。飲食料品にかけるお金が多い方が、より軽減税率の恩恵を受けて食費を抑えられると考えると、食費にかけるお金が少ない分、低所得者が受けるメリットは薄いと考えられます。
本来、消費税の逆進性緩和のために導入されたはずの軽減税率ですが、単純に食費で比較してしまうと、低所得者よりも高所得者のメリットの方が大きいのです。

軽減税率はいつ終わる?

軽減税率は一時的な措置で、いずれは廃止されるものという話を耳にしたことがある方がいるかもしれません。しかし結論から言うと、軽減税率という制度に期限はありません。軽減税率は消費税法を基に運用されている制度ですが、法律には期限が特に記載されていないのが、その根拠です。
将来的に法律が改正された場合、軽減税率が終わる可能性はゼロとはいえません。しかし、法律が変わってしまうと消費者や企業、販売業者などに大きな混乱が生じることが予想されるため、そう簡単に内容が変わるものではありません。
世界的に物価高が続いている現在、日本でも物価上昇が顕著です。軽減税率が導入されている中でも、現在の物価高騰によって消費税引き下げの声が出ているほどなので、もし軽減税率が廃止されてすべての飲食料品に10%の消費税が課された場合、消費活動が落ち込むことは火を見るより明らかです。
このような理由からも、軽減税率が終わることは現状、現実的ではないといえるでしょう。

今後影響が及ぶ?今注目のトランプ関税
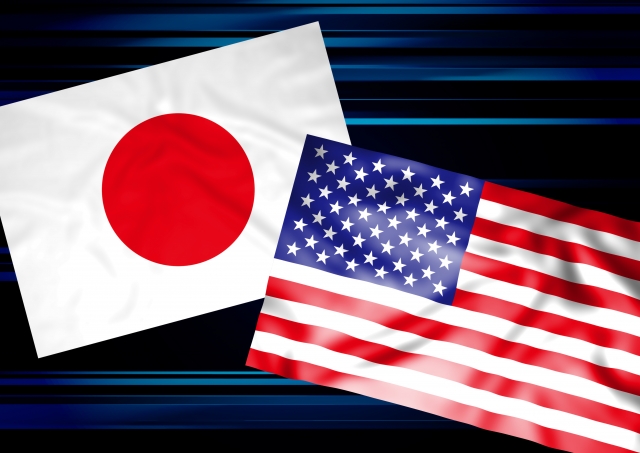
2025年1月、ドナルド・トランプのアメリカ合衆国大統領就任後より、いわゆる「トランプ関税」が世界経済に大きな影響を与えています。トランプ関税とはどのようなものなのか、そして日本の一般消費者へも影響を及ぼすものなのでしょうか。
そもそもトランプ関税とは
トランプ大統領は、大統領選挙前から自国の産業保護、貿易不均衡などを是正するために追加関税を課す考えを表明していました。なぜトランプ大統領が諸外国へ追加関税を課すのか、それは貿易赤字の縮小と自国の製造業強化が主な理由です。
アメリカの貿易赤字は2024年、過去最大を更新したことが、アメリカ商務省の発表で明らかになっています。トランプ大統領は、この貿易赤字を問題視しており、追加関税によって赤字縮小を目指しています。同時に、関税を上げて海外からの輸入を縮小する代わりにアメリカ国内での製造業の国内回帰を目指すことも、目的の一つとされています。
参考:読売新聞「アメリカの貿易赤字185兆円、過去最大を更新…国別トップは中国・日本は7番目」
日本への関税も引き上げ対象に
トランプ大統領は、まずカナダとメキシコを対象に25%の関税、中国に対しては10%の追加関税を発表し、その他の国々に対しても、それぞれ異なる追加関税の上乗せを発表しました。その後中国が報復関税を発表したことに対抗し、トランプ大統領はさらに対中国の関税引き上げを発表したことなどから、「世界貿易戦争」として世界市場の混乱を招くと多方面からの批判や懸念が高まっています。
日本に対する関税もトランプ関税の例外ではなく、日本に対しては24%の相互関税が発表されました。しかし、トランプ大統領が発表した相互関税の引き上げは、まだ正式には発動されてはいません。追加関税の発表直後、金融市場の混乱を抑えるために90日間の停止が発表されたからです。その間に各国との協議が続いているため、2025年5月現在、対米関税に関してはまだ流動的な状況が続いています。
一方5月3日、輸入されるすべての自動車部品に対しての25%の追加関税が発動され、今後日本の自動車部品メーカーへ及ぶ影響が懸念されています。
トランプ関税で考えられる影響
まず知っておきたいのは、ここまで解説した消費税と関税は異なるものということです。消費税は国内で消費されたものに課される税金、関税は輸入品に課される税金のことです。関税を個人で支払う機会があるのは通常、海外旅行先で購入した物品や個人輸入した物品程度なので、トランプ関税と言われてもピンとこないかもしれません。
しかし、世界中を巻き込んだトランプ関税によって考えられる影響は、輸出入に関わる企業だけに限ったことではありません。日本企業へ大きな影響があるということは、その企業が販売する製品やサービスを購入する一人ひとりの消費者まで影響が及ぶ可能性があるのです。
日本企業が販売している製品を見ても、100%日本産の原料を使用して日本国内で製造されている物は限られます。日常的に使用している製品や口にしている食料品でも、輸入原料を使用したり海外で製造されたりした物、海外で生産された機械を使用して製造された物などが多いものです。つまり、日々使用しているもの、消費しているもので関税がまったく関わっていないものは非常に少ないといえます。
トランプ関税に関しては、特に自動車や自動車部品のほか、医療機器や半導体製造装置、建設機械などに大きな影響が及ぶと予想されています。これらの機器を使用する企業では、トランプ関税によって輸出コストや原料価格の増加が見込まれており、これらのコスト増は価格転嫁や生産体制の見直しでカバーすることとなるでしょう。トランプ関税によって企業が被るコストは製品価格などに転嫁されるとすると、さまざまな物品の価格が今以上に高騰し、消費が落ち込むことも予想されます。
参考:経済産業省「米国の日本からの輸入品目と追加関税賦課状況」

消費税や関税による値上げ対策に有効な福利厚生

近年、世界規模で物価高が著しく、日本でも消費増税による値上げに加えて円安の影響で、物の価格は高騰を続けています。これから発動されると予想されるトランプ関税の影響により、さらなる物価高が懸念されます。
外食費に関しても、米の価格急騰や原料価格の上昇などにより食費にかかる負担が増えていると感じている人は多いことでしょう。働いている人の昼食代一つ取っても、外食費が増えることで毎日の食費負担は増加していきます。
そのような日々の食費にかかる負担を軽減する方法として企業にとって有効な手段が、福利厚生の導入です。食事に関わる福利厚生には、社員食堂の設置や置き社食などさまざまな種類があります。
心幸グループでは、従業員の食費軽減に寄与する社員食堂や企業内売店・コンビニの運営、リーズナブルに利用できる置き社食「オフめし」などをトータルでサポートしています。毎日栄養バランスの整った食事を提供することで従業員の食費負担を軽減しつつ、健康経営につなげられます。

まとめ
軽減税率は、主に消費支出の割合が大きい日々の生活に必要な飲食料品にかかる消費税を8%に抑えた制度です。持ち帰りやデリバリーでも適用される軽減税率ですが、外食費は10%の消費税がかかるため、外食費の増加や税率の混在による手間などのデメリットも生じています。物価が高騰している現在、トランプ関税によって消費者への価格転嫁が起こると、さらなる物価上昇による消費の落ち込みも懸念されます。
外食にかかる費用が増えることによる従業員の食費負担を軽減するための対策には、企業が福利厚生を導入するのも一つの方法です。福利厚生を導入して食費負担の軽減と同時に、従業員の満足度アップにもつながる福利厚生導入を、検討してみてはいかがでしょうか。
福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>


オフィスにつくる設置型ミニコンビニ

「オフめし」はオフィスの一角にミニコンビニ(置き社食)を設置できるサービスです。常温そうざいや冷凍弁当の他に、カップ麺やパン、お菓子など約600アイテムから成る豊富なラインナップが魅力。入会金2万円(税抜)+月6,000円(税抜)+商品代+送料からスタート可能で、手軽に従業員満足に貢献できます。
オフめしはこちら