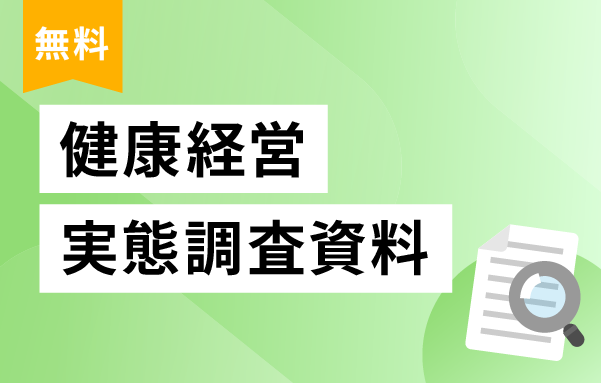エイジフレンドリーガイドラインとは?高年齢労働者が安全で健康的な職場を確保するための対策も紹介

こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。
少子高齢化によって労働者不足が深刻化し、働く高齢者の増加に伴って労災の発生率が高まる中、厚生労働省が定めるエイジフレンドリーガイドラインに沿った取り組みが重要です。
エイジフレンドリーとは、「高年齢労働者の特性に配慮した」という意味を持つ言葉を指します。
エイジフレンドリーガイドラインに基づいた、長く働ける職場環境を実現することで、高年齢労働者も含めたすべての労働者が安心かつ快適に働くことが可能です。
そして、結果として企業の人手不足解消につながり、生産性向上に寄与します。
この記事では、エイジフレンドリーガイドラインの概要や注目される背景、5つのポイントを紹介します。
エイジフレンドリーガイドラインに沿った職場環境を実現する際に必要な対策もあわせて解説するので、高年齢労働者を活用して人手不足解消につなげたい経営者や人事担当者は、ぜひ参考にしてください。
福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉
目次
エイジフレンドリーガイドラインとは?

エイジフレンドリーガイドラインとは、2020年に厚生労働省が公表した「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)」のことです。
具体的には、高年齢労働者を現に使用していたりこれから使用する予定であったりする職場において、誰もが安心・安全に働ける職場環境を築くため、事業者や労働者に求められる具体的な取り組みをまとめたものです。
取り組みの例として、主に以下のことが挙げられます。
・柔軟な働き方ができる制度を取り入れる
・高齢従業員の身体的特性に合わせて、作業環境を改善する
・健康管理体制を強化する
こうした考え方は、WHO(World Health Organization:世界保健機関)や欧米の労働安全衛生機関が始まりです。
そして、日本では2020年より正式にエイジフレンドリーガイドラインを公表し、さらに2021年4月1日から高年齢者雇用安定法の改正によって、企業には70歳までの就業機会を確保するための措置を講じる努力義務が課されています。
このように、健康寿命の延長や少子高齢化による労働力不足といった社会背景を受け、高年齢労働者が安心・安全に働ける職場環境の構築や、労働災害を未然に防ぐための健康づくり推進は、高齢者の就業意欲を高めるうえで重要となっています。

エイジフレンドリーガイドラインが注目される背景

エイジフレンドリーガイドラインに沿った取り組みが昨今、重要視される背景には、主に以下の3つの要因があります。
・深刻な労働力不足を抱えている
・働く高齢者が増加傾向にある
・高年齢労働者に占める労働災害の発生率が高い
これらの点を踏まえると、今後より一層エイジフレンドリーガイドラインに基づいた推進が不可欠となります。
深刻な労働力不足を抱えている
日本では少子高齢化が急速に進展しており、15歳から64歳までの「生産年齢人口」が減少の一途をたどっているのが現状です。
これにより、多くの業界・企業で深刻な労働力不足が顕在化しています。
内閣府が公表した「令和6年版高齢社会白書(全体版)」によると、総人口に占める生産年齢人口の割合は59.5%と年々低下している一方で、65歳以上の人口割合は29.1%と増加傾向にあります。
これに伴い、現在の労働市場では、高年齢労働者が生産年齢人口の減少分を補う形となっているのが実情です。
今後も高年齢労働者の増加が見込まれることから、企業にはこれまで以上に高齢者にとって働きやすい職場環境の整備が求められています。
働く高齢者が増加傾向にある
日本では、高年齢労働者数が毎年増加しており、65歳を超えても働き続けたいと考える人が増えています。
総務省統計局の「高齢就業者数の推移」によれば、高齢就業者数は18年連続で増え続け、2021年には過去最多の909万人を記録しました。
また、厚生労働省の「エイジフレンドリーガイドライン」によると、特に商業や保健衛生業といった第三次産業で働く高齢者が顕著に増加しています。
このように、全労働者に占める高齢労働者の割合が増えているため、職場環境の改善への取り組みは欠かせない施策となっています。
高年齢労働者に占める労働災害の発生率が高い
高年齢労働者は、若い世代と比べて身体能力や反応速度が低下する傾向があるため、労働災害のリスクが高くなります。
厚生労働省が公表した「令和5年 高年齢労働者の労働災害発生状況」によると、労働災害による死傷者全体に占める60歳以上の割合は29.3%でした。
これは、20年前と比べて約2倍に増加しており、年々上昇傾向にあります。
さらに、60代以上の労働災害発生率を男女別で見ると、男性が0.93%であるのに対して女性は2.41%と、女性の方が2倍以上も高い発生率を示しています。
加えて、20代と比較すると、男性で約3.6倍、女性に至っては約15.1倍も発生率が高く、高年齢労働者を雇う企業にとって看過できない課題です。
労働災害の内容としては、特に墜落・転落・転倒が多く見られます。
このように、加齢に伴う身体能力や反応速度の低下は、わずかな段差であっても足を取られて大きなケガにつながるおそれがあります。
高齢者が安心して働ける職場環境を構築するためにも、安全対策や作業負担の軽減策を取り入れ、エイジフレンドリーガイドラインに基づいた取り組みを推進することが重要です。

エイジフレンドリーガイドラインにある5つのポイント

高年齢労働者が安心・安全に働ける職場環境を構築するため、そして労働災害を未然に防ぐためにも、厚生労働省の「エイジフレンドリーガイドライン」にある5つのポイントを実践することが不可欠です。
・安全衛生管理体制の確立
・職場環境の改善
・高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
・高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
・安全衛生教育
それぞれのポイントについて、順を追って解説します。
安全衛生管理体制の確立
高年齢労働者が安心して働ける環境を築くうえで、強固な安全衛生管理体制の構築は欠かせません。
安全衛生管理体制は、労働災害の発生を防止するにあたって、組織的に取り組むための基盤となります。
具体的な施策として、以下のとおりです。
・経営陣が労働災害防止に向けた安全衛生に関連した明確な方針を打ち出す
・方針に取り組むにあたって、担当者や組織を明確に指定する
・従業員の意見を積極的に聴き、リスクアセスメント(危険性の評価)の機会を設ける
・潜在的な危険要因を特定して対策を講じる
・労働安全衛生上のリスクや業務負担、体調不良などについて気軽に相談できる窓口を社内に設置する
上記の施策を実施して、風通しの良い職場文化を育みましょう。
職場環境の改善
年齢を重ねるにつれて、体力や筋力の低下といった身体的な変化は避けられません。
そのため、高年齢労働者がいる職場では、安全面において特別な配慮が求められます。
職場環境の改善としては、作業スペースの工夫や適切な設備の導入が不可欠です。
具体的には、以下のような対策を実施することで、高年齢労働者の身体的負担を軽減し、より快適に働ける職場を実現できます。
・滑りにくい床材への変更
・警報音は聞き取りやすい中低音域の音
・高さを調節できる作業台の設置
・涼しい休憩場所を設けて、通気性の良い服装を準備する
・段差による転倒を防ぐためのスロープの設置
・解消できない危険箇所に標識やポスター等で注意喚起
・視力に合わせて照明の明るさを調整できる機能
加えて、高年齢労働者の体力や健康状態を考慮し、勤務形態を柔軟に調整できる仕組みを構築することも重要な要素です。
高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
高年齢労働者の健康管理を強化するためには、最初に各従業員の健康状態と体力を正確に把握し、それらの情報に基づいて適切な措置を講じることが大事です。
その際、定期的な健康診断と体力チェックの実施が不可欠です。
健康診断については、労働安全衛生法に基づく雇入時および定期健康診断を必ず実施する必要があります。
さらに、従業員自身が高齢に伴う身体機能の変化を理解し、主体的に健康管理に取り組めるようなサポートも重要です。
一方で体力チェックに関しては、事業者と従業員の双方が客観的に体力の状況を把握し、その結果に基づいて、無理のない範囲で適切な業務への配置を行うことが大切です。
また、従業員自身が体力維持・向上に努めることも重要なポイントとなります。
これらの取り組みを実施する際は、企業の明確な方針を示し、対象となる従業員に対して、体力チェックの目的を丁寧に説明し、理解と協力を得ることが成功の鍵です。
高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
高年齢労働者の健康状態や体力状況を踏まえた措置として、以下の3つの取り組みは不可欠です。
・各従業員の健康状態や体力状況に基づく措置:各従業員の健康診断や体力測定の結果を踏まえ、その人に合った業務内容や労働時間を設定する
・高年齢労働者の状況に応じた業務の提供:高年齢労働者の体力やスキルに適した業務を提供し、過度な負担のない作業環境を整備する
・心身両面にわたる健康保持増進策:健康維持のための運動機会の提供や、メンタルヘルスケアの支援を行い、心身機能の維持向上に取り組む
加齢に伴い脳や心臓の疾患、がんなどの発症リスクが高まるため、各従業員の健康状態に合わせた労働時間や業務内容の調整は重要です。
もし、持病を抱えながらも働き続けることを希望する従業員がいる場合は、治療と仕事が両立できる体制を整えることが求められます。
また、業務内容や労働時間の変更を行う際は、従業員と十分に話し合って、本人の理解と同意を得ることが不可欠です。
さらに、以下の観点に基づいて、健康づくりに取り組むことも重要です。
・高年齢労働者自身が身体機能の維持・向上に努める
・企業が従業員の健康管理を経営戦略の一環として捉え、戦略的に取り組む「健康経営」を実践する
・健康保険組合や協会けんぽを通して保険者と企業が連携し、従業員の健康増進を図る「コラボヘルス」の視点を取り入れる
こうした高年齢労働者の健康管理への取り組みは、結果として企業全体の生産性やパフォーマンス向上につながります。
安全衛生教育
安全衛生教育は、高年齢労働者向けと管理監督者向けの2種類に分けられます。
高年齢労働者向けの教育では、実際の作業内容や潜在的なリスクについて、言葉だけでなく写真や映像を効果的に用いて、より深い理解を促します。
特に、再雇用や再就職などによって未経験の業務に就く場合は、きめ細やかな説明と実践的なトレーニングが欠かせません。
一方で管理監督者向けの教育では、高年齢労働者特有の身体的・精神的特徴や、それらに対する適切な対策についての知識習得が求められます。
例えば、転倒防止トレーニングや腰痛予防講座といった具体的な対策を実施すると効果的です。
これらの教育を実施するにあたって、管理監督者が主体となって推進し、職場全体の理解と協力を促すことが重要となります。

エイジフレンドリーガイドラインに沿った職場を実現するために必要な対策

エイジフレンドリーガイドラインに沿った職場を築き上げるためには、高年齢労働者を含むすべての従業員がその重要性を理解し、積極的に対策を推進することが不可欠です。
具体的な対策として、以下のことが挙げられます。
・柔軟な働き方ができる制度を取り入れる
・ストレスチェックを実施する
・賃金・労働条件の見直す
・従業員の急な欠勤や退職に備える
・エイジアクション100を活用する
・若手従業員による協力を促す
・メンタルヘルスに関する研修を行う
・従業員同士のコミュニケーションを活発化させる
・身体機能の低下を補う設備・装置を導入する
・高年齢労働者の特性を踏まえた作業管理を行う
それぞれ順を追って解説します。
柔軟な働き方ができる制度を取り入れる
エイジフレンドリーガイドラインに基づいた職場を実現するにあたって、高年齢労働者が無理なく働けるよう、柔軟な働き方を推進することが重要です。
具体的には、以下のような働き方ができる制度を取り入れることが効果的です。
・時短勤務
・週休3日制
・時差出勤
・1時間単位の有給休暇
・在宅勤務やテレワークの活用
・個々の健康状態に応じた業務内容の設定
年を重ねるにつれて、体調不良や通院のリスクが高まる傾向にあるため、従業員自身の体力やライフスタイルに合わせて働ける職場環境を整えることが大事です。
さらに、こうした柔軟な働き方は、高年齢労働者のみならず若手従業員にも恩恵をもたらし、結果として職場全体の効率アップやコスト削減にもつながることが期待できます。
ストレスチェックを実施する
ストレスチェックは、高齢者をはじめとした全従業員のメンタルヘルス管理に欠かせません。
実際に、各従業員の心理的負担を評価し、高ストレス者を発見して適切なケアへつなげる重要な役割を担います。
ストレスチェックを実施することで、ストレスの程度や原因を客観的に把握でき、産業医や保健師の助言に基づいて、職場環境の具体的な改善策を講じることが可能になります。
特に、高年齢労働者が在籍する職場では、世代間のコミュニケーションや考え方の違い、業務内容や職場での役割変化によって、精神的なストレスを感じやすい傾向にあるため、定期的にストレスチェックを実施することが重要です。
なお、2025年5月現在、ストレスチェックの実施は従業員数が50人以上の企業に義務付けられていますが、高年齢労働者を多く雇用している企業は、規模にかかわらず実施を検討することをおすすめします。
参照元:厚生労働省・東京労働局|ストレスチェック制度について
賃金・労働条件の見直す
高年齢労働者のモチベーションを維持するためには、能力や貢献度を考慮した賃金・評価制度が欠かせません。
年齢に基づいた一律の賃金ではなく、職務内容や成果などに応じて適切に反映した労働条件に見直すことで、高年齢労働者は納得して働いてくれます。
また、2025年4月からは、高年齢雇用継続給付の給付率が15%から10%に変更となり、引き下げられました。
そもそも高年齢雇用継続給付とは、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者が、60歳時点と比較して賃金が75%を下回った状態で働き続ける場合に受け取れる給付金です。
本制度変更によって、手取り賃金が減少する高年齢労働者が少なからずいます。
企業には、こうした制度変更を考慮した賃金の見直しが必要となります。
参照元:厚生労働省|令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します
従業員の急な欠勤や退職に備える
高年齢労働者は、健康リスクや家庭の事情などによる突発的な欠勤や退職が多い傾向にあります。
そのため、企業はあらかじめ、従業員が足りなくなることを想定して、備えをすることが重要です。
具体的には、複数の従業員で業務を分担する「ワークシェアリング」を導入したり、マニュアルを整備して業務内容を可視化したりします。
また、業務の属人化を防ぐ体制を整えることで、従業員の急な欠勤時もスムーズな対応が可能です。
そして、新人や若手社員の教育にもつながり、組織全体の生産性向上にも寄与します。
エイジアクション100を活用する
そもそもエイジアクション100とは、高年齢労働者の安全と健康確保のための職場改善に向けて、厚生労働省が策定した100項目の取り組みをまとめたチェックリストです。
エイジアクション100を用いることで、職場の現状把握や課題の洗い出しを行えます。
実際に、エイジアクション100を活用した職場改善のステップとして、以下のとおりです。
| ステップ | 説明 |
| 現状把握 | 高年齢労働者の作業負荷の程度や健康状況、事業所内で過去に発生した労働災害の発生状況などの現状把握を行う |
| チェックの実施 | 実施体制を決定したら、チェックリストを活用して、取り組みの優先度を決める |
| 職場改善の実施 | 改善が必要な項目について、具体的な取り組みを実施し、職場環境の改善に努める |
上記のプロセスを継続して実施することで、エイジフレンドリーガイドラインに基づいた職場に近づくことが可能です。
参照元:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署|エイジアクション100<概要板>
若手従業員による協力を促す
エイジフレンドリーガイドラインに基づいた職場を築き上げるためには、高年齢労働者はもちろんのこと、若手従業員による協力を促すことも不可欠です。
その一環として、若手従業員にも産業保健活動の重要性を理解してもらうことで、職場全体で高年齢労働者をサポートする意識が向上します。
そもそも産業保健活動は、主に以下の3つの目的があります。
・業務上の健康問題を予防する
・従業員の健康増進に努める
・職場環境を改善する
従業員の健康は企業を経営するにあたって重要であり、労働災害や過労死などの問題が発生すると、場合によっては企業の経営状態が傾くおそれがあります。
そのため、近年では経営リスクを抑えるためにも、従業員の健康増進が欠かせないものになっています。
産業保健活動を効果的に実施するためには、従業員自身で産業保健活動の意義を理解し、自ら疾病予防や健康維持に関心を抱いてもらうことが大事です。
特に、高年齢労働者を雇用している職場では、従業員自身の健康管理だけでなく、高齢者特有の特性を理解して働きやすい職場づくりへの協力が必要となります。
メンタルヘルスに関する研修を行う
メンタルヘルス不調を抱えた従業員は、働く能力が低下して生産性やパフォーマンスが下がります。
もし、そのまま放置すると以下の精神疾患につながる可能性があります。
・うつ病
・双極性障害
・統合失調症
・パニック障害
こうした精神疾患の早期予防と対策を実施するためにも、メンタルヘルスに関する研修を実施するのが望ましいです。
研修を行う目的として、心の健康に関する正しい知識を提供し、良好なメンタルヘルスを保てる職場環境を構築することが挙げられます。
これにより、メンタルヘルス不調の早期発見や予防、発生時の適切な対処法などを学べ、従業員自身が対策を講じる力を付けることが可能です。
その結果、企業全体の業務遂行能力が向上し、生産性アップにつながるといえます。
従業員同士のコミュニケーションを活発化させる
エイジフレンドリーガイドラインに沿った職場を実現するためにも、従業員同士で良好なコミュニケーションを取ることは重要です。
コミュニケーションが活発化すると、以下のようなメリットが得られます。
・情報共有や協力体制がスムーズになる
・従業員のストレス軽減につながる
・業務効率や従業員の定着率がアップする
特に、高年齢労働者を雇用している職場では、世代間のギャップによって仕事がしにくくなるおそれがあります。
こうした業務上の課題を解決するためには、双方ともに理解と協力を得ることが重要です。
コミュニケーションを活発化させる具体的な方法としては、以下のような取り組みが挙げられます。
・リラックスして会話できる共用スペースを設置する
・部門・部署の垣根を超えて合同研修を実施する
・経営陣と従業員が顔を合わせて、直接意見を交換できる環境を整える
これらの取り組みを実施することで、企業全体を通して従業員同士の連携が深まり、高年齢労働者も含むすべての従業員にとって働きやすい環境を整備できます。
身体機能の低下を補う設備・装置を導入する
高年齢労働者が安全かつ効率的に作業を行うためにも、加齢に伴う身体機能の低下を補うための設備や装置を導入することは不可欠です。
具体的には、事業所の実情に応じて優先順位をつけ、以下の取り組みを実施します。
・通路を含めて作業場所に十分な照度を確保する
・警報音は聞き取りやすい中低音域の音にする
・パトライトは有効視野を考慮して見やすい位置に設置する
・階段には手すりを設けてできる限り通路の段差をなくす
・作業台の高さや作業対象物の配置を作業姿勢に合わせて改善する
・涼しい休憩場所を整備して通気性の良い服装にする
・防滑靴を準備する
・解消できない危険箇所には標識やポスター等で注意喚起する
・リフトやスライディングシートなどを導入して抱え上げ作業を抑える
・水分・油分を放置せずこまめに清掃する
・床や通路の滑りやすい箇所には防滑素材(床材や階段用シート)を取り入れる
・熱中症の初期症状を把握できるウェアラブルデバイスをはじめとしたIoT機器を利用する
・作業中の体への負担を軽減できるパワーアシストスーツを導入する
・パソコン作業では照明や文字サイズを調整して見やすくする
こうしたハード面の対策は、労働災害のリスクを減らすだけでなく、作業の質と効率を維持・向上させることにもつながります。
高年齢労働者の特性を踏まえた作業管理を行う
高年齢労働者は、加齢による身体機能の変化をはじめとした特性を考慮した作業管理が必要です。
各従業員の能力を最大限に活かしつつ、無理なく安全に働いてもらうためにも、以下の対策を実施してマニュアルを見直しましょう。
・事業所の状況に応じて、勤務形態や勤務時間を工夫する
・ゆとりのある作業スピード・無理のない作業姿勢を促す
・注意力や集中力を必要とする作業は作業時間を考慮する
・こまめに休憩を挟む
・始業時の体調確認を行う
・体調不良時は速やかに申し出るよう促す
・パソコン作業では個々の労働者の特性に配慮した無理のない業務量にする
これらの対策を実施することで、従業員自身の能力を最大限に発揮でき、長期的に貢献できる環境を整えられます。

エイジフレンドリーガイドラインの実現には補助金を活用して「オフけん」を利用するのがおすすめ!

エイジフレンドリーガイドラインに基づいた職場を実現するためには、オフィスに健康を届けるサービス「オフけん」に対して、厚生労働省が推進している「エイジフレンドリー補助金」を利用するのがおすすめです。
そもそもエイジフレンドリー補助金とは、中小企業を対象に高年齢労働者を含むすべての従業員に向けて安心・安全に働けるよう、健康管理強化や労働災害防止のために取り組む活動を支援する制度です。
補助対象に該当すれば申請でき、補助率や上限額に応じて資金的なサポートを受けられます。
エイジフレンドリー補助金を活用した事例の一つである「オフけん」は、転倒防止や腰痛予防に焦点を当てた「出前からだ測定会」や「健康セミナー」などを実施しており、測定後には一人ひとりに合わせたカウンセリングや運動指導を受けられるのがポイントです。
年齢にかかわらず誰もが安心して健康的に働ける環境を整えたい企業にとって、「オフけん」は最適な選択肢となります。
まとめ:エイジフレンドリーガイドラインを理解して職場全体で働きやすい環境を構築しよう!

健康寿命の延長や少子高齢化に伴う労働力不足などを受け、エイジフレンドリーガイドラインに沿った職場の実現は、今後ますます重要性を増します。
そのためにも、転倒防止や腰痛予防などが挙げられ、これらの対策を実行するにあたってエイジフレンドリー補助金を活用するのがおすすめです。
エイジフレンドリー補助金を効果的に活用するためには、オフィスに健康を届けるサービス「オフけん」を利用するのがおすすめです。
「オフけん」では、体成分や体力を測定できる「出前からだ測定会」や、肩こり・腰痛予防体操を行う「健康セミナー」をはじめ、多種多様なイベントやプログラムを提供しており、各従業員の課題や状況に応じたサポートを受けられるのが強みです。
こうした取り組みを実施することで、結果として企業の生産性やパフォーマンスの向上につながります。
エイジフレンドリーガイドラインに基づいた働きやすい職場環境を構築したいのであれば、ぜひエイジフレンドリー補助金を活用して、企業全体で従業員の健康度を高めてみてはいかがでしょうか。
福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>