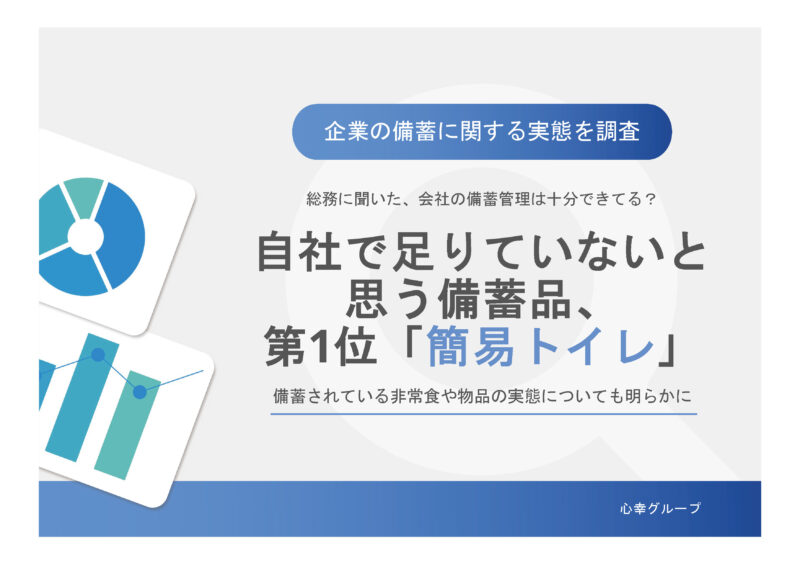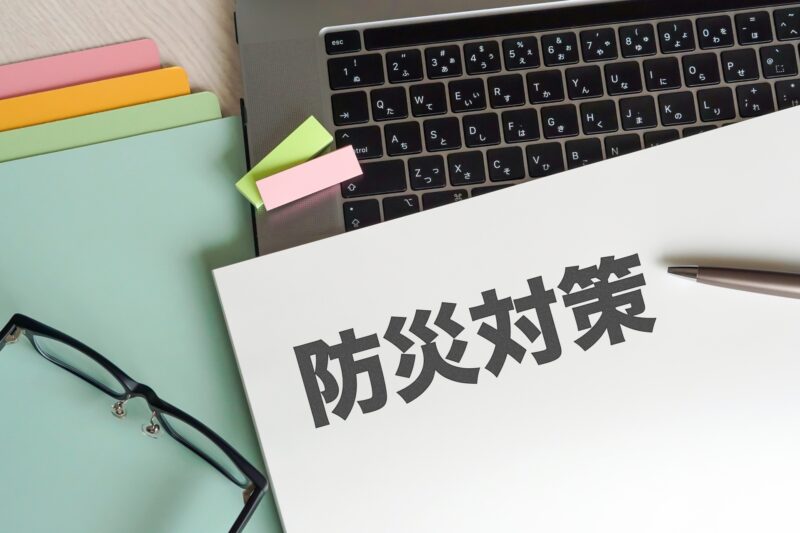企業で備える防災備蓄リスト|担当者と社員が知っておきたい備蓄品の基本一覧と必要な災害への備えの実践ポイント

こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。
防災備蓄は、万が一のときに“命をつなぐ準備”であると同時に、社会や取引先からの“信頼”を守る企業姿勢の表れでもあります。
企業が取り組むべき備蓄のあり方が、従来とは変わり新たな局面を迎えています。
この記事では、企業が備える防災備蓄について実践的な視点から見つめ直し、課題を解決するためのヒントを解説します。
福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉
目次
【防災の重要性】企業が備蓄すべき理由と背景

地震や台風など、日本での企業活動は常に自然災害のリスクと隣り合わせです。
南海トラフ地震や首都直下地震のような大規模災害が発生すれば「帰れない・動けない状況」が想定され、社員の安全確保と事業の継続が重大な課題になるでしょう。
企業が災害時に混乱を最小限に抑えるためには「備蓄」が不可欠である背景や、BCP(事業継続計画)と関連する実践的な備えについて解説します。
【「72時間問題」に備える重要性】 企業活動と災害リスクの現実
近年は南海トラフ地震や首都直下地震の発生が高い確率で予測されており、政府や自治体も大規模災害への対策を呼びかけています。
企業も例外ではなく、業種や規模を問わずに災害発生時の対応準備が強く求められる時代となりました。
災害対策のうち企業が注目すべき点として発災直後の「帰れない・動けない72時間の問題」が挙げられ、交通機関が停止すれば、多くの社員が職場に足止めされます。
特に都市部では、数万人規模の帰宅困難者が一斉に駅や道路にあふれる事態が想定されていることから、社会的混乱を引き起こす要因にもなり得ます。
この「72時間」は救助・支援が行き届かない時間帯で、行政やライフラインの復旧も遅れる可能性が高いとされています。そのため企業は従業員の安全を守り一人ひとりに冷静な行動を促すためにも、最低3日分の備蓄が不可欠です。
必要とされる備蓄は水や保存食だけでなく、簡易トイレ・毛布・モバイルバッテリー・マスク・衛生用品なども含まれます。これらは単に便利な物資ではなく、社員の命を守り混乱を最小限に抑えるための必需品です。
こうした現実的なリスクに向き合い、災害発生時にも冷静に対応できる体制を整えることが、企業の社会的責任として求められているのです。
BCP(事業継続計画)と備蓄の関係
災害時の備えは、単純に従業員の安全確保のためだけではありません。
企業における災害対策は、事業を止めずに早期復旧を実現するための「BCP(事業継続計画)」の一環として位置づけるべきものでもあります。
BCPとは地震や水害・パンデミックなどの緊急事態において、業務の中断を最小限に抑えて重要業務を優先的に再開するための具体的な計画です。
BCPの実効性を担保するためには、物理的な準備すなわち「備蓄」が欠かせません。
仮に、災害によって出社困難な社員がいても社内に最低限の備蓄があれば、現場に残った社員だけで必要な連絡やデータ保全も行えます。また在宅勤務が困難な環境でも、職場内に滞在できる環境があれば重要な機能を一定程度は維持できます。
なお、昨今ではBCPや災害備蓄を強化している企業は「危機管理能力が高い企業」として評価される機会も増えています。

企業の防災備蓄リスト 【基本編】

災害発生時に、企業が取るべき初動対応のひとつが「社内での待機と自立」です。
政府が推奨する最低3日間、できれば5〜7日間を社内で安全に過ごせる備蓄を準備しましょう。
備えるべき基本の「6つのカテゴリ」と代表的な備蓄品をまとめました。
1:【命を守る最優先備蓄】 飲料水・食料品
命を直接的に守る備蓄品は、最優先で備えましょう。
飲料水・・・1人あたり1日3Lが目安
飲料水は、1人あたり1日3リットルが目安です。
社員の人数分と日数分をかけた数量を備えます。
長期保存食・・・3日分の食事が目安
長期保存食は、最低でも3日分を備蓄します。1日に3回の食事をするので、従業員の人数分で3日分の保存食を備えると、それなりのスペースも必要です。
さらに間食類として栄養補助食品やチョコバー、飴などもあわせて備蓄しておきます。
2:【感染症や二次被害を防ぐ】 衛生用品
断水時にも衛生環境を維持できるよう、感染症対策の視点からも社内の備蓄を整える必要があります。
簡易トイレ・・・1人あたり1日5回が目安
簡易トイレ(携帯トイレ)は1人あたり1日5回を目安に計算し、最低でも3日分が必要です。
ウェットティッシュやからだ拭きシート、生理用品・・・余裕をもって備える
入浴できない環境でも衛生状態が保たれるよう、十分な量を確保します。
ビニール袋・ごみ袋・ポケットティッシュ・トイレットペーパー・・・全員が余裕を持って使える量が目安
断水が起きていてもある程度の清潔を保てるよう、全員が余裕を持って使える量を備蓄します。
3:【寒さ・暑さ・疲労から社員を守る】 防寒・防暑・休息用品
寒さや暑さから身を守るグッズや、社員が休息をとるための雑貨も必要です。
防寒グッズ・・・会社に寝泊まりすることを想定して揃える
アルミブランケットやエマージェンシーシート、毛布または寝袋など、従業員が会社で寝泊まりをする際に寒さから身を守れるグッズが便利です。
防暑グッズ・・・酷暑で停電していても暑さから身を守ることを想定して備える
停電時でも使えるよう、蓄電池と繋げられる扇風機や冷感を感じるボディシート、叩くと冷たくなる保冷グッズのほか、うちわや霧吹きなど個人で使えるグッズも十分な量を確保しましょう。
休息用品・・・会社内での寝泊まりを想定して備える
簡易マットや段ボールベッド、耳栓やアイマスクなど、社内で数日間にわたって避難生活を送る際にも休息をとりやすい環境を整えられる視点で選びましょう。
4:【情報確保と安全確保】 照明・電源関連
夜間の停電時にも避難や行動の妨げにならないよう、明かりの確保は不可欠です。
停電時でも使いやすい手回し・ソーラー式の懐中電灯やLEDランタン、複数サイズの乾電池、モバイルバッテリーやラジオを備えましょう。
5:【けが人・体調不良者への備え】 応急処置・医療用品
けが人や体調不良者のために、絆創膏、ガーゼ、包帯、消毒液などの救急セットや体温計、解熱鎮痛剤や胃腸薬などの家庭用常備薬も備えておきます。
なお、薬品類は使用期限があるため定期的な見直しが必要です。
6:【BCP視点で必要なもの】 業務を維持するための備品
災害時にも事業を継続するために、最低限の備品を備える必要があります。
筆記用具、メモ帳、クリップボードなどの簡易的なデスクセットや、指示伝達用の拡声器やメガホンのほか、インターネットが使えない状況も想定し社員名簿や連絡網も紙ベースで整えましょう。
また、従業員が使用するヘルメットや防塵マスク・手袋・防災ベストといった備品もあると安心です。
✩内閣府が企業に求めている災害・防災への意識については、過去記事の『内閣府が企業に求める災害・防災備蓄とは?備蓄品の種類や量、選定のポイントを解説』でも詳しく解説しています。

働く人の視点から見る「あると助かる備蓄品」

災害時の備蓄は「命を守る」だけでなく「不安やストレスを減らす視点」も重要です。
女性・高齢社員・外国籍社員への配慮
女性特有のニーズに対して最低限の衛生・プライバシーを守れるだけの備えがあれば、精神的な安心にもつながります。
備蓄品としては、ナプキン・タンポンといった「生理用品」、使用済みの衛生用品を廃棄するための「携帯用サニタリーバッグ」、着替えの時やトイレ時の目隠しになる「小型ポンチョ」などが挙げられます。
また、高齢の従業員や持病のある社員が安心して過ごせるような備品も求められるほか、昨今では外国籍の社員が働く企業も増えていますので、多言語対応のマニュアルやピクトグラム入りの説明書、宗教・文化に配慮した食材にも意識を向けた準備が求められています。
メンタルケアや快適性を意識した備蓄
災害時には、情報遮断や空間の閉鎖性によって多くの人に強いストレスや不安感が生じるため、できるだけ快適な空間を整えることで心理的なパニックを防ぎ冷静な行動を促せます。
空気の不快感対策になる消臭スプレーや芳香剤、味の変化と癒しにつながるキャンディやガム、インスタントコーヒーなども備蓄に加えていきましょう。

【準備をして終わりではない】 備蓄管理の実践ポイント

企業の防災備蓄は、準備をして終わりではありません。
いざというときに「使えなかった」「どこにあるかわからない」では命や信頼を守れないため、備蓄を機能させるためには管理方法も重要です。
賞味期限・使用期限の管理
非常食や水、医療用品、乾電池などの備蓄品には、期限のある物品が多く含まれます。
たとえば、保存水やアルファ米は5年〜7年の長期保存品が多いとはいえ、期限切れのまま放置されがちな点に注意しましょう。
年に1回または半期ごとの「備蓄点検日」を社内で設定し、リストに購入日と期限日を記録しておくと管理しやすいですし、備蓄品を入れ替えて使用する「ローリングストック方式」も有益です。
備蓄場所の確保と分散管理
備蓄品は、倉庫に積んでおくだけでは不十分です。
地震や火災、水害などに備えて適切な場所に分散して配置をし、迅速に取り出せる状態で保管しておきましょう。
たとえば本社だけでなく、各フロア・部署ごとに最小限の備蓄を配置する「分散備蓄」や、エレベーターの停止や通路の封鎖を想定し、階段や非常口付近にも備蓄設置を行うなどの細かな工夫が求められます。

防災備蓄のトレンドと今後の課題
企業における防災備蓄は今、従来とは異なる局面を迎えています。
トレンドと今後の課題について解説します。
備蓄品の多様化・パーソナライズ化
これまでの企業備蓄は「水・食料・毛布を人数分」などの画一的な備えが中心でした。
しかし働く人の多様化に伴って、誰にとっても安心できる備蓄が求められる時代を迎え、備蓄品も多様化・パーソナライズ化しています。
パーソナライズ化の例としては社員ごとに個人備蓄BOXを設けたり、持病や服薬に合わせた常備薬ポーチを個別配布したりといった現場ごとの「きめ細やかな対応」が導入されています。
DXを活用した備蓄管理
備蓄管理は物量が多く更新サイクルも長いために、手間とコストがかかる業務です。
そこで対策として注目を集めているのが、DX(デジタルトランスフォーメーション)による管理の効率化です。
DX化の活用例としては、備蓄品をバーコード・QRコード管理し在庫状況を一括確認できる仕組みや、賞味・使用期限が近い品をアラートで表示するよう期限管理の自動通知を設定したり、オフィスの図面上で備蓄場所・数量を可視化すべく備蓄マップをデジタル化したりといった施策がとられています。
✩『オフめしイート&ストック』の導入なら限られた予算内で「置き社食で備蓄」が実現します!
心幸が提供する『オフめしイート&ストック』は、「オフめしの常温そうざい」を利用して、“食べながら備える”を特徴とした新しい備蓄プランです。
無添加のお惣菜を真空パックにして熱殺菌処理をほどこしているため、おいしく・からだにも良く、賞味期限は製造から1年以上と長いため「おいしい備蓄品」として限られた予算を効率的に活用できます。
「置き社食で備蓄」は福利厚生にもつながり、事業者規模に応じてオーダーメイドの備蓄プランとしても利用しやすいとご好評をいただいています。ぜひお気軽に、お問い合わせください。

備蓄は“命をつなぐ準備”と“企業の信頼”の側面がある

災害時に備える企業の防災備蓄は、単なる物資のストックではありません。一人ひとりの命を守る準備を通じた「企業としての危機管理力の象徴」でもあります。
災害発生時には可能な限り混乱を抑え、安全に配慮しながら事業を継続できる環境を整備する姿勢が求められています。
今、実効性のある備蓄整備への姿勢は、将来にわたって企業が信頼されるために必要な側面とも言えるのではないでしょうか。
福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>


食べながらそなえる、新しい備蓄

オフめしイート&ストックは、賞味期限が製造から約1年あるオフめしの「常温そうざい」を利用した、普段は食べながらそなえる、新しい備蓄プランです。
オフめしEAT&STOCKはこちら