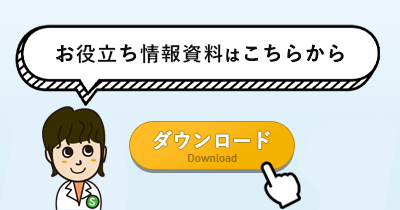健康経営の歴史
健康経営の歴史|日本での始まりから現在までの流れ
健康経営は、単なる「福利厚生」や「健康づくり」ではなく、従業員の健康を企業の成長戦略として位置づける考え方です。ここでは、その歴史を年表形式で振り返りながら、日本においてどのように発展してきたのかを解説します。
1990年代:アメリカで「ヘルシー・カンパニー」の概念が登場
健康と経営をつなぐ発想の始まり
健康経営の起源は、1990年代のアメリカにあります。
当時、従業員の医療費負担の増大が企業経営を圧迫しており、臨床心理学者ロバート・H・ローゼン博士が「ヘルシー・カンパニー思想」を提唱しました。
従業員の健康状態が企業の生産性や業績に影響を及ぼすという考え方が広まり、この発想が後の「ウェルネス経営」や日本の「健康経営」へとつながっていきます。
2000年:「健康日本21」政策のスタート
国レベルでの健康推進が始まる
2000年、厚生労働省が掲げた「健康日本21」は、国民の健康寿命を延ばすことを目的とした健康増進運動です。この取り組みにより、健康づくりの視点が「個人」から「社会全体」へと広がり、企業が従業員の健康に取り組むための土台が整いました。
2006年:NPO法人健康経営研究会の設立
「健康経営」という言葉が日本で定着
2006年にNPO法人健康経営研究会が設立され、「健康経営」という言葉が正式に使われ始めました。これにより、日本企業の健康への向き合い方が、法令遵守中心から戦略的な経営課題へと転換。企業・医療・行政の連携を通じ、健康経営の普及と実践が進みました。
2013年:「日本再興戦略」で健康経営が国策に
経済政策の一環としての「健康」
2013年に政府が発表した「日本再興戦略」では、「国民の健康寿命延伸」が明記され、健康経営が国家戦略の一部となりました。経済産業省が主導する「企業の健康投資」という概念が注目を集め、健康経営が経済政策としても位置づけられるようになります。
2014年:「健康経営銘柄」制度のスタート
上場企業を対象とした顕彰制度
経済産業省と東京証券取引所が共同で、健康経営に優れた企業を選定する「健康経営銘柄」制度を創設しました。
投資家からも注目され、健康経営が“企業価値”の一部として評価されるようになりました。
2016年:「健康経営優良法人認定制度」の創設
中小企業にも広がる健康経営
2016年には、「健康経営優良法人認定制度」が創設され、中小企業を含めた幅広い企業が健康経営に取り組むようになりました。
大規模法人部門と中小規模法人部門の2区分で顕彰が行われ、健康経営が大企業の取り組みから全国的な経営スタンダードへと発展しました。
2017年:「未来投資戦略2017」とSociety5.0の連動
デジタル技術による健康経営の進化
政府の「未来投資戦略2017」では、「Society 5.0」の実現に向け、テクノロジーを活用した健康づくりの推進が示されました。
AIやIoTを活用して従業員の健康データを可視化し、ウェアラブルデバイスやアプリによる個別支援など、“健康経営×DX”という新たな取り組みが進みました。
2020年~現在:「健康投資」の時代へ
経営指標としての健康経営
2020年、経済産業省が「健康投資管理会計ガイドライン」を公表。
健康経営を“費用”ではなく“投資”として評価する動きが強まりました。
2025年3月には、約10年ぶりに「健康経営ガイドブック」が改訂され、健康投資の考え方や実践手順がより明確に整理されています。
これにより、企業の健康経営は“戦略的経営”の一環として深化しつつあります。
まとめ|健康経営は「企業文化」へ
健康経営は、政策や制度の枠を超えて、今や企業文化そのものとして定着しつつあります。
働く人の健康を支えることが、企業の未来を強くする。
これこそが、健康経営の歴史が示す最大のメッセージです。