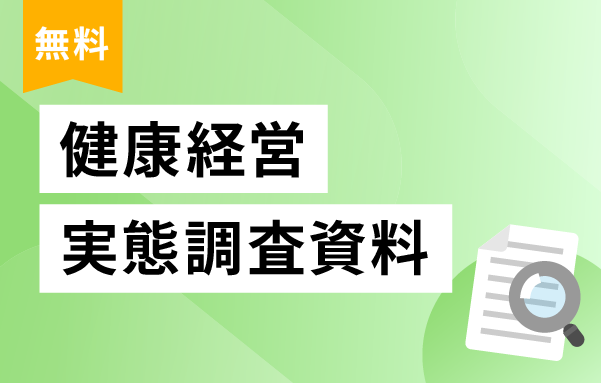健康経営はどのように導入されている?企業の取り組み事例や導入ポイントなどを解説

こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。
従業員の健康への投資を実践する「健康経営」は、労働環境の変化や時代の流れに伴って業種を問わずすべての企業に求められる取り組みです。国が推進していることもあり、現在では健康経営を実施している企業が見える化されており、企業イメージにも影響を与える要素となっています。
では、実際に健康経営を導入している企業ではどのような取り組みが行われているのでしょうか。本記事では、健康経営を行う企業の取り組み事例とともに、健康経営の基本や期待できる効果、時代に即した導入ポイントなどを解説します。
福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉
目次
健康経営の基本

健康経営とは、「従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること」と経済産業省で定義されており、日本再興戦略、未来投資戦略に位置づけられた「国民の健康寿命の延伸」に関する取り組みのひとつに挙げられています。
健康経営は企業が従業員の健康管理や健康増進への取り組みを積極的に実施することで、従業員の活力や生産性向上、医療費削減などの効果に加えて、業績向上につながる経営戦略です。つまり、企業による従業員の健康への投資が、組織の活性化を図れる方法となるというわけです。
参考/経済産業省「健康経営」
健康経営が重要視されている理由
健康経営は近年、企業規模を問わず多くの企業で重要視されており、導入が進められています。なぜ健康経営が重要視されているのか、その理由のひとつは、労働人口の減少です。
少子高齢化に伴い、働く世代は減少しています。従業員の心身の状態の悪化で休職や離職となると、ますます人手不足が深刻となり、周囲の従業員への負担が重くなり健康状態が悪化する悪循環に陥る恐れがあるため、人手不足の中でも円滑に業務を進めるには健康経営で従業員の健康に投資することが重要なのです。
もうひとつの理由は、国が健康経営を推進していることです。日本は少子高齢化に伴い、労働人口が減少傾向にあります。健康寿命を延ばすことで生涯現役社会を実現して社会保障費用削減につなげるために、厚生労働省では国民の健康寿命の延伸、経済産業省では健康経営を経営戦略のひとつとして位置付け、健康経営に取り組む銘柄選定や企業の認定を行っています。
このような背景から、現在健康経営は多くの企業で導入されているのです。
参考/厚生労働省「日本再興戦略」
内閣官房「未来投資戦略 2018」
ACTION!健康経営「健康経営とは」

健康経営に期待できる主な効果

健康経営を導入することには、企業にとってプラスとなるさまざまな効果が期待できます。主な良い効果として、以下の3点が挙げられます。
組織の活性化
健康経営は、従業員の心身ともに健康状態の維持・改善や健康意識向上が期待できる施策です。健康状態が良好になれば、一人ひとりの従業員がいきいきと働くことができるようになります。従業員の業務遂行能力やパフォーマンスの向上も期待でき、そこから業績向上につながって組織全体が活性化する効果も期待できます。
付随して、従業員同士のコミュニケーションが活発化して部署を超えた協力体制の構築、業務に対する意欲が高まることによって従業員のモチベーションが上がることで新たなアイデアやイノベーションのきっかけとなることも望めます。
組織が活性化することで企業価値や信用性、企業イメージがアップし、さらに従業員が意欲的に働ける環境が整う好循環が生まれるでしょう。
ワークエンゲージメントの向上
健康経営は、従業員の企業に対する信頼性を高める効果が期待できます。健康経営を実践して従業員の健康を考えていることが明確に示せると、「会社は従業員のことを大切にしている」というポジティブな印象を持つことで、ワークエンゲージメントの向上が図れます。
前述の組織の活性化と共通しますが、職場への信頼を得ることで従業員のワークエンゲージメントが向上すると、仕事に対する意欲がアップし、生産性や定着率向上効果が得られるでしょう。
企業のイメージアップ
健康経営を導入・実施している企業は、その旨を広くアピールできます。健康経営優良法人として認定されている企業は、健康経営を推進するポータルサイト「ACTION!健康経営」の認定法人一覧に掲載されるため、健康経営を実施しているかどうかは誰でも簡単にチェックできるのです。
健康経営の実施有無は、対外的なイメージに大きく関わります。健康経営を実施して従業員の健康を守る取り組みを積極的に行っていることは、社外へポジティブな印象を与えることができるでしょう。
健康経営を実施している企業の方が、「従業員を大切にする会社」という良い印象が強くなります。求職者、新卒者の応募先に同条件の企業があった場合、健康経営を行っている企業は労働環境が良いと判断できることから、求職者や新卒者に選ばれやすくなる効果が期待できます。したがって、健康経営を行うことで企業は優秀な人材確保も望めるでしょう。
金融機関においても、健康経営を行っている企業は評価が高まります。実際に、一部の金融機関では健康経営に取り組み認定を受けた企業を対象とした融資を行っているところもあるほどです。
このように、健康経営は社外へのイメージアップにつながり、会社経営に関わる良い効果が期待できます。
参考/ACTION!健康経営「認定法人一覧」
北日本銀行「健康経営融資」

大企業における健康経営の取り組み事例企業
健康経営は、すでに大企業では導入が進んでおり、健康経営を推進する体制も各企業で異なる取り組みが行われています。そこで、健康経営優良法人に認定されている企業での取り組み事例をご紹介します。
ウェルビーイングと健康経営の違い|成功事例や取り組みを一挙紹介
キリンホールディングス株式会社

キリンホールディングス株式会社では、2017年に「キリン健康宣言」を発信し、健康経営を人財戦略の基盤に位置づけています。
健康投資からその効果、重要目標達成指標(KGI)や目標に至るまでの健康経営戦略マップを公表しており、同社は会員企業数500を超える業界の垣根を超えた組織「健康経営アライアンス」の代表幹事も担っています。
キリンホールディングスでの具体的な健康経営の取り組みは、睡眠セミナーや女性特有の健康課題に関するセミナー、適正飲酒チャレンジやオンライン禁煙プログラムの提供、メンタルヘルスへの理解を深めるeラーニングやリーダー対象のラインケア研修などがあります。
また、健保との連携で生活習慣病予防を目的とした重点領域の設定や歯科疾患対策なども行うなどの取り組みも行っています。
明治安田生命保険相互会社
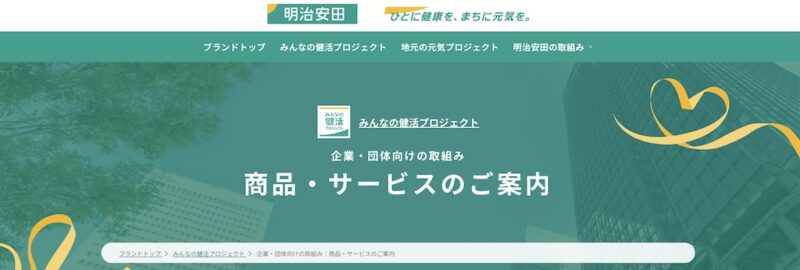
明治安田生命保険相互会社では、働き方改革を通じた「働きがい」と「働きやすさ」のある職場づくりを追求することを目的として、以下の3つの取り組みを行っています。
・健康管理体制の充実:健康診断と再検査の完全実施、職場環境の整備、ストレスチェックの結果を踏まえた産業医との面談実施など
・健康増進:専用アプリを活用したウォーキングコンテストの実施、勤務時間中のストレッチタイム設定などで運動習慣の定着を図る取り組み
・安全・快適な職場環境づくり:検温・消毒の実施などの感染症予防対策、勤務場所、時間の自由化など
同社では健康経営推進委員会を設置し、経営会議へ報告する体制を構築し、PDCAサイクルを回ることで定期的な健康経営の見直し・改善を図っています。
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

「多様性ある個々人の心身の健康が挑戦と成長の土台」という考えの元、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社では健康経営最高責任者として代表取締役執行役員社長をトップとした健康経営推進体制を取っています。
社内の健康経営の旗振り役として健康経営推進室を設置し、産業医や産業保健スタッフなどの健康経営チーム、健康保険組合やヘルスケアサービスを提供するグループ会社と連携して健康経営の実行や効果検証、改善などを行っているのが特徴です。
具体的な取り組みとして、健康診断の受診促進や人間ドック・オプション検査の費用補助、グループ会社のヘルスケアアプリの無償提供、休暇制度の充実などがあります。
参考/ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社「健康経営」
ANAホールディングス株式会社

ANAホールディングス株式会社では2016年4月に「ANAグループ健康経営」を宣言し、従業員の健康管理やメンタルヘルス、安全衛生活動強化に加えて生活習慣病の指標を定めて取り組みを進めています。
グループ全体の健康経営推進責任者は、チーフウェルネスオフィサー(CWO)としてANAホールディングス役員が務めています。グループ各社のウェルネスオフィサーやウェルネスリーダーが密に連携してグループ合同経営戦略会議や取締役会に審議・報告を行い、社員の健康状況把握と健康増進施策を進める体制を整えています。
また、同社ではグループ社員の健康管理を担うANA健康管理センターに加えて日本全国8ヶ所に健康管理室と健康管理センターを設置し、がんや女性特有の疾病、生活習慣病予防やメンタルヘルス、安全衛生活動に関わるさまざまな取り組みを行っています。
健康に関するイベントやセミナー開催や社員教育を含めて取り組むことで、ANAホールディングス株式会社では健康状態の改善が堅調に推移しているとのことです。

ユニークな健康経営の取り組み事例
健康経営が多数の企業に導入されている昨今、大手企業のみならず中小企業などでも健康経営の導入は進められており、中には他の企業にはないユニークな取り組みを行っている企業もあります。
独自の禁煙方式「禁煙バトン」
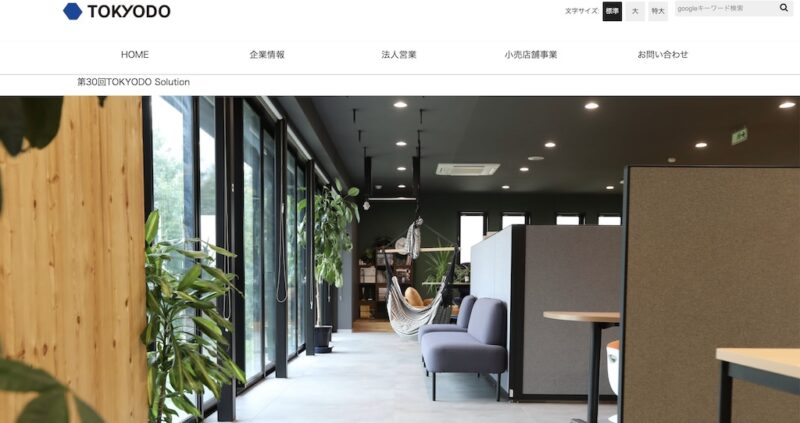
健康経営優良法人に認定されている青森県の株式会社東京堂は、従業員ががんに罹患したことをきっかけに2015年から健康経営に取り組んでいる企業です。
同社では、ワークライフバランスを実現する100通りものシフト制定やトレーニングルーム設置・イベント参加などを通した運動促進、健康診断の受診推奨など多彩な健康づくりのための取り組みを行っていますが、その中でもユニークな取り組みが「禁煙バトン」です。
禁煙バトンとは、喫煙率が高いという青森県の地域性を考慮し、文字通りバトンを持った人が禁煙に成功したら次の人へバトンを渡すというリレー方式の禁煙対策です。受動喫煙対策の取り組みとしても行われており、過去にバトンを渡された人は全員禁煙に成功した実績もあるとのことです。
参考/株式会社東京堂「環境・社会活動」
経済産業省「健康経営優良法人取り組み事例集」
3時間の昼休みを取れる「シエスタ制度」

大阪府のITコンサルティング会社株式会社ヒューゴでは、毎日昼に3時間自由に過ごせるシエスタ制度を導入しています。元々「シエスタ」とはスペインなどの南ヨーロッパで行われている午後の長い休みのことです。
同社では、午後1時から4時までをシエスタの時間として眠くなりやすい午後の時間をリフレッシュに使うことで業績向上を図っています。3時間を休みとした場合に退勤時間が遅くなるため、早く帰宅したい場合はシエスタ制度を利用する必要はなく、自由な勤務時間や場所で働けるテレワークも推奨しています。
参考/日本経済新聞「昼に「シエスタ」毎日3時間 ITコンサルのヒューゴ」
体を動かせる器具の設置・トレーナーの指導を受けられる「健康サポート」

東京都のシステム開発・コンサルティング会社株式会社ヒトメディアは、デスクワークが多い業務の特性から、立ったままデスクワークができるスタンディングデスクを導入し、長時間座りっぱなしが多いデスクワークによる体への負担を軽減する取り組みを実施しています。
さらに、デスクワークが多く体を動かす機会が減ることを防ぐためにストレッチ器具を導入したり、週2回トレーナーを社内に招いて運動やストレッチなどの指導を受けられるトレーナー指導制度を導入したりしているのも同社で実施されている取り組みの特徴です。
デザイナーやエンジニアのように長時間デスクワークが続く企業ならではのこれらの健康サポートは、他社にはあまり見られないユニークな取り組みとしてメディアにも取り上げられています。
参考/株式会社ヒトメディア「社員の健康サポートに関する取り組みが日本テレビ「news every.」で紹介されました」

時代に即した健康経営を導入するポイント

技術革新や働き方の多様化などは、時代の流れとともに企業や労働者を取り巻く環境にも影響を与えています。現在の時代に合った健康経営に取り組むには、主に以下に挙げる2つのポイントを押さえて実施してみましょう。
デジタルツールの活用
健康経営は、企業が独自の取り組みを導入して実施されていますが、効率的な健康経営の実現に高い効果が期待できるのが、スマートフォンやウェアラブルデバイスなどのデジタルツールの活用です。
特に、ほとんどの人が持っているスマートフォンを活用したサービスを健康経営の一環として実施している企業は多くあります。従業員数50名以上の事業場で義務化され、50名未満の事業場にも将来的に義務化される予定のストレスチェックも、スマホアプリで効率的に実施が可能です。
健康経営を支援するさまざまなサービスを利用できる健康管理システムには、専用スマホアプリを活用できるタイプもあります。アプリの直感的な操作で従業員一人ひとりが手軽に健康管理をできるようになり、企業側ではそれらのデータを一元管理して分析・可視化することで健康状態の把握や改善策の提案などが容易にできるなど、デジタルツールは健康経営を効率的に進められる利便性の高いツールといえるでしょう。
リモートワークへの対応
働き方改革や感染症流行を機に、これまで一般的だったオフィスでの勤務だけではない、多様な働き方を導入する企業は一昔よりも格段に増えています。
感染症予防策のひとつとしてリモートワークの導入が推奨され、場所にとらわれない働き方も実現しています。感染流行が収まったタイミングで出社に戻す企業もありますが、現在も引き続きリモートワークでの勤務を続けている企業は少なくないでしょう。
オフィスに勤務せずに働けるリモートワークは、ワークライフバランスの向上に一役買う方法である一方で、企業側としては従業員の健康管理が難しくなるという問題も孕んでいます。そのため、時代に即した健康経営を実施するには、テレワークで働く従業員への対応も考慮する必要があります。
リモートワークで働く従業員の体調の把握は、オフィスで働く場合よりも難しく、勤怠管理の正確な把握も困難です。また、自宅など外部での勤務は、オフィスのようにデスクやパソコンなどの機器が揃った労働環境が整っていないことも考えられるでしょう。労働安全規則に沿わない環境である可能性もあり、しかも一人ひとりの労働環境が大きく異なることもあり得ます。そもそも通勤の必要がない場合が多いため、運動不足に陥るケースも増えるでしょう。
リモートワークを導入している企業で健康管理を実施するには、ストレスチェックや産業医との面談などができる健康管理システムなどのデジタルツール活用が推奨されます。労働時間の把握についても、クラウド型の勤怠管理システムを導入すれば、遠隔でも記録が確認できます。加えて、企業の人事労務担当者などと遠隔でもコミュニケーションを取れる環境づくりも必要です。
日常的に顔を合わせていない場合でも、オンラインで常にコミュニケーションが取れる環境があれば、業務はもとより健康管理に関する情報共有もスムーズに進められるでしょう。

企業で健康経営を導入するなら「オフけん」で

今では多数の企業が導入している健康経営ですが、一から自社に導入をするのは難しい、というイメージがあるかもしれません。しかし、前述したように健康管理を一元化できるシステムを利用すれば、さまざまな健康管理サービスを使用できます。
心幸グループが提供している健康経営プログラム「オフけん」は、企業の課題や悩みを解決するオーダーメイドプランの提供をはじめとして、従業員が楽しんで利用できるサービスを通した健康経営を実現します。専用アプリ「オフけん体調管理アプリ」は従業員の体調管理のほか、ストレスチェックやオンライン診療まで利用できるのもメリットで、リモートワークを導入している企業でも効率的に健康経営を進められるでしょう。
オフけんは、健康経営優良法人認定取得のための申請手続きサポートも行っています。自社に合わせた健康経営を導入したい企業、健康経営優良法人認定を視野に健康経営を実施している企業におすすめのプログラムです。
まとめ
大企業から中小企業まで、現在は非常に多くの企業が健康経営を実施しています。少子高齢化による労働人口が減少傾向にある中、国が推進している健康経営の認定制度もあることから、健康経営の実施有無はすでに「見える化」されています。健康経営は、自社の従業員のモチベーションを上げることによる生産性やワークエンゲージメントの向上や組織の活性化とともに、企業のイメージアップにも大きな影響を及ぼす取り組みとなるでしょう。
健康経営の実施は、自社の環境や従業員の健康状態などによって適した取り組みは異なります。すでに健康経営を導入している企業では、それぞれ自社に最適な取り組みや仕組みを構築して実践しています。また、健康経営は時代の変化とともに増加する多様な働き方への対応も必要です。
企業や業務内容によってはリモートワークの従業員が多いこともあるため、今後の健康経営は最新技術を活かしたデジタルツールなどを活用し、多様な働き方に対応することも求められるでしょう。
福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>