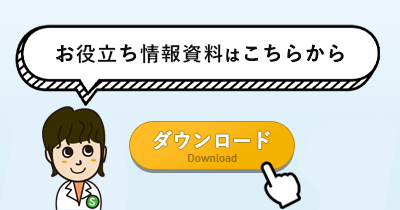厚生年金保険の標準報酬月額上限が引き上げに?保険料の計算方法や引き上げの影響、企業ができる対策を解説

こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。
会社員や公務員として働く人、一部のパートやアルバイトで働く人が支払っている厚生年金保険料が、2027年から変更となることはご存知でしょうか。2025年6月に年金制度改正法案が可決・成立したことにより、2027年9月から厚生年金保険料を計算する基本となる標準報酬月額の上限が引き上げとなることが決定されたことが、その要因です。あまり大きな影響を受けない人も多いですが、所得が多い人にとっては収入に関わる改正となる可能性があります。
厚生年金保険の標準報酬月額の上限が引き上がると、どのような影響が予想されるのでしょうか。本記事では、厚生年金の基本や保険料の計算方法とともに、標準報酬月額の上限引き上げに対して企業ができる対策について解説します。
福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉
目次
厚生年金とは

厚生年金とは、厚生年金の適用対象となる企業に勤めている70歳未満の従業員や公務員が加入する公的年金の一つです。企業や官公庁などに勤務している人すべてが厚生年金加入の対象というわけではなく、基本的に1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上を満たす70歳未満の従業員が、加入対象です。働き方によって、一部のパートやアルバイト勤務の人は対象外になることもあります。
日本の年金制度は、大きく分けてこの厚生年金と国民年金の2種類があります。国民年金は20歳以上60歳未満の国民すべてが加入する、年金制度の基礎となるものです。つまり厚生年金に加入している人も、国民年金に加入しているということになります。なぜなら、年金制度は国民年金をベースとした制度だからです。
年金制度は、国民年金をベースとして厚生年金で2階建て、個人型確定拠出年金や厚生年金基金などで3階建ての構造となっているため、国民年金は「基礎年金」とも呼ばれています。厚生年金に加入しているということは、国民年金を基礎としてプラスアルファの年金保険料が上乗せされていることとなります。
厚生年金は、勤務先と加入者で半分ずつ同額の保険料を負担する「労使折半」です。全額を個人が負担する国民年金よりも負担が少なく、しかも保険料が国民年金に上乗せされているため、将来受け取れる年金受給額は国民年金よりも増えます。個人型確定拠出年金などに加入している場合もさらに上乗せとなるので、国民年金や厚生年金よりも将来受け取れる年金の額が増えます。

厚生年金保険料を計算する方法

国民年金の場合は、収入にかかわらず支払う保険料は一律です。一方、厚生年金は所得に応じた額を支払う点が国民年金との大きな違いです。厚生年金保険料を計算するには、まず標準報酬月額を知る必要があります。
標準報酬月額とは、毎月の給与などの額を分類したもので、後述する標準報酬月額の等級を定める際に用いられます。標準報酬月額の算出には給与や賞与に加えて、家族手当や住宅手当などの各種手当などを含んだ額が含まれますが、単純に12ヶ月分すべての給与が算出対象になるわけではありません。
標準報酬月額の算出には、毎年4~6月の給与が用いられます。この3ヶ月間の給与や手当などの平均額が、標準報酬月額として毎年7月に算出されます。この額を標準報酬月額の等級に当てはめて18.3%をかけた額が、厚生年金保険料です。
標準報酬月額の等級とは
標準報酬月額の等級とは標準報酬月額を等級に分けて表したもので、厚生年金保険料を計算する際の基本となります。給与が高いほど等級は高くなり、現在、厚生年金の標準報酬月額は標準報酬9万8,000円の1等級から65万円にあたる32等級まであります。
標準報酬月額の上限が引き上がるということは、一人ひとりが支払う厚生年金保険料も引き上げられることとなります。2027年から標準報酬月額の上限は毎年段階的に引き上げが予定されており、最終的に2029年までに上限が75万円に引き上げられます。
また、2027年以降は標準報酬月額の上限が引き上げされると同時に等級も新設され、こちらも段階的に新設される予定です。
参考/厚生労働省「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて」
厚生労働省「標準報酬月額等級表(厚生年金)」

厚生年金の上限引き上げで何が変わる?
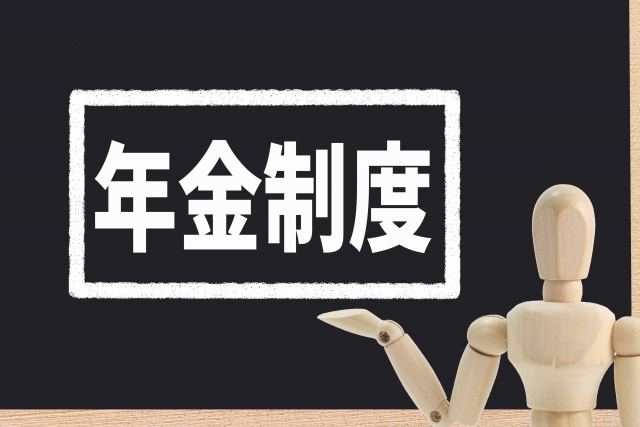
2025年6月に年金制度改正法案が可決・成立し、厚生年金の標準報酬月額の引き上げが決定しました。標準報酬月額が改定されて厚生年金の上限が引き上げられると、当然ながら厚生年金保険料が上がり、企業と従業員双方の負担が増えます。所得を元に算定される標準報酬月額の上限が引き上がるということは、等級が低い人にはさほど大きな影響は見込まれないものの、所得が多い人にとっては変化が大きく、これまでよりも保険料の負担が増えることが予想されます。
標準報酬月額の引き上げは、企業と従業員双方に負担が増える可能性があることから、デメリットばかりという印象が大きいかもしれません。しかし、標準報酬月額の上限が引き上がることで、を基準とする傷病手当金や出産手当金の支給額も増加することが考えられます。
標準報酬月額の上限引き上げとなる理由と背景
厚生年金の標準報酬月額上限が引き上げとなる理由は、上限に達している人の割合が多いことと再分配機能機能の強化、そして公的年金制度持続のためです。
そもそも、標準報酬月額はすべての被保険者の平均標準報酬月額の約2倍に設定されており、現在の上限である65万円がその額にあたります。これは、厚生年金保険料の半分を負担する企業の負担を考慮し、かつ年金給付額に大きな差をつけないために設定されています。所得に応じた保険料を負担することにより、将来的に現役世代の収入に見合った年金が受け取れるようになるというわけです。
平均標準報酬月額が上限を超える場合、政令によって新たな等級の追加が可能となっています。過去にも標準報酬月額の改正が行われており、2020年の改正では32等級が新設されて現在の標準報酬月額の上限である上限に引き上げられました。
そして今回、賃金が上昇傾向にあり平均標準報酬月額が65万円を超える状況が続いたことから、再び標準報酬月額の引き上げが予定されています。
厚生労働省が公表している令和5年の標準報酬月額別の被保険者数分布割合によると、被保険者全体で現在の上限である標準報酬月額65万円に達している人の割合は、令和5年7月の段階で6.3%を占めています。男性に限って見ると、標準報酬月額が上限に達している人は全等級の中で最も多い9.2%を占めています。
標準報酬月額が上限の65万円に達している人は現状、それ以上厚生年金保険料が上がることがありません。所得が上限以上の額に増えていたとしても標準報酬月額65万円以上の厚生年金保険料は一律であるため、他の等級の支払い能力と比較して所得に対する厚生年金保険料の負担が少ないと考えられます。
そこで、高所得者に対して収入に応じた保険料負担を実現するために、上限の引き上げが行われます。これにより、高所得者が従来よりも多い厚生年金保険料を負担することで、収入が少ない人に対しても安定的に年金を支給できる再分配機能の強化が見込まれます。さらに、標準報酬月額の上限を引き上げて高所得者がより多い厚生年金保険料を支払うことによって保険料収入が増えることから、公的年金制度の持続にも大きな働きが期待できます。
参考/厚生労働省「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて」
厚生労働省「標準報酬月額の上限」
標準報酬月額の引き上げ時期とスケジュール
前述したように、標準報酬月額の引き上げは一度に行われるのではなく、2027年から2029年にかけて段階的に行われます。現時点では、2年間にわたり以下のスケジュールで3段階に分けて、標準報酬月額の引き上げと等級の新設が行われる予定です。
・2027年9月:標準報酬月額上限を68万円に引き上げ、33等級の新設
・2028年9月:標準報酬月額上限を71万円に引き上げ、34等級の新設
・2029年9月:標準報酬月額上限を75万円に引き上げ、35等級の新設
この引き上げで、現在の標準報酬月額65万円の場合と比較してどの程度厚生年金保険料が増えるのか、2029年に改正が予定されている標準報酬月額75万円以上の所得がある場合を例に挙げてみましょう。
引き上げの1段階目で上限が68万円に上がると、厚生年金保険料は1ヶ月あたり2,745円、年間3万2,940円の増加が予想されます。2段階目は1段階目と同じ引き上げ幅なので、1段階目と同じ額の負担がさらに加わり、最終的に2029年9月の3段階目の引き上げでは2段階目よりも1ヶ月あたり3660円、年間4万3,290円の厚生年金保険料増加となります。
現在32等級の人はこの先給与額に変更がなかったとしても、今後の全3段階の上限引き上げで徐々に負担額が増加し、2029年の3段階目の改正後には1ヶ月あたり9,150円、年間10万9,800円もの負担増となります。
標準報酬月額の上限引き上げによって増える厚生年金保険料は、企業が負担する額と同額です。つまり、高所得者を抱える企業では従業員1人あたりこれだけの負担が増えてしまうのです。高所得者が多い企業では、厚生年金保険料だけでかなりの負担増となるでしょう。

厚生年金の標準報酬月額引き上げによって考えられる企業への影響
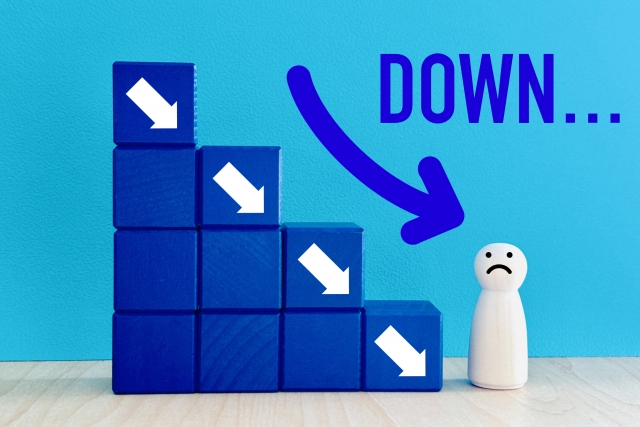
厚生年金保険料は企業が半分を負担するため、標準報酬月額の引き上げは企業にとって影響が少なくありません。従業員にかかるコストに加えて、厚生年金保険料の変更に付随する事務作業が発生するなど、さまざまな影響が予想されます。
高所得者の社会保険料負担の増加
標準報酬月額の上限が引き上げられると、上限に達していた高所得者の厚生年金保険料負担が増えます。厚生年金保険料は、勤務先企業と従業員が半分ずつ負担するものです。そのため、標準報酬月額が引き上げとなった場合、企業が負担する保険料も同程度増加することとなるのです。
標準報酬月額の上限が引き上げられると、所得が多い従業員を多く抱える企業では社会保険料負担が増加します。上限が65万円から75万円に引き上げになった場合、上限に達している従業員が100人いる企業では、1ヶ月あたりおよそ70万円の保険料負担増が見込まれるため、企業への負担が大きくなることが懸念されます。
人材確保や雇用戦略の見直し
上記のように、標準報酬月額の上限が引き上げられると、高所得者が多い企業ほど厚生年金保険料の負担が増大します。人材雇用にかかるコストが引き上げられることとなるため、中長期的な人材確保や採用計画などの雇用戦略、昇給制度などの見直しが必要となることが考えられるでしょう。
人材採用・獲得コストがかかることから、人材確保そのものが難しくなる可能性もあります。人材を確保するために、給与体系の見直しも必要となる可能性がある点が、標準報酬月額の上限引き上げが企業へ与える大きな影響の一つです。
従業員の事務負担増加
標準報酬月額の上限引き上げは、企業の事務負担にも大きな影響を及ぼす可能性があります。給与システムを利用している企業では、標準報酬月額の引き上げに付随する給与システムの改修やアップデート、給与明細の様式変更などの作業が必要となります。しかも、引き上げは3段階に分けられているため、引き上げが行われるたびに事務作業を行う必要も出てくるでしょう。
また、従業員に対して厚生年金保険料の引き上げに関する説明の実施が求められます。手取りが減少することとなるため、問い合わせに対する対応が発生することもあります。さらに、変更が生じる可能性がある就業規則や給与規定の改定などの事務負担もかかってしまいます。
このように、標準報酬月額の上限引き上げは従業員の手取りが減少するだけではなく、事務負担の増加につながることが予想されます。そして、事務負担の増加は企業の事務コスト増加にもつながるため、人事戦略の見直しも必要となるでしょう。
離職率の増加
厚生年金保険料の負担が増えるということは、後述するように従業員の手取り収入が減少する要因となります。
企業で働く高所得者は一般的に経験やスキルが豊富で、それに見合った収入を得ています。厚生年金保険料の負担増加によって手取りが減少している中で、もっと良い条件を提示してもらえる競合他社があった場合、収入を増やすために離職する可能性が高まります。同じ働き方でも、手厚い福利厚生を提示してくれるなど好条件で働ける企業があった場合、優秀な人材の離職リスクが高まるでしょう。
自社で給与を減らしているわけではないものの、従業員にとっては厚生年金保険料の引き上げで手取りが減ってしまうと、勤務先企業への不満にもつながる可能性があることは、企業にとって悪い影響となり得ます。今回の年金制度改正は高所得者への影響が大きいため、経験豊富で優れたスキルを持つ高所得者の離職が増加して人材流出すると、企業にとって大きな損失となるでしょう。

厚生年金の標準報酬月額引き上げによって考えられる従業員への影響
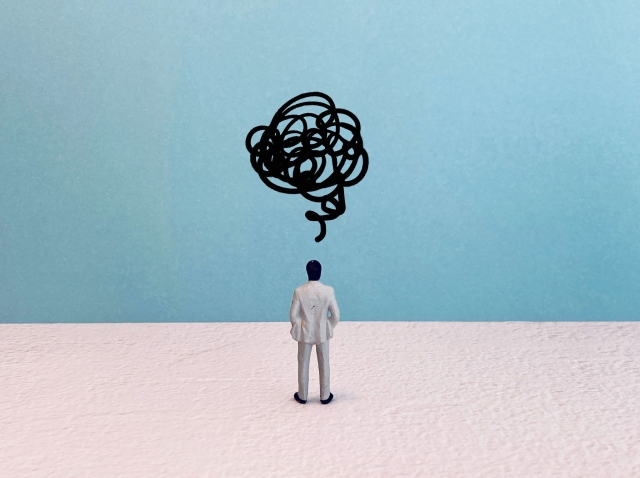
厚生年金の標準報酬月額引き上げは、企業で働く従業員へも影響を及ぼします。主な影響として考えられるのが、以下の2点です。
手取り額の減少
標準報酬月額が上限をはるかに超える所得が高い人は、これまでは最も高い32等級に該当しており、それ以上厚生年金保険料が上がることはありませんでした。今後の改正後も、上限を超える所得を得ている場合はこの仕組みに変更はありません。しかし、上限が上がることによって上限に達していた人の厚生年金保険料は増加します。よって、特に高所得者は厚生年金の標準報酬月額上限の引き上げの影響が大きくなるでしょう。
標準報酬月額の上限引き上げ前と所得額が変わらないとしても、厚生年金保険料の負担が大きくなるため、従来の制度と比較すると当然ながら従業員の手取り額が減少することが予想されます。3段階に分けて標準報酬月額の上限が引き上げられるとともに、高所得者の手取り額も段階的に減少するでしょう。
厚生年金保険料の負担が増える分、社会保険料控除によって住民税や所得税の負担が減り、将来受け取れる厚生年金額も増えるメリットはあります。しかし、手取りが減る方が従業員にとっては大きな影響として捉えられてしまうでしょう。
モチベーションの低下
手取り額が減少すると、従業員のモチベーション低下が懸念されます。厚生年金保険料は所得額に応じた額を負担することとなるため、仕事内容や仕事量が変わらないにもかかわらず手取りが減ると、労働に対する対価が減ったと感じ、従業員のモチベーション低下につながる可能性があるでしょう。企業によっては、標準報酬月額の引き上げに備えた事務負担が増加することから、仕事量が増えている一方で手取り額が下がる事態になることも考えられます。
収入の減少は、日々の生活だけではなく将来設計にも大きく関わるものです。今回の標準報酬月額の上限引き上げは高所得者に影響が大きいので、収入が減ることを防ぐためにもっと良い条件の会社で働いてを得たいという考えから、離職者を生むことにつながることもあり得ます。

厚生年金の標準報酬月額上限引き上げに対して企業ができる対策

標準報酬月額の上限引き上げは、働く従業員の収入に関わる重要な問題です。優秀な人材が多い高所得者にとってはより影響が大きい改正となるため、収入減少を理由として離職する事態も起こり得ます。
そのような悪影響を防ぐために企業ができることとして、以下のような対策があります。
給与体系や手当の調整
給与額が変わらない状態で厚生年金の標準報酬月額の引き上げが行われると、引き上げ前よりも手取り額が下がることは明白です。手取り額の減少は、従業員のモチベーション低下や離職率増加につながる要因となりかねません。このような問題を避けるには、企業側で給与体系や手当を見直し、標準報酬月額を算出する際の要素を調整する必要が出てきます。
給与や手当が上がると、その分標準報酬月額とともに厚生年金保険料も上がります。厚生年金保険料の負担を軽減するための対策として、給与や手当を調整して基本給を下げることによって標準報酬月額を下げる方法があります。
もちろん、単純に給与や手当を減らしてしまうと、従業員は待遇が悪化したと感じてしまいます。そこで賞与の比率を上げたりインセンティブを導入したりすることが、標準報酬月額を抑えるのが一つの方法となるでしょう。また、社会保険料がかからない退職金に給与を振り分ける方法もあります。残業が多い場合は、標準報酬月額の算定対象となる4~6月中の残業時間を抑えることも、厚生年金保険料の軽減につなげられます。
ただし、これらの給与や手当に関わる調整を行うには従業員本人の理解を得ることが必須です。実際に給与体系や手当を調整する前に、従業員に対して十分な説明が求められます。
フレキシブルな働き方の導入
働き方改革の一環として、在宅勤務や時短勤務などフレキシブルな働き方を実現できる制度を導入することも、厚生年金保険料の負担軽減策となります。労働時間を短縮することで標準報酬月額を抑えられるので、企業の厚生年金保険料負担の軽減につなげられます。同時に、フレキシブルな働き方ができれば従業員の働き過ぎを防ぐこともできるので、ワークライフバランスの向上や従業員の健康維持にも良い効果が期待できるでしょう。
人材雇用に関わるポイントとしては、業務委託のフリーランス人材を活用するのも一つの方法です。業務委託で働くフリーランスは会社員という扱いではないので、特定の企業に業務を依頼されていたとしても依頼元企業の社会保険に加入することはできず、企業も社会保険料を負担する必要がありません。
業務に対応するための人材募集をしたいけれど社会保険料の負担が大きい場合は、業務委託契約でフリーランスを活用してみましょう。業務に必要なスキルや労働力を確保できるとともに、従業員にかかる厚生年金保険料をはじめとして健康保険料なども含めた社会保険料を削減できるメリットが期待できます。
確定拠出年金の導入
確定拠出年金とは、個人や企業が積み立てた資産を運用する制度です。確定拠出年金には個人が積み立てる、「iDeCo」と呼ばれる「個人型」、企業が従業員の年金口座に積み立てる「企業型」の2種類があります。
企業型確定拠出年金では、企業が従業員の年金口座に拠出するお金は給与とみなされず、掛金と運用益は非課税となります。つまり、確定拠出年金への積み立てで標準報酬月額を低くして従業員の所得を抑えることで、厚生年金保険料を抑えることができるのです。 確定拠出年金は、将来的に一時金として受け取る際は退職所得控除の対象となる点、将来の資産形成となる点が、従業員にとってもメリットとなります。
福利厚生の活用
標準報酬月額の引き上げが行われると、従業員の手取り額が減少する恐れがあります。給与を上げてしまうと、その分標準報酬月額の等級も上がり、結果的に厚生年金保険料も上がってしまいます。
給与体系や手当を調整することを対策として述べましたが、厚生年金保険料を軽減する目的のみで意図的に給与や手当を調整することは不適切と捉えられることもあります。法令を遵守しつつ、手取り額が減ることによる従業員の不満を解消するためには、全額経費として計上でき、企業が自由に導入できる法定外福利厚生の活用が有効な手段の一つです。法定外福利厚生は、自社で制度を行うほか、福利厚生サービスを利用する方法があります。
非課税となる福利厚生を導入すれば、手取りが減少した分の補填が可能です。厚生年金の標準報酬月額上限の引き上げに伴う手取り額減少対策としては、食事補助や住宅手当など、従業員の生活に直結する福利厚生が有効です。福利厚生の充実は従業員の満足度向上とともにモチベーション維持に寄与するので、離職率を抑える効果も期待できます。
企業側としても、福利厚生の活用で企業の厚生年金や法人税の負担軽減効果が期待できます。求職者や新卒者は企業の福利厚生をチェックしているので、同業種で同条件の企業が複数あった場合、福利厚生の内容が企業の選択に関わることが少なくありません。 福利厚生の充実は、自社の働きやすさなどを社外にアピールすることが可能となります。求人情報をチェックしている求職者に対して自社の魅力を発信でき、人材採用時に有利になる効果も期待できる点は、厚生年金保険料による手取り減少対策に付随するメリットといえるでしょう。
2025年社会保険料が値上げされる理由は?予想される影響や値上げ対策を解説についてはこちら〉〉

まとめ
厚生年金保険料はすべての従業員が毎月支払うもので、企業も自社で働く従業員の分を負担する必要があります。給与によって分かれている標準報酬月額の上限が引き上げとなった場合、特に等級が上限に達していた高所得者を多く抱える企業は負担が大きくなることが予想されます。標準報酬月額は今後段階的に引き上げになるため、急激に負担が増えるわけではないものの、今後2年間で高所得者の厚生年金保険料の負担が増加することは明らかです。
標準報酬月額の上限が引き上げになると、従業員にとっても手取り額が減少するので、将来設計に大きな影響を与える可能性があるでしょう。従来と同じ働き方であるにもかかわらず手取りが減ると勤務先への不満やモチベーションの低下につながる要素となり得るので、企業側は来る厚生年金制度の変更に備えた方法を検討することが推奨されます。
厚生年金保険料の負担そのものを企業側で変えることは簡単ではないため、企業内の制度整備を工夫してみるのが、負担増に対抗する一策となるでしょう。柔軟な働き方の導入や給与体系などの整備に加えて、確定拠出年金や福利厚生を上手に活用することによって、従業員の実質的な給与を減らすことなく増加する厚生年金保険料負担への対策が可能です。
2年後に迫る年金制度改正に備えて、高所得者を多く抱える企業や厚生年金保険料の負担を軽減したい企業は、今回ご紹介した方法を参考に対策を講じてみてはいかがでしょうか。
福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>