いつまで続く? 米の価格が値上がりする要因と今後の上昇見通し…まるで令和の米騒動!?

こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。
上昇する米の価格は、いったいいつ戻るのでしょうか。また、米同様に上がり続ける生鮮食品の値上げも深刻です。
こういった状況は、いつまで続くのでしょうか。多くの人が関心を寄せている食費の高騰について、値上がりが起きる要因と今後の見通し、さらには米の価格が上昇しているときに企業が従業員に対してできる対策を、福利厚生の視点から解説します。
福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉
目次
「令和の米騒動」と呼ばれるほどの米値上がり・品薄が続く要因・理由からわかる問題点
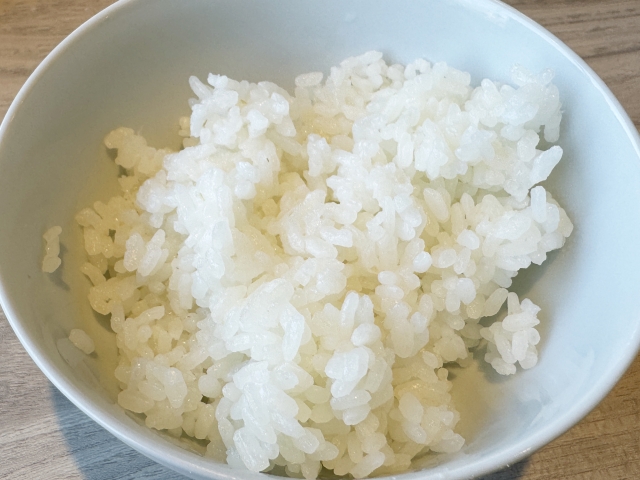
1:米の需要が増加し品薄を招いている
近年、これまでよりも米の需要が増加しています。その背景には複合的かつ経済的な理由があり、日本国内だけでなく海外でも米の需要が高まっていることから海外市場が拡大している点や、米粉や加工食品への利用が拡大している点も影響しています。特にアジアや中東の国々では、日本産の高品質な米が人気を集めている実態によって従来よりも国内市場での供給が減り、価格が上昇する要因にもなっています。
また小麦の価格高騰に伴い米粉を使ったパンや麺類などの食品への注目が集まっていて、食用米だけでなく、加工用米の需要も高まっています。
2:主食ではあるにもかかわらず米の供給が減少している
需要が高まっているにも関わらず、米の供給が減少していることも価格が高騰する理由です。
ひとつには米農家の高齢化が進み、後継者不足による生産量の減少が問題となっています。米作りにかかるコストが上昇する中で、高齢化や経営難を理由に離農する農家も増えています。
また、都市開発や他の作物への転作が進み、米を栽培する農地そのものも以前より減少しています。国の政策による「減反政策(生産調整)」の影響で、米の生産量が抑えられてきたことも供給減少の一因でしょう。
さらに近年では世界的な資源価格の上昇により、米の生産に不可欠な肥料や燃料が高騰していて農家の負担が増えています。生産コストが上がってしまい、一部の農家には生産を縮小する動きも見られます。
3. 異常気象による天候の影響を受けている
主に地球温暖化の影響で、日本の夏は年々暑くなっています。高温が続くと米の登熟(実が成熟する過程)が妨げられます。また米の品質低下や収穫量の減少につながることから、高温による収穫量の減少も米が高騰する原因です。
米以外の生鮮食品、つまり野菜についても異常気象による影響は深刻です。米同様に生育に影響が出ることから価格の上昇や不安定な供給状況が深刻化しています。
また米の生育期に台風や長雨が続くと、稲が倒れたり水田が冠水したりして収穫量が減少します。大雨が増えれば病害虫の発生も増加し、米の収量や品質にも影響を及ぼすでしょう。大雨の影響は、米以外の作物に対しても同様です。
他方で、米作りには大量の水が必要なことから降水量が不足すると生育不良にもつながります。特に夏場の高温と雨不足が重なると、収穫量が大きく減少する恐れがあるとされています。
このように気候変動や異常気象は、米の生産量や品質に大きな影響を与えています。

米の価格が上昇する事態への政府の意見・対応は?

米が高騰している実態については、政府も対策をとっています。
1. 備蓄米の放出について運用を見直しを発表
日本政府は、米の価格が急騰した際に市場を安定させるために「備蓄米(政府が保有する米)」を放出する仕組みを見直し、これまでは凶作などの緊急時のみの運用だったものを2025年2月からは円滑な流通に支障が出ている場合にも放出できる制度に変更しました。
これにより、需給がひっ迫して価格が過度に上昇した場合にも、備蓄米を市場に供給して価格の安定を図ることができるようになりました。
農林水産省によれば「米の市場価格が一定基準を超えて上昇した場合」や「供給不足が深刻化し、消費者への影響が大きいと判断された場合」が対象です。
この仕組みにより急激な価格上昇を抑制し、消費者の負担を軽減することが期待されていますが、放出した分は備蓄として同じ量を買い戻す必要もあることから、再び米の価格が上がる可能性も指摘されています。
なお、2025年2月に農林水産省は21万トンの備蓄米放出を発表し、価格抑制の効果が期待されています。
〉〉備蓄米とは何?購入後の保管方法と米の備蓄方法を解説についてはこちら
2. 生産者に対して米の生産を調整する趣旨の政策が継続されている
米の価格安定を図る目的で実施されていた従来からの「生産調整(減反政策)」は、2018年に廃止されました。生産調整とは、米の過剰供給を防ぐために農家に対して水田での米の作付けを減らし、他の作物(大豆や飼料用米など)への転換を促す政策です。
しかし近年でも「事実上の減反政策」は継続していて、条件の見直しは入っているものの、米以外の作物を生産する米農家に対して交付金を支給する制度が存在します。
米の価格が上昇傾向であったにもかかわらず政府がこの方針を維持するのには、米の供給過多による価格暴落を防ぐ目的や、農業の持続可能性を確保、長期的な需給バランスの維持、食料自給率の維持向上などの理由があるとされています。
しかし米の価格上昇時には、こういった背景が影響して供給が不足しやすくなっている点も指摘されているのが現状です。

今年も品薄は続く?暮らしに直結する「米の価格」が高騰している状況について問題解消への見通し

1:今年も猛暑の影響で引き続き品薄の可能性が高い
米の生産量は、2023年から2024年にかけて記録的な猛暑や少雨の影響によって減少したほか、高温障害によって品質の低下や収量減が発生したり、一部の産地では供給が不安定になったりして品薄を招きました。前年の品薄状態に続き、今年も品薄になる可能性は低くないと見られています。
2025年以降も引き続き異常気象の影響を受ける可能性が高く、今後の天候次第ではさらなる価格高騰につながるリスクもあるでしょう。
2:新米出荷の流通による価格抑制への効果は限定的
通常ならば新米の収穫が始まると供給量が増加するので、米の価格は落ち着く傾向にあります。しかし2025年2月時点で問題となっている価格上昇は単なる一時的な需給バランスの変動ではなく、猛暑の影響による生産量の減少や肥料・燃料の価格上昇に伴う農業資材の高騰、さらには人件費や輸送費の上昇による流通コストの増加が強く影響していることから、新米が市場に出回っても価格の下落幅は限定的になるという見方が主流です。
3:業者等による投機的取引による影響
米も市場の価格変動が激しくなると、投機的な取引が活発化する傾向があります。「今後さらに、米の価格が上がるかもしれない」という不安による市場心理の影響だけでなく、価格変動を利用した短期的な売買を目的とした投資マネーの流入も指摘されています。
投機的取引が増えると実際の需給以上に価格が高騰する可能性が高く、この状況が長くなるほど価格の乱高下が発生し、消費者や流通業者にとっては不安定な状況が続く恐れがあります。
4:店での米の価格が安定するまでには時間がかかる
現状を分析すると米の価格が短期間で安定するとは考えにくく、しばらくは高値が続く可能性が高いという見通しが主流です。
政府の備蓄米放出や輸入米の活用などの対策も進められていますが、作柄次第ではさらに供給が不安定になる可能性もあるうえに、生産コストの上昇が続く限りは価格が以前の水準まで下がる可能性は極めて低いでしょう。また国内で米不足が起きる根本的な原因が解決しない限りは、価格が安定する状況は考えにくい点も否めません。
つまり米の価格が落ち着くまでには、一定の時間がかかる見込みです。
〉〉備蓄米とは何?購入後の保管方法と米の備蓄方法を解説についてはこちら
〉〉エンゲル係数が高くなるのはなぜ?解決策としての節約方法と福利厚生についてはこちら

米の値上げが続く状況に企業ができる従業員に向けた取り組み・検討するべきことは?

1:「食」にまつわる福利厚生を手厚くする
米の価格高騰が家計に影響を与える今は、会社が「食」に関する福利厚生を充実させることで、従業員の生活を直接的にサポートできます。
具体的な施策としては、価格据え置きや米飯メニューを充実させるなどの社員食堂における補助の強化や、食材の社内販売制度によって従業員が安価で購入できる仕組みを整える方法が挙げられます。
また、昼食代の一部負担やクーポンの配布などによる昼食補助制度の拡充も、従業員の食費負担を軽減して健康的な食生活を維持しやすくなる施策になるでしょう。
2:「食」に関係する支援金を会社が支給する
物価高騰の影響を直接的にカバーするために、企業が「食費補助」として金銭的な支援を行う方法も有効です。
例えば「食費手当」として一定額を給与に上乗せしたり、子どものいる家庭は特に影響を受けやすい現実を踏まえて家族を持つ従業員向けに「食育支援金」を支給したりする方法があります。また特定の期間だけ臨時的な「物価高騰手当」を支給する方法もあるでしょう。
直接的な金銭による支援は、従業員のモチベーション向上にもつながります。
3:事業所内に直接的に食事を補助できる場所を提供する
職場内に従業員の食事を補助する環境を整えると、従業員の負担軽減につながります。無料または低価格でご飯を提供する「社内炊き出し」制度や、おにぎり・味噌汁などの軽食を提供するコーナーの設置、社内に「フードパントリー」を設けて安価に米や食品を提供する仕組みなどが挙げられます。
従業員が日々の食事を安心して確保できるようになると、勤務先への愛着心や業務における生産性の向上にも一役買ってくれるでしょう。
✩「オフめし」制度は従業員1名から設置できる“食の福利厚生”
心幸グループが提供する『オフめし』は、企業の規模を問わずに従業員1名から設置でき、卸売価格で商品が手に入るサービスです。年間契約の縛りもなく、ランニングコストは業界最安値(※自社調べ)。
オリジナル惣菜や冷凍弁当、コンビニ商品まで800アイテム以上を取り扱っているので、米が高騰している今、従業員への「食の支援」が直接的に行えます。
全国各地へ配送していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

今後も続くであろう米価格の上昇には福利厚生で従業員へのサポートを(まとめ)

米の価格上昇は、現在のところ収まる気配がありません。ニュースでは連日のように米に関係する報道が続いています。複合的な要因が複雑に絡み合っているために、政府が対策をしても期待するほどの効果が得られていない実態もあります。
米の価格上昇に対して、企業ができる対策は限られます。「食」は健康やモチベーションの源となるものですので、企業として従業員へのサポートを行うことで従業員のストレスや暮らしへの経済的負担を軽減し、業務に集中しやすい環境を整えやすくなるでしょう。
※本記事は2025年2月上旬現在の情報に基づいて執筆しています。
福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>

オフィスにつくる設置型ミニコンビニ

「オフめし」はオフィスの一角にミニコンビニ(置き社食)を設置できるサービスです。常温そうざいや冷凍弁当の他に、カップ麺やパン、お菓子など800アイテム以上から成る豊富なラインナップが魅力。入会金2万円(税抜)+月6,000円(税抜)+商品代+送料からスタート可能で、手軽に従業員満足に貢献できます。
オフめしはこちら
