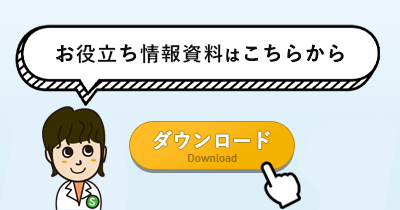単身赴任の生活費はいくら必要?補助額や自己負担の目安と節約法を解説

目次
単身赴任とは?生活費の目安やメリット・デメリット
単身赴任とは転勤や仕事の都合で、やむを得ず家族と離れて一人暮らしを始める生活スタイルです。勤務している会社から異動を命じられた際に子どもの生活環境や配偶者の生活基盤などの事情から家族は同行せず、本人のみが引っ越しをして単身で生活するケースが一般的です。
単身赴任には仕事に集中できる環境が整いやすいメリットがある一方で、家族と過ごす時間が減り二重生活への経済的な負担が大きくなるのがデメリットでしょう。
単身赴任をすると家族の生活拠点とは別の生活拠点を設ける必要があることから、単身赴任前の生活と比べれば生活費のトータルコストがかかります。
単身赴任をするとかかる費用の実態を知りながら、生活費をはじめとした出費を安く抑えるコツをチェックしていきましょう。

家賃以外で単身赴任時に必要な生活費は13万円程度
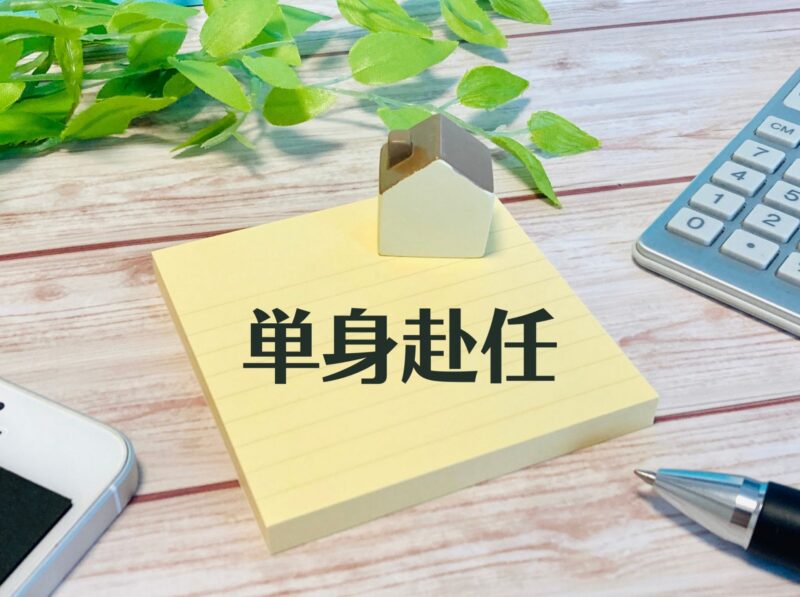
総務省が発表している『家計調査年報(家計収支編)』などから導くと、単身赴任の生活費は、家賃を除くと平均して13万円程度(2019年値)です。
主な内訳は、以下の通りです。
- 食費:外食や自炊費用を含め月に3~4万円程度
- 水道光熱費:電気代やガス代、水道代で1万円程度
- 家具・家事用品費:6,000円程度
- 被服・履物費:5,000円程度
- 保険医療費:8,000円程度
- 交通費:通勤費や生活に必要な移動費で1万円程度
- 通信費:スマホやインターネット代で8,000~1万円程度
- 教育娯楽費:2万円程度
- その他:日用品や趣味に使う費用で3万円前後
これらに加えて、外食や飲み会が多い場合はさらに出費がかさむケースもあります。赴任して間もない頃には、職場の人たちとの親交を深めるために外食費がかさむ傾向も見受けられます。上記の金額は、あくまでも目安として参考にしながらメリハリのある出費を心掛けていきましょう。
また単身赴任先での生活リズムが安定するまでの間は、新たに買い揃えるものも多くなることから出費が増えがちです。
さらに物価高やインフレが進むほど、より多くの生活費がかかるでしょう。
このほか、単身赴任中に必要な生活費を算定するにあたっては、次の2つの点にも留意してください。
生活費の算定には地域によるライフスタイルの違いも考慮する
実際の生活費は、赴任者のライフスタイルや赴任地によっても変動します。
例えば、東京や大阪などの都市部では食費や交通費が増えやすいことから生活費は高めになりやすい一方で、地方では物価が下がる分だけ出費が抑えられる可能性も高いでしょう。
ただし車での移動が必須となる地域の暮らしでは、ガソリン代や車の維持費がかかります。
自宅に帰る頻度によっても出費が変わる
単身赴任における生活費を算定する際には、どのくらいの頻度で自宅へ戻るかも考慮する必要があります。
所属する会社から帰宅旅費の補助がある場合でも、企業によって金額や補助額はまちまちです。
帰宅するときの交通費が必ずしも補助でまかなえない可能性も視野に入れましょう。また定額補助と実費精算のいずれかによっても、自己負担額が変わります。

単身赴任にかかる初期費用の実態はいくら?

単身赴任には、月々の生活費だけでなく初期費用もかかります。
新たな生活拠点で使う生活必需品をはじめとして、さまざまな日用品を買い揃える必要もあるでしょう。
単身赴任にかかる初期費用を抑えることができれば、単身赴任に伴う経済的な負担だけでなく心理的な負担も軽減されますので、できるだけ無駄な出費を抑える工夫が必要です。
また初期費用の負担は、企業側の補助によっても異なります。企業からの補助が大きいほど、個人の負担は少なく済むでしょう。
以下に、具体的なポイントを解説します。
転居費用や新居の契約費用は会社負担が一般的
単身赴任では、転居費用(引越し代)や新居の契約にかかる費用を会社が負担をするケースが一般的です。これは、企業側が従業員の転勤に伴う経済的な負担を軽減するための措置です。
具体的には、次のようなものが補助の対象に該当します。
- 引越し代金:運搬費や荷物の梱包サービス費用。利用する引越し業者を会社が指定する場合もある。引越しの料金は荷物の量だけでなく、距離によっても大きく異なる。
- 敷金・礼金:物件の契約時に発生する初期費用。仲介する不動産事業者を会社が指定する場合もある。敷金や礼金は物件を探す時期によって、変動する場合もある。
- 家賃の一部負担:福利厚生の一環として提供される場合が多い。
ただし会社の規定によっても、企業の負担範囲や内容が異なります。単身赴任が決まった際には、実際の企業負担額について事前に確認をしたほうが良いでしょう。
新居で必要な生活品は自己負担が多い
引越し先の新居では、新しく家具や家電を揃えなくてはならない場合も少なくありません。実態としては単身赴任先の住居は今まで暮らしていた家よりも狭くなるケースがほとんどなので、自宅から持っていこうと思っていた家具が入らない場合も想定する必要があります。
また単身赴任を予定している期間によっても、生活品への必要・不必要の判断が変わってきます。快適な生活を送るうえでは、最低限必要なものから優先して買い揃えていくと出費を減らせます。
単身赴任をするにあたり、必ず揃えなくてはならないケースが多い物品は次のものです。

✩ベッドや布団、ソファ・・・単身赴任先の部屋のサイズに合わせる必要があることから新たに買う人も多い。数万円の出費を考慮する必要がある。
✩冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ・・・自宅で使っているものは引き続き家族が使うため、単身赴任先でも新しく準備する必要がある。数十万円単位での出費が必要になる場合もある。
✩カーテン、照明器具・・・部屋の仕様に合わせて買う必要があるため、単身赴任先の部屋に合わせて新たに買う必要がある。数万円の出費が必要になりやすい。
このような「生活に必要な物品」の購入費用は全額が個人負担になるケースも多く、一度に揃えるとまとまった出費にもなりやすいでしょう。
単身赴任初期の出費を安く抑えるのであれば、優先順位をつけながら必要最低限のものを選び、徐々に買い足していく方法が賢明です。
例えば、単身赴任中に暮らす家の近くに営業時間の長いスーパーマーケットがあれば必要に応じて買い出しに行けることから、家に置くのは小さな冷蔵庫だけでも十分な一方で、近くに食材を買えるお店がない地域に住む場合には大きな冷凍庫まであるほうが暮らしやすい場合もあります。また洗濯をコインランドリーで済ませるなら、洗濯機を買わない選択肢もあるでしょう。
昨今は物価が上がっているので、数年前の感覚で予算を立ててしまうと予想以上に出費がかさむ可能性もあります。事前に価格調査をしたほうが確実です。

単身赴任によって貰える手当の目安は?

単身赴任によって、勤務先から諸手当が出ることもあります。すべての企業で一律に支給される類のお金ではありませんが、手当が出ることによって単身赴任にかかる経済的な負担が軽くなる可能性もあります。
企業が負担する諸手当は、従業員が家族と暮らしている自宅を離れ新たにひとり暮らしをしなくてはならない負担を考慮しながら、従業員本人や家族の負担を軽くすることを目的としています。
なお、手当については「単身赴任手当」名目だけでなく「別居手当」として支給される例もあります。
単身赴任によってもらえる補助については、後ほど詳しく解説します。
単身赴任手当の相場は約5万円
単身赴任手当とは、単身赴任者の生活費を補助するために会社が支給するお金です。単身赴任の負担を軽減するために企業が用意する制度で、民間企業では月額で47,600円程度(出典:令和2年就労条件総合調査の概況)が、一般的な相場です。
なお参考までに公務員の場合には、人事院規則によって月額30,000円と定められています。
この手当は、家賃補助とは別に支給されるケースが一般的で、規模が大きいほど支給を実施している企業の割合が高い傾向もあります。
具体的な支給額は、会社によって異なります。単身赴任手当を支給していない企業もありますし、地域や物価水準によって変動する場合もあります。具体的な条件や金額については、所属する会社の人事部に確認しておくと安心でしょう。
関連記事:単身赴任手当の相場は5万 or 10万?民間と公務員で生活費は違う?条件や種類・税務のポイントを解説
単身赴任手当が支給されるには条件がある
単身赴任手当が支給されるためには、条件があります。公務員と民間企業でも条件は異なりますので、ここでは民間企業のケースを紹介します。
また単身赴任手当の支給要件は法律で定められていないことから、企業によって対応が異なります。
一般的な手当の支給要件としては、次のようなものが挙げられます。
・配偶者も仕事をしている
・養育している子どもの教育環境を変えられない
・持ち家について家族が居住して管理する必要がある
・通院や介護などの理由で配偶者や家族が転勤先に行けない
上記のような「やむを得ない事情」がある場合に限り、単身赴任手当を支給する例もあるため、所属する会社の基準を確認しておくといいでしょう。

単身赴任手当以外にもらえるお金もある?

単身赴任手当以外にも、所属している会社の規定によって手当が支給されることがあります。
一般的なものとしては「住宅手当」や「引越し手当」、勤務地の実情を踏まえた「地域手当」や「帰省手当(一時帰宅支給金)」などが挙げられます。
具体的に解説します。
住宅手当(家賃補助)
「住宅手当」は、「家賃補助」と呼ばれることもあります。
単身赴任先で必要となる赴任者本人が暮らす家の家賃に対して、割合を定めて支給する例が一般的です。
ほとんどの企業では上限額を定めていて、家賃の全額を補助するケースもあれば一部のみを支給する場合もあります。
また社宅や借上住宅が企業から用意されている場合には、単身赴任の期間中はそれらの住宅に暮らす事例もあります。この場合も家賃は全額を企業が負担する場合と本人が賃料を支払う場合があり運用方法はまちまちです。
引越し手当(転居支援金・単身赴任準備金)
「引越し手当」は、「転居支援金」や「単身赴任準備金」という名目の場合もあります。
単身赴任先へ転居をする際にかかる費用を補助するのが目的で、一時金として支払われます。
「引越し」や「転居」という言葉のつく手当においては、一般的に家財を運搬する際の引っ越し業者への支払いが適用範囲で、引越しや転居に関わるそのほかの費用は対象になっていない事例が多いでしょう。
また必ず支給されるとは限らず、会社によって規定はさまざまです。
地域手当(勤務地手当)
「地域手当」は、「勤務地手当」とも呼ばれます。
単身赴任先の実情に合わせて支給されるもので、生活コストがかかりやすい大都市圏への転勤や交通アクセスに不便がある遠隔地域への配属となった場合に、単身赴任者の負担を軽くするのが目的です。
地域手当の額は企業が自由に定めているほか、支給のない企業もあります。
帰省手当(一時帰宅支援金)
「帰省手当」は「一時帰宅支給金」と呼ばれることもあり、単身赴任をしている従業員が赴任地から自宅へ一時的に戻る際の交通費を負担する例が一般的です。
固定費として一律で支払われる場合のほか、実費をベースにして帰省をするたびに精算をするケースもあります。
また企業側で事前に補助をする帰省の回数を定めておき、あらかじめ定めた金額を単身赴任者に支払うパターンも少なくありません。
ただし全ての企業において必ず支払うべく手当ではなく、会社が自由に定めることができます。
このように単身赴任者に支給される手当には、いくつかの種類があります。
適用される範囲や補助の実施有無は企業によって大きく変わりますので、所属する会社に確認をしておくと安心でしょう。

単身赴任の手当にまつわる注意事項
単身赴任にまつわる手当を受け取る際には、その法律的な位置付けを理解しておく必要があります。
重要なポイントを2点解説します。
単身赴任手当は課税対象になる
単身赴任手当は、給与所得にあたることから課税対象です。具体的には、所得税や住民税がかかります。
月または年単位で単身赴任者が帰宅するための旅費を支給する場合でも、毎月一定額を単身赴任手当として支給する場合のどちらでも、課税の対象になる点は変わりません。
一方、例外もあります。
単身赴任者が職務遂行上の理由から旅行する場合に支給される旅費にあたる場合には、これに付随して自宅へ帰宅をした場合でも非課税として扱われます。
例えば週末を挟む4泊5日の出張で、移動をした日の翌日が週末に当たるために土曜日・日曜日の2日間にわたって自宅に滞在したあと、月曜日に出社をして火曜日に単身赴任地へ戻る場合にも非課税が認められています。
単身赴任手当の法律的な位置付けは?
単身赴任手当をはじめとする単身赴任者に支給される補助は、就業規則で定められている必要があります。
事前に規則として明記されていれば支給条件や額が明確になるほか、従業員と会社側での認識の違いに起因するトラブルを防げます。
ただし単身赴任手当は、法律で義務付けられている補助ではありません。
従業員に対する福利厚生としての役割が強く、支給の条件や範囲、方法については会社側が自由に決定できます。

単身赴任生活で節約をするには?

さまざまな手当が出たとしても、日々の生活にかかる費用は抑えられるに越したことはありません。無駄な出費を避け、単身赴任の生活費を節約するために、いくつかのポイントを押さえておきましょう。
家賃の安い物件を探す
単身赴任での転居では赴任期間が終われば自宅に戻ることを想定していることから、赴任中の住まいは買わずに賃貸住宅で暮らすケースがほとんどです。
賃料は毎月の生活費の中でも大きな比重を占める部分ですから、出費を抑えるのであれば安い賃料の物件を選ぶに越したことはありません。立地や設備、築年数などに譲れない部分があるほど高額になりがちなため、妥協できる点を探せるかが賃料を下げるポイントでしょう。
また毎月の賃料を抑えるにあたっては、会社からの家賃補助がある場合には新居を選ぶ段階で家賃補助額を考慮して物件を選ぶといいでしょう。会社からの家賃補助でまかなえる割合が高い物件を探せれば、それだけ自己負担を減らせます。
さらに赴任先では一人暮らしであることを念頭に置き、必要最低限の広さや設備で妥協できると無駄な出費を防ぎやすくなります。また希望のエリアに条件が合う物件がない場合には、探すエリアを広げてみると賃料を抑えながらも納得できる物件が見つかりやすくなります。ただし通勤に不便な立地の賃貸を借りてしまうと、実際に暮らしてみてから不便を感じる可能性もありますので、職場へのアクセスや通勤にかかる所要時間は必ず考慮したほうがいいでしょう。 地域によって家賃の相場は大きく異なりますし、会社からの補助の支給額によっても負担が変わります。通勤の利便性も考慮しながら生活を圧迫しない程度の家賃負担でおさまるよう、物件選びの際には賃料にも重点を置きましょう。
水道光熱費を見直す
電気、ガス、水道を使用する際の費用は、毎日少しずつ節約を意識するほど「チリツモ」で節約ができます。
単身赴任者の場合には、自分以外に使う人がいないのでこまめなスイッチオフを心がけるほか、消し忘れやつけっぱなしの時間を少なくするために、人感センサーのついている照明やタイマー機能を活用するのも方法です。
光熱費は供給事業者の選び方によっても、費用を抑えられる可能性があります。期間限定のキャンペーンを探すと、よりお得に契約できる可能性も低くありません。
家具・家電にかかる費用を見直す
家具や家電類は単身赴任のためだけに新品を揃えると、当初の想定以上の出費になってしまう場合も少なくありません。
一方で「新品購入」以外の選択肢を考慮すると、出費を大幅に抑えやすいでしょう。例えば、リースやレンタルの利用や、フリマアプリやリサイクルショップで中古品を購入するなどの工夫があります。
高価な家具や家電は単身赴任後にも引き続き自宅で使うことを想定して買う場合もありますが、先のことは予定通りにならない可能性も低くありません。 基本的には、単身赴任先での利用だけを視野に入れながら買い物をしたほうが出費は低くなりやすいでしょう。
自炊を増やす
頻繁に外食をすると、食費が高くなっていくだけでなく、栄養の偏りも気になりがちです。
健康的な食生活を維持しながら食費を抑えられるよう、単身赴任先では自炊を取り入れていきましょう。
調理が苦手でも簡単に作れるレシピやミールキットを活用すれば便利ですし、ひとり暮らしでも使いやすいよう小分けになっている食材を買うと、一度の出費を抑えながら栄養バランスのいい食事を続けやすくなります。
通信費やサブスクを見直す
スマホやインターネットの契約プランを見直して、必要最低限のプランに変更するだけでも毎月の出費を下げられます。ただし単身赴任になることによって、これまでとは通信費の内訳が変わる可能性もある点には注意が必要です。
具体的には、スマホなどのデジタルツールによるやり取りが家族との主な連絡手段にもなることから、通話料や通信料は単身赴任前より増えがちです。
プランを見直す際には、単身赴任後の生活を想定して選びましょう。
また契約中のサブスクリプションサービスをチェックして、使っていないものを解約するだけでも固定費を減らせます。
オンラインサービスを活用する
家族と電話で話すときには通信費がかからないWi-Fi対応の通話機能を使う、コンビニやスーパーマーケットに行くと余計なものばかり買ってしまうなら必要なもの以外は買わないと決めてネットスーパーを使うなど、自分の生活スタイルに合わせて各種オンラインサービスを活用すると節約につながる例も少なくありません。
またこれまで家族と暮らしていた生活が一変してひとり暮らしに慣れないうちは、寂しさから無駄なものにお金を使ってしまう傾向もあります。家にいる時間に、無料で試せるオンラインサービスをいろいろと試してみるのも一案です。
単身赴任生活では、食事や健康管理、生活基盤への出費をどれだけ抑えられるのかによって節約効果も変わってきます。
すべてを節約するのは難しくても、無理なく取り組める項目から節約を意識してみてもいいでしょう。 コツを掴んでいくにつれ、無理なく節約生活を楽しめるようになっていきます。

まとめ
単身赴任中の生活費は、工夫次第で無理なく抑えられます。
まずは初期費用や日々の生活にかかる費用を把握し、会社の手当や節約術もうまく活用すると、無駄な出費を減らせるでしょう。
単身赴任中は家族と離れて暮らす寂しさもありますが、赴任者が充実した単身赴任生活を送りながら業務に集中できる環境が整えばベストです。ぜひ参考にしてみてください。
福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>


<参考>
総務省「家計調査年報(家計収支編)」
厚生労働省「令和2年就労条件総合調査の概況」
オフィスにつくる設置型ミニコンビニ

「オフめし」はオフィスの一角にミニコンビニ(置き社食)を設置できるサービスです。常温そうざいや冷凍弁当の他に、カップ麺やパン、お菓子など約600アイテムから成る豊富なラインナップが魅力。入会金2万円(税抜)+月6,000円(税抜)+商品代+送料からスタート可能で、手軽に従業員満足に貢献できます。
オフめしはこちら