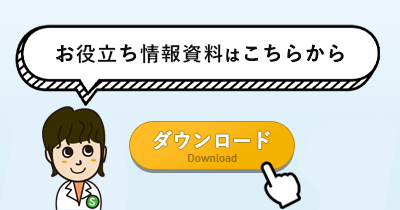影響を解説|円安・物価高のインフレから社員を守る!企業がいま見直すべき福利厚生とは?

こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。
円安や物価高の時代に突入し、この傾向はしばらく続くと見られています。
そこで注目を集めているのが、企業が従業員に行う福利厚生です。円安・物価高の時代に社員を守る施策を実践する企業は、長期的な視点でのメリットも大きいでしょう。
この記事では、企業がいま見直すべき福利厚生について、実践的なポイントを踏まえて解説します。
福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする
目次
【深刻】 円安・物価高が企業と社員の生活に与えている影響について情報を整理
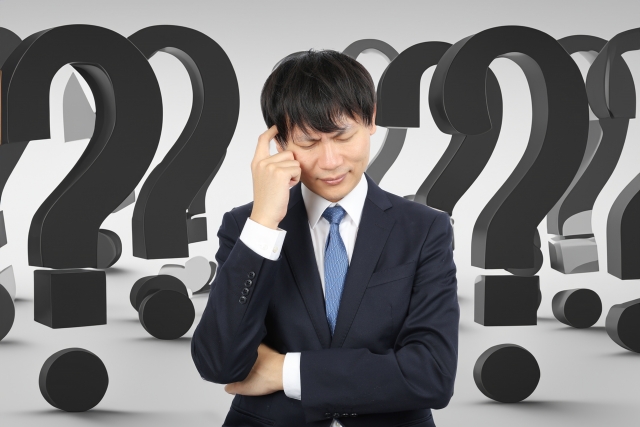
2025年6月時点では、円安や急激な物価高によって、企業や社員の生活には大きな影響が出ています。
そこでまずは、多くの人や企業が直面している主な影響について情報を整理します。
【1ドル145円前後】 日本の円安が食材や生活コストに与える具体的な影響とは?
急激な円安は、輸入依存度の高い日本経済に大きな影響を及ぼしています。2025年6月中旬の為替レートは1ドル145円前後、引き続き円安水準で推移しています。
とりわけ食材やエネルギーといった生活必需品は多くが輸入に頼っている現状があるために、円の価値が下がると仕入れ価格が上昇し消費者価格にも転嫁されています。たとえば小麦や食用油・乳製品、さらには調味料までもが値上がりの対象となっていて、日々の食卓に直接的な打撃を与えているのが現状です。
日本の物価高・インフレはいつまで続く?
専門家の間でも見解は分かれているものの、当面は物価高の傾向が続くと見られています。
物価高の背景にあるのは日本銀行の金融緩和姿勢や世界的な原材料価格の高止まり、地政学リスクといった複合的な要因です。そして、これらが複雑に作用していることから「すぐに元通り」とはいかないのが現実でしょう。
過去記事の『食品・米の物価高はいつまで続く?物価の値上げ地獄における企業のチェックポイントと対策・原因から導く方法を解説』で解説したように、食だけでなくあらゆるもののコストが上がっていることから企業でもコストの見直しや効率化に迫られています。
企業も個人も、今後しばらくは継続的なコスト増に備える必要があるでしょう。
国内で特に厳しい「食費」の上昇とその実態
あらゆるものが値上がりしている物価高のうちで、最も家計を圧迫しているのは「食費」です。
家庭では米やパン、野菜、肉などの基礎的な食材価格の上昇が続いていて、外食チェーンでも次々に値上げを発表しています。
共働き家庭や一人暮らし世帯にとっても、日常の食事が「節約対象」にならざるを得ない状況が広がっています。
なぜ企業が物価高・インフレに対する社員支援に動くべきなのか?
円安・物価高が招く所得格差や社会的不平等への影響は、企業にとって深刻なテーマです。
また物価高による生活コスト増は、社員のモチベーションや健康状態に直接関わります。
社員の心身が不健康になる状況を放置すれば、パフォーマンスの低下や離職率の上昇にもつながりかねません。
こうした背景から企業は積極的に生活支援に取り組む必要が求められていて、円安・物価高への対策施策は経営の持続可能性を高める戦略的投資と位置づけ、積極的に取り組むべき領域と言えるでしょう。
【企業の視点】 食材価格の高騰が社員の健康・生活に及ぼしているリスク

物価高のなかでも特に食材価格の高騰は、写真一人ひとりの健康や生活に、決して小さくないリスクを及ぼしています。
見逃しがちではあるものの意識しておくべきポイントを、企業サイドによる4つの視点から解説します。
【心身に悪影響】 外食・自炊いずれも負担が増している
外食はもちろんながら、日々の自炊に必要な食材すらも高騰し続けている今は、社員にとって「これ以上の食費の節約」が難しい状況になりつつあります。
栄養バランスよりも価格重視の選択をせざるを得ないといった声もあちらこちらから聞こえ、社員一人ひとりの心身の健康にじわじわと悪影響を与えていると考えられます。
【医療費や休職率の増加】 栄養バランスの崩れによる健康リスクが懸念される
手っ取り早く空腹を満たす安価な食事に偏ると、ビタミン・ミネラルの摂取不足や糖質過多の傾向が強まります。
栄養バランスが偏っている、または崩れている食事は、疲労感や集中力低下、生活習慣病のリスクを高める要因にもなりえます。
健康問題は従業員の個人的な問題にとどまらず、長期的には医療費や休職率の増加といった企業や社会の問題にもつながりかねません。
【精神的ストレス】 食の安心・安全に対する不安が高まっている
物価が上がっているなかでの厳しい価格競争では、安価な輸入食品や添加物の多い加工食品への依存が進んでいます。
周囲でも「安いのは嬉しいけれど不安」「こんなに安価だと、何が使われているかわからない」といった声が増えてはいませんか?
食品に対する安心感の低下は精神的ストレスの一因となり、じわじわと不満が蓄積されるだけでなく自己肯定感の低下や自暴自棄といったマイナスの作用にもつながります。
【人材定着への悪影響】 若年層や子育て世代への影響が大きい
収入が限られる若手社員や、教育費・養育費がかかる子育て世代にとって、食費の高騰は死活問題です。
よって若年層や子育て世代には、少しでも給与が上がる仕事へと転職を望みがちな実態もあります。
このような実態から、物価高に対して企業が社員になんの手も打たずに放置をし続ければ、将来的な人材の確保や定着にも悪影響が及ぶ可能性が低くないでしょう。
【物価高・インフレ対策】 企業が取り組むべき「食」に関する福利厚生の選択肢とは?

物価高、とりわけ「食」に関連する物価高騰に対しては、企業が福利厚生としての施策に取り組むメリットが大きいでしょう。
どのような取り組みが求められているのか、企業が取り組みやすい選択肢に絞って解説します。
社員食堂・社食補助の再評価
過去には、多くの企業が一度は見直しを迫られた「社員食堂」。コストカットですでに廃止をした企業も少なくないなか、今になって再び注目が集まっています。
栄養バランスが取れた食事を低価格で提供することは、健康促進と物価高対策の視点から企業にとっては一石二鳥で、自社に社員食堂がない場合でも、提携飲食店での割引や補助制度の導入によって一定の効果をあげている好事例が目立ちます。
お弁当や宅配食サービスの補助 (食事クーポンの配布や地域での連携強化施策も含む)
外部の宅配弁当サービスや食事クーポンを活用する企業も増えていて、リモート勤務が主流となっている事業所でも自宅で利用できる支援策を導入し、社員から高い支持を得ているケースがあります。
また、地元の飲食店と連携して地域経済を支援しながら福利厚生を拡充する取り組みも、これまで以上に注目されています。
食材配布や定期便などの物理的支援
企業が米や野菜、調味料などの食材や食品を直接的に配布したり、提携農家からの定期便を手配したりするケースも現れ始めています。
「食」に関連する業務を行う企業ではなくても実際に会社から社員に対して「物」が届くという実感があると、社員一人ひとりの満足度を高め、社員個人だけでなく家族にも向けた生活支援にもつながることから「会社が従業員とその家族を大切にしている」というメッセージにもなるでしょう。
円安・物価高対応の福利厚生施策を成功に導くポイントとは?

食への施策だけでなく、住宅手当や通勤費支援などを含む円安・物価高対応の福利厚生施策は、行き当たりばったりに取り組むと失敗をしかねません。
そこで、成功に導くために欠かせないポイントを整理します。
ポイント1:「社員の声を反映する仕組み」を確立する
福利厚生は「与える」ものではなく、「ともに作る」ものへと変化している視点を大切にしましょう。
会社が“上から目線”で「何かをしてあげる」といった姿勢では、せっかくの施策も失敗しがちです。
「ともに作る」ためには社員の声を反映する仕組みが不可欠ですので、定期的なアンケートや意見箱など、多くの社員のリアルな声を吸い上げるよう意識しましょう。
仕組みを整えられれば、ニーズに即した施策を展開しやすくなります。
ポイント2:福利厚生が企業ブランディングに与える影響を考慮する
「社員にやさしい企業」というイメージは、採用力や社外の信頼にも直結します。
今の時代にはWEBやSNSを通じて企業の取り組みを発信する機会も少なくないことから「この会社で働きたい」「安心して働ける」と思ってもらえるブランディングは、企業にとって必要不可欠な視点にもなっています。
福利厚生の施策でも、社会が好意的に感じる施策への取り組みが有効と言えるでしょう。
ポイント3:自社の規模に応じた実現可能な対応方法を模索する
予算の関係もあって、すべての企業が大規模な福利厚生を導入できるわけではありません。
そのため中小企業でもできる施策を模索する柔軟性も大切な視点で、仮に小さな会社だとしても地域食堂との連携やクーポンの配布など、コストを抑えた柔軟な支援方法は見つけられます。
重要なのは「やらない」理由を探すのではなく、「できること」から始める姿勢です。
【個人施策との相乗効果】 物価高対策と生活防衛術を併用し施策効果をアップさせる秘策

ここからは、個人でできる物価高対策と生活防衛術について、企業側ができる取り組みを解説します。
従業員の生活を守りながら個人・企業で双方の取り組みの効果を少しでも上げるべく、企業側が意識したいポイントを見ていきましょう。
【常に無駄を省く声かけを】 日常生活における食費やエネルギー費への対策
冷蔵庫の中身を把握して計画的に食材を使う、まとめ買いを活用する、エネルギー効率の良い調理方法を探すなど、日々の生活における小さな工夫を組み合わせれば、従業員は生活コストの削減につながります。
企業側は、まとめ買いの推奨や、節電・節ガスのポイントを従業員に周知することも施策の効果を上げる上で有効です。
一つひとつの取り組みは小さなことでも「常に無駄を省く意識を持つ」ことの積み重ねによって、家計にゆとりが生まれます。
【見えない貯金・資産を増やす】 ポイント還元やキャッシュレス決済の活用による地道な節約術
キャッシュレス決済やポイント制度は、現代における“見えない貯金”です。日々の小さな積み重ねが、月単位あるいは年単位では大きな差になります。
企業側ができる取り組みとしては、地域通貨のポイント制度など事業所の風土に合う節約術を従業員に告知することで、従業員が「何をするべきなのか」が明確になりやすく、地道な節約を続ける効果が期待できるでしょう。
まとめ:物価高対策の福利厚生には「短期的なコスト」でなく「中長期的な投資」の視点を

物価高や円安といった外的要因は、企業努力だけで解決できるものではありません。
しかし社員の生活を守るための支援策は、企業の未来を守るための中長期的な投資です。住宅手当や通勤費支援だけでなく特に生活に密着する「食」を中心とした福利厚生の強化は、社員の健康と働きやすさを支えるだけでなく、企業の魅力や成長力を高める大きな武器にもなるでしょう。
すぐに施策の効果が目に見えなくても、地道な施策を続けていく姿勢が求められています。
福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>

はたらく人を元気にする会社

グループ間協力で、売店・食堂・企業内福利厚生をワンストップでサポートいたします。売店とカフェの併設や24時間無人店舗など、個々の会社では難しい案件も、グループ間協力ができる弊社ならではのスピード感で迅速にご提案します。
心幸グループ WEBSITE