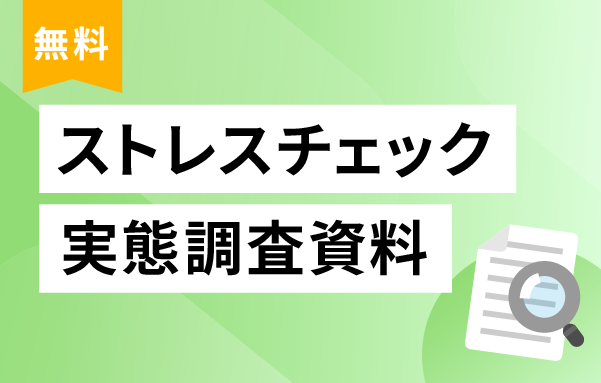ストレスチェックが義務化になる!?企業が知るべき実施方法と注意点をご紹介

こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。
近年、働く人々のメンタルヘルス対策は、企業経営において欠かせない要素となっています。中でも「ストレスチェック制度」は、労働者の心理的負担を把握し、職場環境の改善を促すために、2015年の法改正により従業員50人以上の事業場を対象に義務化された制度です。さらに、労働安全衛生法の改正により、今後はすべての事業場が対象となり、公布から3年以内に施行される予定です。2025年においてもストレスチェックは企業経営において重要な立ち位置にあり、全ての企業が準備を進める必要があります。
しかし、実際に制度を運用する際には、法律上のルールや実施手順、プライバシー保護、結果活用の方法など、多くのポイントを押さえることが求められます。本コラムでは、制度の概要から具体的な手順、注意点、外部委託や助成金活用のヒントまで、企業担当者が知っておくべき情報をまるごと解説します。単なる義務対応にとどまらず、制度を職場改善と組織力強化につなげるための実践的な視点をお届けします。
福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉
目次
ストレスチェック制度の概要と重要性

制度導入の背景と目的
ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調の予防を目的に、2015年12月に労働安全衛生法の改正で導入されました。背景には、長時間労働や人間関係のストレスによるうつ病・適応障害などの増加があります。厚生労働省の調査では労働者の約6割が強いストレスを感じており、企業としても看過できない状況です。制度は、年1回の質問票調査で従業員の心理的負担を測定し、高ストレス者には医師面接を実施。職場環境の改善につなげることで健康保持と生産性向上を目指します。
引用:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000153859.pdf
ストレスチェックの基本的な仕組み
この制度では、従業員が質問票に回答し、心理的負担をチェックし、医師や保健師など「実施者」が評価します。結果は本人に直接通知され、同意がない限り事業者は個人の結果を閲覧できません。高ストレス者には、本人の申出に基づき医師面接が行われ、必要に応じて就業上のケアを行います。また、部署単位での「集団分析」により、組織のストレス要因や傾向を把握し、改善策を立案可能です。プライバシー保護を前提とした運用が、制度の信頼性を支えています。
企業・従業員双方にとってのメリット
ストレスチェックは単なる義務対応にとどまらず、企業と従業員の双方にメリットをもたらします。従業員は自らのストレス状態を客観的に知り、改善のきっかけを得られます。企業はメンタル不調による休職・離職を防ぎ、採用や教育コストを削減できるほか、生産性低下を防止できます。また、健康経営優良法人認定などの取得にもつながり、企業ブランドや採用競争力を高め、企業価値向上にも役立ちます。働きやすい職場づくりの一環として、制度活用は不可欠です。
詳しくはコチラ:https://www.shinko-jp.com/column/kenkoukeieiyuuryouhoujin/

ストレスチェックの義務化に関する法律

労働安全衛生法における位置づけ
現段階では、常時50人以上の労働者を使用する事業場に、年1回以上のストレスチェック実施を義務付けています。対象は事業場単位で判断され、本社や支社ごとに従業員数を確認する必要があります。調査票の内容は厚生労働省指針に準拠し、心理的負担の程度を把握できる形式でなければなりません。対象条件は厚生労働省の指針一覧で確認可能です。
事業者の義務と責任範囲
事業者は、ストレスチェックの計画策定から実施者の選任、結果通知、必要に応じた職場改善まで一連のプロセスを確実に行う責任があります。特に結果の保存義務は5年間とされ、個人情報保護の観点から厳格な管理が求められます。また、従業員に不利益な取り扱いをしないことも義務付けられており、制度運用には法的配慮が欠かせません。また、実施や結果保存などの社内の運用方針を明確化する必要があります。
未実施時のリスクと行政対応
義務を怠っても直接の罰金はありませんが、労働基準監督署による是正勧告や指導の対象となります。さらに、安全配慮義務違反として損害賠償を請求される可能性もあります。制度未実施は、法令違反に加え企業イメージの低下にもつながるため、確実な実施体制の構築が必要です。

ストレスチェックが義務化される対象企業と実施頻度

対象となる事業場の条件
ストレスチェックの義務は、従来「常時50人以上の労働者を使用する事業場」に適用されてきました。ここでいう「労働者」には正社員だけでなく、契約社員、パートタイマー、アルバイトも含まれます。対象は企業単位ではなく事業場単位で判断されるため、本社・支社・工場・支店など、拠点ごとに従業員数を確認する必要があります。従業員数が変動する場合でも、常時50人以上を超える状態が継続すれば対象となります。そのため、複数拠点を持つ企業は、拠点ごとに対象可否を判断できる体制づくりが欠かせません。
さらに、労働安全衛生法の改正により、このストレスチェック制度の対象は大きく拡大します。改正後は「すべての事業場」が義務化の対象となり、従業員数や事業場規模にかかわらず対応が必要となります。この改正は公布から3年以内に施行される予定であり、今後は中小規模事業場も含めて、全ての企業が体制整備を進めることが求められます。
従業員数のカウント方法
人数の算定では、雇用形態にかかわらず常時使用している労働者を含めます。「常時」とは、おおむね1年以上雇用している、または1年未満でも更新により継続雇用が見込まれる場合を指します。派遣労働者については派遣先の事業場の人数に含めて計算します。このため、派遣受け入れが多い企業や季節雇用がある業種では、時期によって対象事業場になる可能性があります。計算方法を誤ると法令違反につながるため、正確な把握が不可欠です。
実施頻度と適切な時期
法律上、ストレスチェックは「年1回以上」の実施が義務付けられています。多くの企業は定期健康診断と同時期に行うことで、従業員の負担軽減と業務効率化を図っています。しかし、繁忙期や業務集中期は回答率が低下する傾向があるため、比較的落ち着いた時期を選ぶのが望ましいです。また、年度末や人事異動後は職場環境が変化しストレスが高まる場合があるため、その時期に合わせた実施も効果的です。年間計画に組み込み、確実な実施を心がけましょう。

ストレスチェック実施の流れと手順

実施体制の構築
ストレスチェックを適切に行うには、まず実施者の選任と計画策定が必要です。実施者には、医師や保健師、一定の要件を満たした看護師や精神保健福祉士などが該当します。事業者は、実施方法、スケジュール、対象者の範囲を明確にし、従業員への周知を行います。また、個人情報の取り扱いルールや、同意取得の方法も事前に定めておくことが重要です。必要に応じて外部委託先を選定し、法令遵守とプライバシー保護の体制を整えます。準備段階の質が、実施の円滑さと従業員の信頼につながります。
質問票の作成・配布方法
質問票は、厚生労働省が推奨する57項目を含む標準的な形式を用いるのが一般的です。内容は、職場環境や仕事内容、心理的負担度、身体的症状などを調査します。配布方法は紙とスマホなどで行うWeb形式があり、Web化すれば集計や管理が効率化できますが、IT環境や従業員の利用しやすさを考慮する必要があります。配布時には回答の匿名性や結果の利用目的を明示し、従業員が安心して回答できる環境を整えることが、正確なデータ収集の前提条件となります。
回収・集計・分析
回答回収後は、実施者が集計・分析を行います。外部委託を利用する場合は、委託契約の中で個人情報保護や守秘義務を明確に規定することが重要です。分析では、個別結果の判定と併せて、部署ごとの平均値や傾向をまとめる「集団分析」も行います。これにより、職場ごとのストレス要因を可視化でき、改善の方向性を検討する材料となります。データは厳重に管理し、法令で定められた期間(5年間)保存する必要があります。
結果の本人通知とプライバシー保護
ストレスチェックの結果は、本人に直接通知されます。同意がない限り、企業が個別結果を閲覧することは認められていません。このプライバシー保護は、従業員の安心感を高め、回答率向上にも寄与します。通知方法は書面や電子メールなどがありますが、セキュリティを確保できる手段を選ぶことが大切です。また、結果を受け取った従業員が希望すれば、面接指導を申請できることを案内し、申請窓口や手続きを明確に示す必要があります。
集団分析と職場環境改善への活用
集団分析は、部署や職場単位でのストレス傾向を明らかにする重要な工程です。分析結果から、長時間労働、コミュニケーション不足、職務の偏り等の、職場特有の課題が浮き彫りになります。事業者は、これらの課題に対して具体的な改善策を検討し、必要に応じて就業規則や業務フローの見直しを行います。改善計画は従業員に周知し、進捗を共有することで信頼を高められます。ストレスチェックは、単なる調査で終わらせず、職場改革のきっかけとして活用することが求められます。

高ストレス者への面接指導とその対応方法

面接指導の対象者と申出方法
ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された従業員は、本人の申し出により医師による面接指導を受けることができます。対象者は、標準化された評価基準に基づき判定されますが、実施者から直接申出の案内を受ける場合もあります。重要なのは、申出が本人の自由意思に基づいて行われることであり、企業は申出しやすい環境を整える必要があります。申出方法は書面、メール、専用フォームなど複数用意し、手続きを簡潔にすることで利用促進につながります。
医師による面接指導の流れ
面接指導は、労働者の就業状況や生活習慣、ストレス要因を総合的に確認する場です。医師は、長時間労働や業務内容の偏り、人間関係の問題など、心理的負担の背景を把握します。面接の所要時間は30分程度が一般的で、必要に応じて医学的助言や治療の提案が行われます。結果は書面でまとめられ、事業者に意見書として提出されますが、その際も個人情報保護を徹底することが求められます。
事業者が取るべき就業上の措置
医師の意見書を受け取った事業者は、必要に応じて就業上の措置を講じなければなりません。具体的には、労働時間の短縮、業務負担の軽減、配置転換、在宅勤務の導入などがあります。措置は本人の希望や業務の実情を考慮して決定し、改善効果を定期的に確認することが重要です。また、対応経過は記録として残し、後日の検証や法的対応に備えます。これらの取り組みは、安全配慮義務の履行にも直結します。
記録保存と法的留意点
面接指導に関する記録は、労働安全衛生法により5年間の保存が義務付けられています。保存するのは、申出書、面接記録、医師の意見書、就業上の措置記録などです。これらは個人情報として厳重に管理し、アクセス権限を制限します。また、保存期間中の情報漏えいは法的リスクや企業信用の失墜につながるため、紙媒体・電子媒体ともにセキュリティ対策を徹底する必要があります。法令遵守と情報管理は、制度運用の信頼性を保つ基盤です。

ストレスチェックの助成金と外部委託

活用できる主な助成金制度
ストレスチェックや職場環境改善に活用できる助成金には、厚生労働省の「職場環境改善計画助成金」などがあります。この助成金は、ストレスチェック結果の集団分析に基づき、職場改善の取り組みを行う場合に支給されます。例えば、外部専門家による研修やコンサルティング、職場レイアウトの改善、コミュニケーション促進施策などが対象です。助成金を活用することで、コスト負担を抑えながら制度の質を高められます。ただし、事前申請が必要な場合が多いため、スケジュール管理が重要です。
申請条件と手続きの流れ
助成金の申請には、対象事業場であることや、計画書の提出、実施報告書の作成など、一定の条件を満たす必要があります。申請の流れは、まず実施計画を策定し、労働局や助成金事務局に事前申請します。承認後に計画を実行し、終了後に実績報告と必要書類を提出します。申請時には、見積書や領収書、改善前後の比較資料など、証拠資料が求められる場合が多いです。条件を満たさないと不支給となるため、手続きの正確さと期限厳守が欠かせません。
外部委託のメリット・デメリット
ストレスチェックの運用を外部委託することで、法令遵守や個人情報保護、集計・分析の効率化が容易になります。特に中小企業では、専門知識や人員不足を補える点が大きなメリットです。また、外部事業者は最新のシステムや豊富なノウハウを持っており、運用の質を高められます。一方で、委託費用が発生し、自社の状況に合わせた柔軟な対応が難しい場合もあります。契約前にサービス内容、費用、セキュリティ体制を比較検討し、最適なパートナーを選定することが重要です。

ストレスチェックサービスの選び方と比較

法令遵守と設問内容の確認
サービスを選ぶ際は、厚生労働省が推奨する標準的な設問(57項目)に対応しているかを必ず確認します。法令に準拠していない設問では、義務を果たしたことにならず、再実施や指導の対象になる恐れがあります。また、必要に応じて自社独自の質問を追加できる柔軟性も重要です。設問の妥当性は、分析結果の正確さや改善策の効果に直結するため、導入前にデモや資料で仕様を確認し、法令遵守と実用性を両立したサービスを選びましょう。
機能面での比較ポイント
集団分析機能や改善提案機能の有無は、サービス選定の大きなポイントです。集団分析が充実していれば、部署ごとの課題や傾向を把握しやすくなります。また、結果をもとに具体的な改善策を提案してくれるサービスなら、実施後のアクションまでスムーズに進められます。さらに、オンライン対応や多言語対応が可能であれば、在宅勤務者や外国籍社員にも利用しやすく、回答率の向上が期待できます。機能の有無は運用効率や効果に直結します。
セキュリティと個人情報保護体制
ストレスチェックは機微な個人情報を扱うため、セキュリティ体制は最優先で確認すべき項目です。データの暗号化、アクセス権限の管理、サーバーの安全性、情報漏えい防止策などが整備されているかを確認します。また、プライバシーマークやISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証の有無も信頼性の判断材料となります。委託契約時には、個人情報の取り扱い範囲や責任分担を明確に定め、万が一の際の対応フローも確認しておくことが重要です。
サポート体制と費用感
サービス導入後のサポート体制も重要な比較基準です。初期設定や操作方法の説明、結果分析後の改善提案、従業員への周知支援など、運用全般をフォローしてくれるかを確認しましょう。また、費用は単なる導入価格だけでなく、更新料や追加サービス料なども含めた総コストで比較する必要があります。安価でもサポートが不十分だと運用負担が増し、逆に高額でもサポートが充実していれば結果的にコストパフォーマンスが高まる場合があります。

ストレスチェック:社員の健康維持を目指すなら「オフけん」

心幸ウェルネス株式会社が提供しているサービス「オフけん」では「健康管理アプリ」を中小企業だと月額二万円から始めることができます。このアプリでは厚生労働省推奨項目を網羅しているストレスチェックだけでなく健康診断やストレスチェックの診断結果から産業医が対応するオンライン診療を受ける事ができるので、アプリ一つで一連のストレスチェックの診断、その後の対応まで完結する事ができる、画期的なサービスです。「健康管理アプリ」にはストレスチェック以外にも、運動動画、健康診断記録、目的別健康レシピなど様々な角度から従業員の健康をサポートする制度が整っています。
その他にも、「からだ測定会」というRPG感覚で、従業員の「ステータス」を見える化することができます。6種類の運動能力を測る「体力測定」、体脂肪率や筋肉量・内脂肪レベルなどが分かる「からだスキャン」、身体のゆがみや未来姿勢を測定する「AI未来姿勢」などを行うことができます。これらのサービスは従業員を健康に導くだけでなく、社内のコミュニケーションの活性化にもつながり、職場全体の一体感やモチベーション向上、さらには生産性の向上にも寄与します。

まとめ
ストレスチェックは、法令に基づく義務として実施するだけでなく、職場環境改善のための有効なツールとして積極的に活用することが望まれます。調査結果から組織の課題を抽出し、労働時間や業務分担、職場コミュニケーションの改善など、具体的な施策に反映させることで、従業員の健康保持だけでなく生産性向上や離職防止にもつながります。さらに、こうした取り組みを外部に発信することで企業の信頼性や採用力の向上にも寄与し、義務的な対応を価値ある投資へと転換することが可能です。しかし、年1回のストレスチェックだけでは十分とはいえません。職場環境は常に変化しており、一度の改善で終わらせず、定期的に状況を見直すことが必要です。そのためには、日常的なメンタルケアの仕組みや、従業員が気軽に相談できる環境づくり、柔軟な働き方の導入など、継続的な取り組みが求められます。経営層から現場までがメンタルヘルスを経営課題として共有し、全社的に推進していくことこそが、健全で持続可能な組織づくりにつながります。
引用:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74001000&dataType=0&pageNo=1
福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>