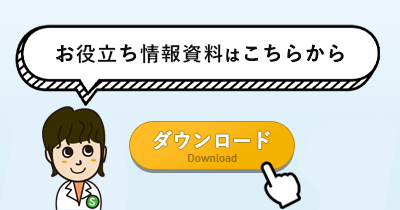1on1の目的や効果とは?進め方や実施するメリット、定着させるためのポイントを解説

こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。
企業内ではさまざまなタイプのミーティングが行われることがありますが、その中で現在注目されているのが、「1on1」というミーティングです。1on1には、従来のミーティングとはどのような違いがあるのでしょうか。本記事では、1on1の目的や効果、基本的な進め方とともに、実施するメリットや企業で定着させるために押さえるべきポイントなどを解説します。
福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉
目次
1on1とは?
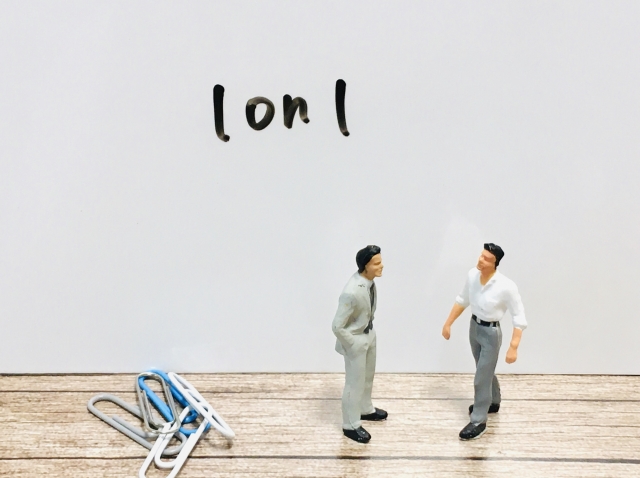
1on1とは、上司と部下がマンツーマンで定期的に話し合うミーティングのことです。つまり、対象者は基本的に従業員全員です。一般的なミーティングは複数名が参加して行うため、場合によっては上司が一方的に話すのみで終わってしまうことがあります。一方で、1on1では上司と部下が一対一で話し合えるため、よりオープンで自由な内容で話し合いが可能です。
元々、1on1はアメリカの企業で始まったマネジメント手法で、世界のハイテク産業が集中するアメリカのシリコンバレーの企業でも根付いている手法と言われています。日本では2012年、ヤフー株式会社が最初に1on1を実施したと言われており、以来日本でも、大企業をはじめとしてベンチャー企業や中小企業に至るまで積極的に導入が進められている手法です。
1on1と同じように上司と部下が行う面談として、従業員の評価を決めるために話し合う「評価面談」があります。どちらも上司と部下が一対一で行う面談ですが、評価面談は目標の達成状況や課題、今後の目標などを話し合い、評価を決めるために行われます。
これに対し1on1は、部下の成長を促しモチベーションを高めるなど、直接的な評価とは異なる目的を持つという点が異なります。 評価面談は人事に関わるため1年に1~2回程度の実施ですが、1on1は週1回、または月1回などの短いサイクルで定期的に、かつ1回あたりの約15~30分の短時間で行うのも特徴です。

1on1が重要と言われる理由

企業ではさまざまな面談などで上司と部下が話し合う場面はありますが1on1が企業や従業員にとって重要性が高いミーティングと言われています。なぜ1on1が重要なのか、その理由や背景として以下の3点が挙げられます。
働き方の多様化に対応するため
2020年の新型コロナウイルス流行を機に数多くの企業で普及したテレワークをはじめとして、副業などを行う人も増えるなど、近年は働き方が多様化しています。このような変化に対応する方法として、1on1が重要といわれます。
テレワークを導入した企業では、毎日すべての従業員がオフィスに集う必要がなくなり、自宅などオフィスから離れオンラインでつながった状態で業務を遂行することが可能となりました。テレワークで時間や場所にとらわれずに働くことができるようになった一方で、従業員同士が顔を合わせる時間が減ったことにより、コミュニケーションが不足する事態に陥ることがあります。コミュニケーション不足の状態では上司と部下がじっくりと話し合える機会も少なくなり、仕事についての相談や意見ができる場も減ってしまうでしょう。
そこで1on1を実施することで、上司と部下がマンツーマンでお互いにきちんと話し合う時間を持てます。働き方の多様化によって不足しがちな心身の健康管理も同時に行えることから、1on1は健康経営につながるという見方もあります。コミュニケーション不足を補いつつ、上司と部下が良い関係を築いて働ける環境作りに寄与するという意味で、1on1は働き方の多様化に対応するために必要なミーティングといえるでしょう。
人材流出に対応するため
上記のように、近年は働き方の変化に伴い従業員同士のコミュニケーションが希薄になるケースが増えています。社内でのコミュニケーション不足は部下の不満や不安、要望などを汲み取りにくくする要因となり、これによって働きにくさを感じる従業員の離職につながる恐れもあります。
現在は、少子高齢化によって労働人口が減少傾向にあります。その傾向は今後も続くと予想されており、労働力の確保は企業にとって重要な課題です。しかし、高い能力やスキルを持っている人材は、より良い条件の企業で働くために転職を選択することも珍しくありません。
入社後定年まで働き続ける終身雇用が崩壊しつつあるといわれる中、優秀な人材に長く働いてもらうことは、企業側の課題といえます。そのためには、好条件の提示だけではなく職場環境の充実もポイントとなります。そこで1on1は、コミュニケーションを取れる環境を作る場としても効果的です。
1on1では上司と部下の一対一での定期的なミーティングで部下の不満をヒアリングできるので、問題をスピーディーに解消しやすくなり、職場環境悪化による人材流出を防げるでしょう。同様に、従業員同士がコミュニケーションを重ねていく中で職場環境を改善し、人材流出を防ぐ方法となることが期待できることも、1on1が重要である理由です。
VUCA時代に対応するため
VUCA(ブーカ)とは、「Volatility(変動性)」、「Uncertainty(不確実性)」、「Complexity(複雑性)」、「Ambiguity(曖昧性)」の4つの単語の頭文字を取った言葉です。2010年代以降の現代社会は、従来と比較して大きく環境が変化しています。これらの単語が示すように将来の予測が困難となっている時代として、現代は「VUCA時代」と呼ばれています。これは、AIなどのテクノロジーの急速な発展や働き方の多様化などによってビジネス環境に大きな変化を迎えることにより、これまでの価値観やビジネスモデルが通用しなくなることも指しています。
VUCA時代への対応に必要な要素は、過去にとらわれない柔軟な思考だといわれます。過去の経験を活かすことが難しい時代に突入している中で、柔軟な思考を共有するには、社内コミュニケーションの活発化が重要です。1on1のミーティングを通して上司と部下が対話を通してコミュニケーションを取り柔軟な考え方を共有することが、VUCA時代の大きな変化に対応するための一策となり得ます。

1on1を実施する目的

アメリカ発祥の1on1は、現在は日本の多くの企業でも実施されています。企業内で1on1を実施する目的として、主に以下の4つの目的が挙げられます。
部下の成長支援
1on1の第一の目的といえるのが、部下の成長支援や人材育成の促進です。ミーティングというと、上司が話す時間の割合が多いと思われがちですが、1on1はあくまでも部下が主体のミーティングです。部下が主体的になることで自らの話を中心に話題を進められ、不満や問題に対しても上司と協力して解決しやすくなるでしょう。この1on1の流れによって、部下の主体性を高められます。
部下が社内で相談しづらい悩みなどを一対一で上司に話せる機会となるので、上司はその内容に対するアドバイスやフィードバックがしやすくなります。また、上司は状況を把握した上で気づきや考えを部下に提供することにより、部下の成長促進が期待できます。
信頼関係の構築
1on1を実施する目的には、上司と部下が信頼関係を構築することも含まれます。コミュニケーション不足の状態は従業員同士の関係に大きく関わり、日頃からコミュニケーションを取れていない相手に対してはなかなか信頼関係を築くことはできないでしょう。不満や悩みを社内の誰にも相談できない状態は、離職を招く原因となってしまいます。
そこで1on1で上司と部下が一対一で面と向かって話す機会を設けることで、相談がしやすい環境を作れます。定期的に1on1を実施していくうちに、信頼関係が構築しやすくなることが期待できます。
現場や部下の問題把握・解決
定期的な1on1は、上司が部下の業務の進捗や職場環境などの現状を把握する良い機会となります。定期的な1on1で状況把握を続けていれば情報がアップデートしやすく、より細やかに部下の問題把握につなげられます。
問題を把握すると同時に、部下が属する部署やチームなどが抱える問題の把握も可能となり、上司と部下が解決策を見出すきっかけも作れるでしょう。
組織力の強化
上司と部下が1on1を重ねていくうちに、信頼関係の構築や部下が抱える問題解決など、社内のコミュニケーションに良い影響が期待できます。コミュニケーション不足を補うことができれば、職場環境が改善でき、従業員のモチベーションやパフォーマンス向上につながります。このような好循環によって組織力の強化を目指すのも、1on1の目的のひとつです。

1on1に期待できる効果

1on1の重要性が注目されている理由は、さまざまな効果が期待できる手法だからです。具体的にどのような効果が期待できるのか、1on1にデメリットがあるのかどうかを以下で解説します。
部下のモチベーションを高められる
前述したように、1on1は上司と部下がコミュニケーションを取れる機会が得られるので、上司が適正な評価をしやすくなる環境も整います。もし評価に不満や疑問があった場合も、1on1で上司と話し合うことができるので、部下も自分の能力や成果に対して正しい評価を受けられる効果が期待できます。自分の能力や成果がキャリアアップに直結するのであれば、部下はもっと成果を出そうとするため、モチベーションを高められるでしょう。
また、円滑なコミュニケーションが取れる職場環境で従業員同士の関係が良好になれば、この中でもっとがんばろうという意欲を引き出す効果により、モチベーションの向上につながることが期待できます。
上司と部下の信頼関係が構築できる
1on1の目的のひとつが上司と部下の信頼関係の構築ですが、1on1が従来の面談とは異なる点が、目的が部下の評価ではないという点です。1on1では仕事の話をすることはもちろん、仕事とは直接関係がないプライベートの話をする機会もあります。
定期的にさまざまな話題で話し合っていくことで、上司と部下の間でスムーズに信頼関係の構築ができることも、1on1に期待できる効果です。
定着率アップ
1on1で社内の人間関係が円滑になり良好なコミュニケーションが取れる環境になると、業務もスムーズに進めやすくなります。成果に対して適正な評価を受けられ、かつ積極的に上司に意見を伝えやすい風通しの良い環境は部下にとって働きやすく、成果も出しやすい環境となるでしょう。
このような職場環境は、「もっと成果を出そう」と従業員一人ひとりのモチベーションが向上する効果が期待できるため、離職者が減り定着率がアップする効果が期待できます。
1on1のデメリットは?
1on1には、上司と部下が密にミーティングを行うことで職場環境が良好になるなど良い効果が期待できる一方で、デメリットも存在します。
そのひとつが、時間を無駄にしてしまう可能性があるという点です。1on1は基本的に定期的に行うものですが、その内容によってはミーティングばかりに時間を取られてしまうという印象を受けられかねません。1on1を実施する目的をきちんと把握した上で行わなければ、定期的なミーティングという形だけが形骸化して中身がなくなってしまい、本来期待できる効果も得られないでしょう。
1on1は短時間のミーティングではありますが、多忙な部署ではその時間を確保することが難しい場合もあります。繁忙度によっては、1on1の定期的な実施が業務の遂行や部下への負担になる可能性がある点もデメリットです。

1on1でよくある失敗例

1on1は、本来の目的に沿って行えば従業員と企業双方に多くのメリットが期待できる方法です。しかし、1on1を実施しても効果が現れない失敗例も少なくありません。そこで、効果のない1on1を避けるために知っておきたい、よくある失敗例をご紹介します。
上司ばかりが話してしまう
1on1は、上司と部下の一対一での対話が基本です。上司ばかりが一方的に発言してしまい、部下が話を聞くだけの状態になってしまうと、一般的な面談と同じような内容となり意味がありません。
このような失敗例は上司に非があるわけではなく、部下が自主的に話そうとしない場合でも起こり得ます。部下が積極的に話さない場合に、上司が話しすぎてしまい、結果的に一方的な話になってしまっては、1on1の目的達成は困難となるでしょう。
雑談ばかりで終わってしまう
1on1の失敗例では、意味のない雑談に終始してしまったというケースもあります。1on1で取り上げる話題は仕事に関わることに限定されてはいませんが、かといってプライベートに関する雑談ばかりでは、内容のない場になってしまうでしょう。
目的を明確にしていない1on1の場合、このような雑談に陥ることがあります。意味のない1on1を避けるには、上司と部下双方が目的をしっかり持った上で臨むことが必要です。
話題がなくなってしまう
定期的に実施する1on1で陥りがちな失敗が、話題が尽きてしまうことです。場合によっては、以前の1on1と同じ話題の繰り返しになってしまうこともありがちです。
話題がなくなってしまうケースは、1on1が形骸化した場合に起こり得ます。ただ単純に時間を確保して一対一で上司と部下が話すだけの時間、と認識して十分な準備もせず、目的も持たずに実施してしまうと、話題はすぐになくなってしまうでしょう。

1on1の基本的な進め方

形骸的で意味のない1on1を防ぐためにも、実施する際は基本の進め方を把握しておきましょう。
部下の状態をチェックする
人事に関わる一般的な評価面談とは異なり、1on1は部下とのコミュニケーションが重要です。部下と話すことがない、部下が乗り気ではない状態で臨んだとしても、成果が出ない1on1になってしまいます。
そこでまず、上司が「調子はどうですか?」など日常的な会話を交わし、部下の状態をチェックするところから始めましょう。また、1on1を行う部下の業務内容や業務に臨む姿勢のほか、性格などもできるだけ部下の情報を把握するよう努めることもポイントです。
テーマや方向性を決める
1on1のテーマや方向性は行き当たりばったりでは意味がないので、あらかじめ設定しておきましょう。注意したいのが、上司がテーマを一方的に決めないということです。なぜなら、1on1は部下が主体となるミーティングだからです。
テーマや方向性を部下に決めてもらうためにも、1on1を実施する前に実施目的を共有しましょう。なぜ今回の1on1を行うのか、何を求めているのかを伝えた上で、テーマや方向性を部下に委ねることが大事です。
そして、1on1の目的に加えて上司と部下が業務に支障をきたすことなく無理なく実施できる日時を設定し、スケジュールも共有しましょう。
1on1の実施・フィードバック
設定した日時に、1on1を実施します。1on1で上司が押さえておきたいのが、話をするのは基本的に部下だということです。もし部下の話が途切れたり話すことがなくなったりした場合は、上司から質問を投げかけて対話が継続できるよう誘導しましょう。
1on1は部下が主体のミーティングであるため、上司が部下の話を途中で遮ること、話の内容を評価してダメ出ししたり否定したりすることも厳禁です。部下の話を受け止めて、理解や共感を示しましょう。話を聞くときはメモを取り、内容を記録すると今後の1on1での部下の課題解決状況や変化などを把握しやすくなります。

1on1のテーマ例

1on1では、あらかじめテーマを設定した上で話を進めるとスムーズに進められます。短時間で行う定期的なミーティングなので、話すテーマを用意するのが効率的です。そこで、1on1で用いられる主なテーマ例を3つご紹介します。
相互理解を促すテーマ
上司と部下が信頼関係を築くために必要なことが、相互理解です。そこで取り上げたいのが、1on1を通して相互理解を促すテーマです。
上司と部下がお互いを理解するには、仕事とは関係がないテーマで問題ありません。趣味や関心がある事柄、好きな音楽やスポーツ、気になるニュースなど、部下がリラックスして気軽に答えられるようなテーマで話し合ってみましょう。1on1を始めたばかりで話しにくいとき、話が途切れてしまったときなどは、このようなテーマで始めると話しやすくなるのでおすすめです。
モチベーション向上を促すテーマ
部下のモチベーションは、業務の成果につながるテーマとなります。まずは部下の現状からヒアリングし、業務で不安やストレスを感じていること、難しいと感じる業務の有無などから確認しましょう。部下の不安を共有して一緒に解決へ導く流れを作ると、部下のモチベーション向上につなげられるでしょう。
また、業務で悩みを抱える部下に対して、心身の状態を確認しておくこともポイントです。メンタルの悪化は、健康診断の結果ではわからない部分です。1on1で部下の心身の状態をある程度把握できていれば、メンタルの不調を未然に防ぐことも期待できます。
キャリアに関するテーマ
1on1では、現在部下が抱えている問題の解決に加えて、中長期的なキャリアについて話し合える場にもなります。近年の働き方の多様化によって、仕事に対する意識は従来のものとは大きく異なるケースもあるでしょう。
そのため、1on1では今後どのような仕事に取り組みたいか、そのためにどのような知識やスキルを身につけていきたいのかなどの現状を踏まえた内容のほか、将来目指すキャリアやチャレンジしたい仕事などについても話し合いましょう。
キャリアに関する悩みを上司と部下の間で共有して悩みを解決することで、部下のモチベーションアップや多様な働き方への対応がしやすくなる効果が期待できるでしょう。

効果的に1on1を実施するには

1on1はただ実施するだけでは期待できる効果を得ることができず、ただ時間を消費してしまうだけのミーティングになりかねません。最大限の効果を得られる1on1を実施するには、以下のポイントを意識してみましょう。
1on1実施の目的を明確化して共有する
人事評価に関わる評価面談とは異なり、1on1は短期間の間に定期的に行われるミーティングであるため、なぜ行われるのかという目的がなければ、ただ話をする場となってしまいます。
目的をきちんと理解していれば、その目的に向かって話し合いを進めやすくなるでしょう。そのため、ただ時間を無駄にするだけのミーティングを避けるためには、1on1を実施する前に目的や理由を明確化して、部下と共有した上で実施することが求められます。
上司はあくまでも聞き役に徹する
1on1は上司と部下が一対一で話す場ですが、前述したように1on1で主体となるのは部下なので、上司ばかりが一方的に話をしては、他のミーティングと大差ありません。上司は聞き役に徹して、部下の話に傾聴することを心がけましょう。
悩みや問題についてのアドバイスを求められた場合、すぐに解決策を伝えてしまうと部下が考える間がなくなってしまいます。上司は解決策を提示するのではなく、対話の中でヒントやアドバイスを出して部下が自分自身で考えて解決策を見いだせるようサポートするのも、効果的な1on1を実施するポイントとなります。
1on1面談シートを活用する
1on1は事前に準備をしておくことでより高い効果が期待できます。そこでおすすめなのが、1on1面談シートを作成して活用することです。1on1面談シートは、面談前に話すテーマや目的をまとめておくほか、ミーティング中に内容を書き留めておくことで、1on1後のフォローアップにも活用できます。
1on1面談シートに盛り込む基本的な内容は、以下の項目です。
・日時と氏名
・相談したいこと・話したいこと
・目標とやるべきこと
・2回目以降の場合は前回のフィードバック
・今回の1on1で話し合った目標ややるべきことのすり合わせ
1on1面談シートは決まった形式のものがあるわけではないので、取り上げるテーマや部下からの質問のほか、ミーティングで話す内容のポイントなどを自由にまとめて記載できます。インターネット上にはさまざまなタイプの1on1面談シートのテンプレートが配布されているので、作成する余裕がない場合は既存のテンプレートを活用してもいいでしょう。
適切なフィードバックを行う
1on1面談シートの内容としても触れたように、1on1では部下に対するフィードバックも重要なポイントとなります。上司が日頃の業務で感じた部下の評価や気づき、助言などを行います。
フィードバックがきちんと行われていないと、部下は現状改善が難しくなり、これ以上の成果を出せずモチベーションが低下し、業績の悪化を招く恐れがあります。モチベーションをアップさせて部下が持つ能力やスキルを活かすためには、適切なフィードバックが大切です。
2回目以降の1on1であれば、前回のミーティングで話し合ったことについて、これまでの成果や上司が感じたことなどを伝えましょう。

1on1を定着させるためのポイント

社内で1on1の実施がスタートしたけれど定着していない、またはこれから導入を検討しているけれど定着するかどうかが不安という場合は、以下でご紹介する3つのポイントを確認してみましょう。
目的を明確にする
1on1を定着させるためには、目的を明確にすることが最初に求められる要素です。すでに述べたように、目的がない1on1は中身のないただの雑談やミーティングに終始してしまうことがあり、1on1を実施しても何も得るものがないという事態は十分あり得ます。
目的が曖昧な状態で行う1on1は、従業員にとって「面倒」「業務の時間を割かなくてはならない」「意味があるミーティングなのか」というネガティブな印象でのスタートとなり、定期的に行うべき1on1の定着は困難となります。
そこで、なぜ社内で1on1を実施するのか、実際のミーティングを始める前に目的を明確化しましょう。具体性のある目的を持つと1on1の意義を従業員が共有できるようになり、意味のあるミーティングであることを全員が意識できます。1回1回の1on1で目的を踏まえて話ができれば意義のあるやり取りが実現し、継続・定着化につなげられるでしょう。
もし、過去に1on1を実施してみたけれど定着せず辞めてしまった企業で再開を希望している場合、従業員は「またミーティングが始まるのか」などのネガティブな印象からのスタートとなることが多いため、より定着化が厳しくなります。1on1の実施歴がある企業での再開には、入念な前準備として目的をはっきりと設定しておくとともに、定着化するための社内の仕組みの見直しなどを行ってみましょう。
1on1の内容を改善につなげる
1on1を実施しても従業員に定着している様子がない場合、内容の改善が不十分な可能性があります。1on1を導入して複数回実施していても、内容を踏まえて運用改善をしなければ、効果が出ないミーティングとなってしまうでしょう。
1on1の定着には、ミーティングの内容を元に改善へつなげる体制を構築することも必要です。1on1で出た意見や不満などを共有して問題解決へ導き、次回のミーティングでフィードバックするなどのフローを作っておくのが、1on1の内容から改善へつなげる一例です。
また、1on1のモニタリングを行ってデータ収集・解析をするのも改善策のひとつです。ツールを使用して従業員向けに1on1の実施頻度や実施時間、満足度や要望、今後継続したいかなどアンケートを取り分析しましょう。その結果から改善点や見直すべき内容を把握し、次回の1on1の改善に活かすという改善サイクルが出来上がれば、有意義な1on1の継続・定着が望めるでしょう。
定期的に実施する
冒頭でも述べたように、1on1は定期的に実施するミーティングです。つまり、継続することで効果を上げることが、1on1の定着につながります。長期間で定期的に実施してはじめて効果を実感できるといわれているため、定期的に実施することが効果を出すための最低条件といえるでしょう。
しかし、繁忙期などはミーティングに割く時間の余裕がないことがあるものです。予定通りに1on1を実施することが難しい場合は、日程を再調整してできるだけ定期的かつ継続して実施しましょう。多忙だからと上司が一方的に1on1を中止、または日程の再調整をしてしまうと、部下の信頼関係に悪影響を及ぼす可能性があります。一方的な予定変更を避け、部下とともにスケジュールを再調整することが重要です。
また、従業員一人ひとりが1on1を企業の文化のひとつとして認識することが、1on1を定着させるためのポイントとなります。そのためには、広報役の従業員を配置して1on1を企業文化として浸透させる取り組みとして社内で1on1についての情報発信を行うなどの工夫も必要でしょう。企業全体でこのような活動をすることで、企業文化としてすべての従業員が通常業務の一つとして捉えられるまでに1on1が浸透する流れを作れるでしょう。

まとめ
VUCA時代を迎えているといわれる現在、働き方の多様化や従来とは異なる職場環境など、企業内ではこれまでの方法では対応しきれない場面も増えているかもしれません。
オープンに話し合える場を作れる1on1は、部下が主体となって行われるので部下の主体性を育む効果とともに、上司と部下がお互いに理解して信頼関係を構築し、部下の不満や問題の解決や成長のサポート、組織力の強化などの良い効果が望めるミーティングです。
短時間でも定期的に実施する必要があるため、多忙な企業では実施が厳しい場合もあるでしょうが、明確な目的を設定して効果的な1on1を企業文化として定着できれば、より良い職場環境や信頼関係の構築が、多方面に良い効果として現れるでしょう。
福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>


はたらく人を元気にする会社

グループ間協力で、売店・食堂・企業内福利厚生をワンストップでサポートいたします。売店とカフェの併設や24時間無人店舗など、個々の会社では難しい案件も、グループ間協力ができる弊社ならではのスピード感で迅速にご提案します。
心幸グループ WEBSITE