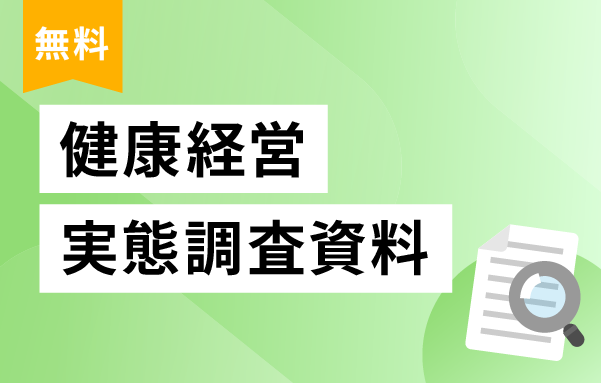感染症予防と対策|コロナ・百日咳など最新の流行状況と職場でできる基本の備え

こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。
感染症は、職場で大きなリスクとなりえます。昨今よく耳にする「新型コロナウイルス」や「百日咳」などの呼吸器系疾患は、集団生活を送る職場環境で感染拡大を引き起こす危険も伴うものです。
そこで本記事では職場における感染症の基本的な予防対策と、職場で実践できる具体的な備えについて現場の目線から解説します。
福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉
目次
【手洗い・消毒・マスク・換気等】 感染症の基本的な予防対策とは?

感染症を予防するためには、基本的な対策がとても重要です。
職場でも継続して実践すべき基本の対策には、次のものがあげられます。
・手洗い・手指消毒:ウイルスや細菌は手を介しても広がるため、こまめな手洗いやアルコールによる手指消毒が効果的です。
・マスクの着用: 飛沫感染を防ぐため、特に人が密集する場所や空間ではマスクの着用が推奨されます。
・換気の徹底: 空気感染を防ぐために、定期的な換気が必要です。
・体調管理と早期受診: 発熱や咳などの症状が現れた場合には無理をせずに自宅待機し、早期に医療機関を受診しましょう。
【飛沫感染・接触感染・空気感染】 職場内における感染経路を正しく理解する
感染症が広がりやすい経路を理解し、職場において適切な措置を講じていきましょう。
主な感染経路は次の3つです。
・飛沫感染: 咳やくしゃみなどで飛び散る飛沫を吸い込むことによって感染します。
・接触感染: 感染者が触れた物品や場所を介して感染します。
・空気感染: エアロゾルと呼ばれる微細な粒子が空気中に浮遊し、それを吸い込むことで感染します。
【手洗い・マスク・換気】 感染対策・予防の「三本柱」を徹底する
感染の広がりを抑え込むために、職場での対策を徹底しましょう。
実践すべき具体的な方法は、次の「三本柱」です。
1・手洗い: 職場内に手洗い場やアルコール消毒液を設置し、従業員にこまめな手洗いを促します。同時に、手指消毒の徹底もできると尚良しでしょう。
2・マスクの着用: 普段は推奨にとどめ、人が集まる会議室や休憩室などではマスクの着用を義務付けるなど感染拡大状況を見ながら柔軟なルールを設けるのも方法です。
3・換気の確保: 定期的に窓を開ける、または換気扇を使用して室内の空気を入れ替えるなどして、新鮮な空気を取り込みましょう。
このほか従業員に対しては体調不良時の早期帰宅や医療機関の受診を促したり、最新の感染症情報を提供したりするのも効果的な対策です。

【2025年版】最近流行している感染症の特徴と注意点

2025年秋現在、特に職場や学校などの集団生活において注意すべき感染症が増加しています。
現在流行している主な感染症の特徴と予防対策をまとめました。
【2025年秋は「ニンバス」の症状に注意!】 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
2025年秋、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染者数は再び増加傾向にあります。
流行している主な変異株は、オミクロン系統の「ニンバス」で、感染力が非常に強く強い喉の痛みが特徴です。そのほかの主な症状は、鼻水、咳、発熱、倦怠感などの上気道症状で、味覚・嗅覚障害は以前よりも少なくなってきています。
なお重症化リスクは低めですが、高齢者や基礎疾患のある人は引き続き注意が必要です。
飛沫感染と接触感染が主な感染ルートです。
【乳幼児・高齢者は重症化に注意!】 百日咳
百日咳は百日咳菌による急性気道感染症で、いずれの年齢でもかかるものの子どもを中心に流行しています。特に乳幼児や高齢者で重症化する可能性が低くないために侮れない感染症です。
初期は風邪のような症状から始まって、次第に激しい咳(特有のけいれん性の激しい咳発作である痙咳発作:けいがいほっさ)に進行するのが大きな特徴で、数週間から数ヶ月も咳が続く症例もあります。
こちらも、飛沫感染や接触感染が主な感染ルートです。
【インフルエンザ・溶連菌・RSウイルスなど】 その他の流行感染症
2025年秋現在では、インフルエンザや溶連菌感染症、RSウイルスも一定の流行をしています。
すでに2025年9月には例年より早く全国各地でインフルエンザによる学級閉鎖が実施されているほか、一部の地域では溶連菌感染症やRSウイルスも増加しています。
溶連菌感染症は子どもを中心に流行しやすく、RSウイルスは乳幼児や高齢者で重症化するリスクがあります。
なお、溶連菌感染症もRSウイルスも主な感染ルートは飛沫感染と接触感染です。
★職場に大ダメージを与えかねない「ノロウイルス」にも厳重警戒を!
過去のコラム「企業・個人で取り組むノロウイルスへの感染予防・対策法とよくある疑問Q&A」では、社内に感染者が出るとダメージが大きい「ノロウイルス」について詳しく解説しています。
こちらも併せてチェックしてみてください。

【従業員に健康と安心を】 職場でできる具体的な感染症対策

職場では、従業員が安心して働ける環境を整えることが感染症対策の基本です。
日常的に取り組める具体的な方法を解説します。
基本の衛生管理を徹底する
職場の入口や会議室、共有スペースにアルコール消毒液を設置してこまめな手指消毒を促す「手指消毒の徹底」や、咳やくしゃみをする際はマスクやハンカチ・ティッシュで口と鼻を覆って飛沫拡散を防ぐ「マスク・咳エチケットの徹底」など、基本的な衛生管理の徹底が感染症対策に効果的です。
感染症対策を風化させないよう、定期的に周知を行うなどして従業員の意識を高めていきましょう。
また、正しいワクチン接種の知識を提供する活動も有益です。
出社ルールを整備する
発熱や咳などの症状がある従業員には無理な出社を避け、自宅で休養するよう促す「体調不良時の休暇取得」や、感染リスクが高い時期にはオンライン会議や在宅勤務を活用して、職場での接触を減らす目的でのテレワークやオンライン会議の活用は非常に効果的です。
また、定期的に感染症情報や注意喚起を社内報やメールで共有すると、従業員の意識向上を図れます。
福利厚生・感染対策への備品を適切に整える
従業員が自分で手指消毒や体温測定を行えるように職場に常備するほか、体温計も備えておきましょう。
休憩室や食堂においても座席の配置を工夫しソーシャルディスタンスを意識して座席の間隔を空けて配置すると、飛沫感染リスクを低減します。
また、加湿器や空気清浄機の導入も積極的に検討したいテーマです。室内の空気環境を整えることでウイルスの浮遊リスクを抑え、快適な職場環境を作ります。

【流行期だけではNG!】 企業がとるべき季節や流行に応じた備え

感染症対策は、流行期だけではなく一年を通じて必要です。季節によってリスクや流行する疾患が異なるために、備えのポイントも変わります。
冬季と夏季における職場での対策を整理しておきましょう。
【加湿と換気がポイント!】 冬季の備え
冬は空気が乾燥しますので、インフルエンザやコロナウイルスなどの呼吸器感染症が流行しやすくなる傾向にあります。
そのため職場など人が集まる空間で特に重要なのが、加湿と換気の両立です。
加湿器を設置して室内の湿度は40〜60%に保つのが理想的で、同時に定期的な換気も行ってウイルスの滞留を防ぎましょう。
また、感染を拡大させないために社食や給湯室での衛生対策も意識すべきです。共用のマグカップや食器の利用は避け、ペーパータオルや個包装の食器類を導入し、食堂や休憩室ではテーブルやドアノブを定期的に消毒しましょう。
関連記事:【10選】オフィスの乾燥対策|加湿器以外の方法も伝授!目や顔の潤いアップ
【高温多湿対策と換気がポイント!】 夏季の備え
夏は高温多湿の環境によって細菌やウイルスが繁殖しやすく、食中毒や胃腸炎などの感染症が増加します。
また、昨今では夏季でもインフルエンザや新型コロナウイルスの感染者が増加傾向にあることから、エアコンを使っていても換気を徹底する意識が求められます。
食品の保管温度は適切に管理し、冷蔵庫の清掃や温度チェックを徹底しましょう。食品提供による衛生管理も重要で、社食や給湯室では調理器具やまな板をこまめに消毒し、従業員には手洗いを徹底させましょう。
弁当の仕出し業者を利用する場合には、衛生基準を確認しておくと安心です。

【長期的に取り組む必要性】 企業における感染症対策の課題と今後の展望

感染症対策は一過性のものではなく、長期的に取り組む必要があります。
しかし時間の経過とともに従業員の意識が低下したり、コストや運用の負担が課題となっている現実も見受けられます。感染症対策において企業が直面しやすい課題と、今後の展望について整理します。
【対策を形骸化させない】 予防意識の風化を防ぐ
感染症の流行が落ち着くと、従業員のあいだでは「もう大丈夫」と油断が生じやすく、対策が形骸化する恐れがあります。
定期的な衛生研修や社内ポスター・社内報による情報発信を続けることで、従業員の意識を維持していきましょう。
実践的な訓練やシミュレーションを取り入れるのも有効です。実際の感染症流行時を想定した訓練を行うと、マニュアルが形だけにならず迅速な対応が可能になりやすいだけでなく、意識の風化を防げます。
また、経営層のリーダーシップも求められています。トップダウンで感染症対策を推進する姿勢を示すことによって、従業員の行動変容を促し予防意識の定着につながるでしょう。
【コスト対策にも】 災害時との備蓄の兼用を検討する
感染症への備えは、コスト面も考慮して災害対策と並行して進めましょう。マスクや消毒液は、感染症対策と防災対策の両方に役立ちます。また、保存食や飲料水も災害時・パンデミック時の両面で必要となるため、共通の備蓄として計画的に管理すると合理的です。
気をつけるべきは、賞味期限や使用期限の管理です。保存食やアルコール消毒液には使用期限があるため、定期的に入れ替える「ローリングストック方式」を導入し、常に新しい状態で備蓄できる体制を整えましょう。
さらに、感染症流行時にはサプライチェーンの確保も課題になりがちです。災害だけでなく感染症の流行時にも物資不足が起きやすいため、複数の仕入れ先を確保するなど安定的に備品を供給できる体制を作っておくことも今後の課題です。

【まとめ】企業の感染症対策は「継続」と「仕組み化」がポイント
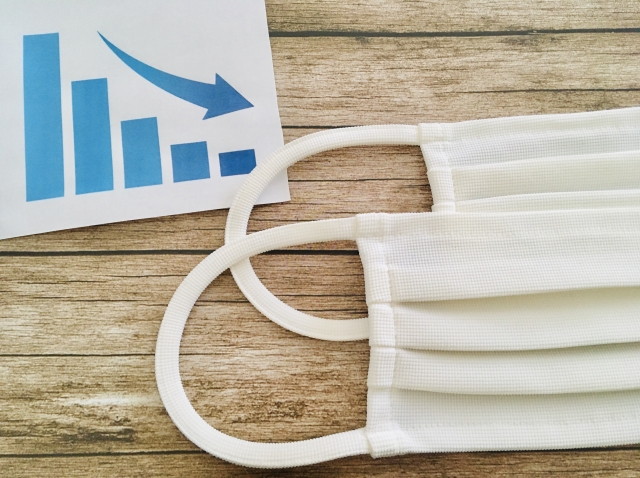
感染症対策では、新型コロナウイルスや百日咳といった流行の変化だけでなく季節ごとにリスクも異なるため、企業には常に柔軟で実効性のある対策が求められています。
基本となるのは 「手洗い・マスク・換気」などの三本柱の徹底。これに加え、職場環境の衛生管理や出社ルールの整備、福利厚生制度や充実した備品の準備も必要です。
一方で感染症対策は時間の経過とともに風化しやすく、継続的な教育や備蓄の工夫は課題です。企業としての危機対応力を高める視点からも、感染症対策を風化させるべきではないでしょう。
「一時的な取り組み」ではなく企業の健康経営やリスクマネジメントの一環として日常的に組み込むのがポイントで、従業員の安全を守る仕組みづくりが業務の継続性や企業の信頼向上にも直結します。
福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>


元気な会社は社員が元気!健康経営サポート

オフけん(運営:心幸ウェルネス)では、「健康経営優良法人」認定取得サポートを中心に、企業の健康経営をバックアップしています。形だけの健康経営ではなく、従業員の健康と幸福に真剣に向き合う取り組みを提案。真の健康経営を実現しています。「からだ測定会」では、体成分測定・体力測定により従業員一人ひとりのからだ年齢が明らかに!他にも、健康セミナー、禁煙サポートなどのサービスを通して、従業員の健康意識を向上させ、元気な会社づくりに貢献します。
オフけんはこちら