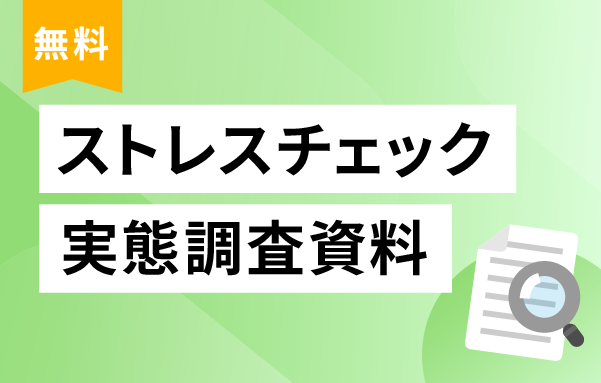健康経営におけるストレスチェックの重要性5選!従業員のメンタルヘルスに寄り添った実施方法も紹介

こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。
近年、従業員のメンタルヘルス不調を未然に予防するにあたって、健康経営の導入は必要不可欠です。
健康経営とは、企業が従業員の健康管理を経営課題の一つとして位置づけ、戦略的に実践するための経営のあり方です。
中でも、従業員一人ひとりのストレス状態を把握できるストレスチェックは、個人の課題だけでなく、企業全体の課題も明らかにできます。
この記事では、健康経営を推進するうえでのストレスチェックの重要性や効率的な活用方法などをわかりやすく解説します。
健康経営を加速させるにあたり、ストレスチェックを実施したい企業の担当者は、ぜひ最後までご覧ください。
福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉
目次
健康経営におけるストレスチェックの基本情報

最初に、健康経営の推進に欠かせないストレスチェックの概要について紹介します。
健康経営におけるストレスチェックとは?
そもそもストレスチェックとは、従業員が健康的に働き続けられるよう、心の健康状態を定期的に把握する検査のことです。
ストレスチェックを実施することで、従業員は自らストレスに気づき、速やかにセルフケアを行えます。
一方で企業側は、組織全体でストレスチェックの結果を分析し、より良い職場環境へと改善するきっかけになります。
関連記事:ストレスチェックの義務化|いつから?罰則は?概要・手順を解説
関連記事:ストレスチェックとは?義務化対象拡大の目的と導入・実施方法を解説
ストレスチェックを実施する目的
ストレスチェックは、長時間労働や人間関係の悩みによるうつ病や適応障害などの増加を受け、従業員のメンタルヘルス不調を前もって防止するために導入されました。
近年、労働者全体の約6割が強いストレスを感じているという調査結果もあり、企業にとっても見過ごせない状況です。
ストレスチェックは、年に一度の質問票調査を通して従業員の心理的負担を測り、その結果に基づいて高ストレス者と判定された従業員には医師による面接が行われます。
その他にも、以下のような目的で実施されます。
・従業員のストレス把握:従業員自らのストレス状況を認識し、セルフケアを踏み出すきっかけとなる
・メンタルヘルス不調の予防:ストレス解消やカウンセリング等で次のステップに進みやすくして、メンタルヘルス不調を予防する
・職場環境の改善:従業員のストレス傾向を分析し、企業全体の課題を特定して、職場環境を改善するための具体的な対策を講じる
このように、従業員のストレスを把握し従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことで、働きやすい職場と生産性向上を実現できます。
ストレスチェックの実施義務と対象企業
ストレスチェックは、2015年に労働安全衛生法が改正され、従業員が50人以上の事業場には実施が義務付けられました。
そして、2025年のさらなる改正によって、今後は従業員数や業種などにかかわらず、すべての事業場が対象となる見込みです。
2025年現在、従業員が50人未満の事業場は努力義務ではあるものの、今後3年以内でストレスチェック実施が義務化されます。
健康経営における重要な要素であるストレスチェックは、今のうちから導入への準備を進めておく必要があります。
関連記事:ストレスチェックが義務化になる!?企業が知るべき実施方法と注意点をご紹介
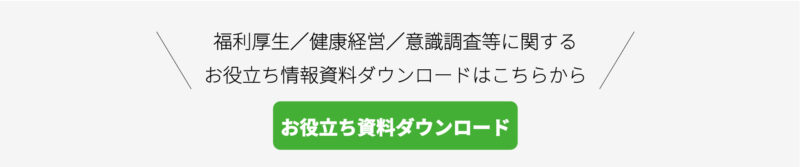
企業が健康経営におけるストレスチェックを実施する重要性5選

ここでは、健康経営の推進に欠かせないストレスチェックの重要性について紹介します。
・職場環境が改善する
・生産性が向上する
・優秀な人材の流出を防げる
・メンタルヘルス不調による労働損失を抑制できる
・企業のイメージアップにつながる
それぞれ順を追って解説します。
職場環境が改善する
企業は、従業員の健康維持に対して積極的に取り組み、働きやすい環境を提供することで、従業員の満足度を高められます。
これにより、従業員は企業への安心感や信頼感が増し、結果として定着率の向上につながります。
特に、優秀な人材の確保と定着が企業の競争力を左右する現代において、ストレスや健康リスクの高い職場は従業員の離職を招きやすいです。
そのため、従業員の健康に配慮した労働環境を整備することは、長く働き続けてもらうためにも重要な要素です。
生産性が向上する
従業員の健康状態が企業の生産性に直接影響することは、さまざまな研究や資料で明らかになっています。
従業員の健康状態を維持・改善させることで、従業員の仕事達成感を維持、上昇させられると言える。
引用元:独立行政法人 労働政策研究・研修機構|従業員の健康状態と労働意欲 中小企業における健康経営の意義
心身ともに健康的な従業員はストレスが少ない傾向にあるため、業務に集中し優れたパフォーマンスを安定して発揮しやすいです。
反対に、体調不良や過度なストレスを抱えている従業員は、集中力が散漫になることで業務の遅延やミスが増え、結果として生産性の低下を招きます。
健康経営を通して従業員が健康的に働ける環境を整えることで、従業員のモチベーションが高まり、業績改善や売上増加にも貢献するでしょう。
優秀な人材の流出を防げる
現代の労働市場で優位に立つためには、優秀な人材をいかに確保して定着させるかが鍵です。
ストレスや健康リスクが高い職場環境では、従業員は心身ともに疲弊して転職を考える可能性が高まります。
そのため、企業が従業員の健康を踏まえて働く環境を整備することで、従業員は長期にわたって働き続けやすくなります。
そして、従業員による採用や研修・セミナーに関わるコストを抑えることが可能です。
メンタルヘルス不調による労働損失を抑制できる
従業員の健康管理を徹底することで、病気の予防や早期発見につながり、メンタルヘルス不調による労働損失を抑制できます。
特に、慢性的な病気の予防やメンタルヘルスケアをするのが効果的です。
具体的には、企業が定期的な健康診断や健康指導を実施し、従業員が自身の健康状態を把握しやすい環境を整備することが重要です。
病気や怪我のリスクが減ることで、中長期的な休職や業務離脱を防げ、欠勤や労災による損失リスクを抑えられます。
このように、従業員の健康維持への投資は、労働損失の抑制にもつながり、企業全体の業務効率向上をもたらします。
企業のイメージアップにつながる
健康経営に積極的に取り組む企業は、消費者や求職者、さらには金融機関や国・地方自治体といったあらゆるステークホルダーから高い評価を得やすいです。
そして、社会的責任を果たす企業として、社会貢献度や価値が高いということで好印象を持たれます。
実際に、従業員の健康に関する施策は地域社会や業界全体への貢献にもつながり、企業のブランドイメージを大きく高める効果が期待できます。
さらに、国や地方自治体の健康経営認定制度に参加して受賞すれば、企業の信頼性がさらに向上するでしょう。
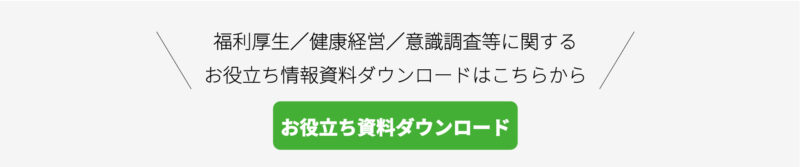
健康経営を加速させるストレスチェックの実施方法と流れ

ストレスチェックを実施する際は、以下の流れで行いましょう。
・実施前の準備と体制構築
・ストレスチェックの実施とデータ管理
・実施後の分析・活用とフォローアップ
それぞれ順を追って解説します。
実施前の準備と体制構築
ストレスチェックを実施するにあたり、質問内容の決定やスケジュールの策定が必要です。
具体的には、以下の項目を事前に決めましょう。
・いつ・誰に対して行うか
・どのような質問票を使用するか
・高ストレス者の判定方法
・面接指導の申し込み先
・面接指導を依頼する医師
・集団分析の実施方法
・結果の保管場所と担当者
そして、ストレスチェックをスムーズに進めるためにも、各担当者の役割分担も明確に設定します。
・制度全体の担当者:スケジュール管理や全体の進捗を把握
・ストレスチェックの実施者:医師や保健師、厚生労働省による研修を受けた看護師など有資格者が担当
・実施事務従事者:質問票の回収やデータ入力など、個人情報を取り扱う事務作業を担当
・面接指導医:産業医をはじめ、高ストレス者との個別面談・相談を担当
質問票を作成する際は、厚生労働省が公開している「職業性ストレス簡易調査票(80項目版)」が役立ちます。
ストレスの原因、心身の自覚症状、周囲のサポートに関する設問が含まれています。
また、あらかじめ従業員へ制度の目的やルールを周知することも重要です。
企業は従業員に対して、本人の同意なしに結果を閲覧できないことや面接指導の利用方法について、そして結果が人事の評価に影響しないことなどを丁寧に説明しましょう。
ストレスチェックの実施とデータ管理
一通り準備を終えたら、企業は従業員に質問票を配布し、回答を記入してもらいます。
使用する質問票に特別な指定はありませんが、何を使用すれば良いかわからない場合は、無料で利用できる「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」をダウンロードしましょう。
ITシステムを利用して、オンラインで実施することも可能です。
回答済みの質問票は、医師をはじめとした実施者または実施事務従事者が回収します。
その際、人事権を持つ担当者や第三者は、回答済みの質問票の中身を閲覧してはいけません。
回収後、実施者がストレスの程度を評価し、高ストレス者を選定します。
高ストレスで指導が必要な人の特徴として、以下のことが挙げられます。
・自覚症状が高い人
・一定の自覚症状があり、かつストレスの原因や周りからのサポート状況が著しく悪い人
高ストレスと判断された従業員には、医師による面接指導を勧める必要があります。
選定基準がわからない場合は、厚生労働省の「ストレスチェック制度実施マニュアル」の基準を参考にしましょう。
ストレスの程度の評価結果や医師による面接指導が必要か否かなどを記載した結果は、実施者から直接従業員に通知されます。
その際、企業側が結果を入手するには、本人の同意が必須となります。
そして、通知後の結果は実施者が責任をもって厳重に保管しなければなりません。
企業内にあるキャビネットやサーバー内で、鍵やパスワードを付けて保管しましょう。
実施後の分析・活用とフォローアップ
ストレスチェックの実施後は、医師による面接指導を実施したり、その後の職場改善に向けたルールを定めたりして、職場改善に役立てることが重要です。
ストレスチェックの結果、「医師による面接指導が必要」とされた従業員から申し出があった場合、企業は速やかに医師による面接指導を依頼し、実施しなければなりません。
従業員は結果通知から1か月以内に申し出る必要があり、企業は申し出から1か月以内に面接指導を行う義務があります。
そして、面接指導を行った医師から労働時間の短縮や職場環境の改善をはじめ、就業上の措置の必要性と内容について意見を聴取し、出てきた意見に基づいて必要な対応を実施します。
その際、医師からの意見聴取は、面接指導後1か月以内に行わなければなりません。
面接指導の結果は、事業所にて5年間保存する義務があり、以下の内容があれば医師からの報告書をそのまま保存することも可能です。
・実施年月日
・従業員の氏名
・面接指導を実施した医師の氏名
・従業員の勤務状況、ストレスの状況、その他の心身の状況
ストレスチェックの結果が一通り判明したら、結果に基づいて職場分析と職場環境の改善(努力義務)を行いましょう。
ストレスチェックの実施者に対して、結果を部署やグループといった一定規模の集団ごとに集計・分析し、その結果を提供してもらいます。
その際、集団に応じて質問票の項目ごとの平均値といった数値を比較することで、どの集団にどのようなストレス要因が潜んでいるかを分析できます。
ただし、集団の人数が10人未満の場合は、個人が特定されるリスクがあるため、原則として全員の同意がない限り、結果を提供してはなりません。
その後、分析結果をもとにそれぞれの集団が抱えるストレスの状況を具体的に把握し、職場環境の改善策を検討・実行します。
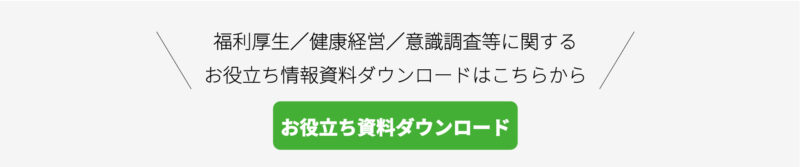
ストレスチェックの結果を健康経営に活かす効率的な方法

ストレスチェックを実施して結果を効果的に活かすためにも、以下の方法を実践しましょう。
・デジタル化を進める
・個人ではなく集団で分析を行う
・改善箇所を検討する
・課題解決に向けて施策を実施する
・効果検証する
ただストレスチェックを実施するのではなく、従業員からの結果を自社の健康経営に活かすことが大事です。
デジタル化を進める
ストレスチェックの運用を効率化するためには、Web対応のツールを活用するのがおすすめです。
紙ベースではなくシステム上でストレスチェックを実施することで、従業員はいつでもどこでも受検でき、回答率の向上につながります。
また、データの集計や分析も速やかに行えるため、担当者の負担を軽減することが可能です。
これにより、紙の印刷費や配布・回収にかかる時間も削減でき、コスト削減にも貢献します。
個人ではなく集団で分析を行う
ストレスチェックは、個々の結果だけを見るのではなく、部署やチームごとの集団分析が重要です。
集団の傾向や特性を把握することで、組織全体が抱えるストレス要因を特定し、効果的な改善策を見つけられます。
特に、高ストレス者が多い部署は離職リスクも高まるため、早急な組織改善が求められます。
より効果的に改善するためにも、集団分析に強みを持つ外部業者を選定して、より本質的な課題解決につなげましょう。
改善箇所を検討する
ストレスチェックの実施後は、結果の分析に基づいた改善策の立案と実行が不可欠です。
たとえば、長時間労働がストレスの要因として明らかになった場合は、勤務体制の見直しを検討します。
ストレスチェックは専門的な知見が必要な領域になるため、自社のリソースだけでは詳細な分析が難しいケースがあります。
そのため、専門家のアドバイスに基づき、ストレスチェックの結果に沿った効果的な健康経営を促進することが重要です。
課題解決に向けて施策を実施する
具体的な施策を実行する際は、組織の特性や課題に応じて、以下のような取り組みの主体を検討しましょう。
・経営者主導型:全社的な制度導入や費用を伴う施策をトップダウンで実現する
・専門職主導型:外部の専門家を活用し、特定の部署へのヒアリングやケアを提供する
・管理職主導型:チームの分析結果を管理職が共有し、現場主導で改善プランを立案する
・従業員参加型:チームメンバー全員で結果を共有し、全員で改善策を検討する
特に、現場主導で行う管理職主導型や従業員参加型は、従業員が課題を自分ごととして捉え、本質的な改善につながりやすいです。
効果検証する
施策を実行したら、必ず効果検証や次年度以降のフォローアップを行いましょう。
前年度に実施したストレスチェックの結果を比較したり、施策の実施後に簡単なアンケートを実施したりすることで、取り組みの効果を測定します。
改善が成功した導入事例や取り組み、困難だったものを次年度の施策に活かすことで、効果的な健康経営を実現できます。
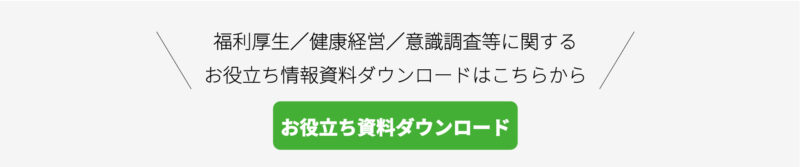
健康経営におけるストレスチェックの注意点

ストレスチェックを実施する際は、以下の注意点を意識しましょう。
・従業員に受験を強制しない
・プライバシーの保護を徹底する
・結果によって不利益な扱いはしない
・正直な回答を出せる環境を構築する
それぞれ順を追って解説します。
従業員に受験を強制しない
ストレスチェックは現状、従業員50人以上の事業所で実施が義務付けられているものの、従業員が受けるかどうかは任意です。
義務化されているのはあくまでもストレスチェックの「実施」であり、従業員が「受検」する義務はありません。
そのため、企業は従業員に対して、社内の会話や教育の場で勧めるのは問題ないものの、ストレスチェックを受けるよう強制してはなりません。
従業員が受検をためらう理由として、業務が忙しいことや結果が人事評価に影響するのではないかという懸念が挙げられます。
なぜ受けたくないのかを話し合って懸念点を払拭することで、ストレスチェックの受験率が上がり、職場環境の改善につながるヒントが得やすくなります。
プライバシーの保護を徹底する
ストレスチェックでは、個人のデリケートな情報が扱われるため、プライバシーの保護を徹底することが重要です。
面談では、既往歴や他人に打ち明けたくない悩みなどを話すことがあります。
そのため、情報管理には細心の注意が必要です。
事前に従業員への十分な説明や教育が不足していると、意図せず情報が漏洩したり、データが不適切に扱われたりするリスクが存在します。
そのため、従業員が安心して受検できる環境を整えることが求められます。
結果によって不利益な扱いはしない
ストレスチェックの結果によって、従業員に不利益な扱いをすることは禁止されています。
また、受検を拒否したことや面接指導を利用しなかったことなども同様です。
ストレスチェックの受検や結果を会社に伝えること、医師による面接指導を希望するかは、すべて従業員の意思に委ねられています。
企業側が実施することは、安心して制度を利用できる環境を整え、得られたデータから組織全体の改善点を見つけ出すことです。
正直な回答を出せる環境を構築する
ストレスチェックを実施する際は、従業員が正直に回答できる環境を構築しましょう。
以下のような状態で懸念から虚偽の回答をしてしまうと、正確なストレス状態を把握できず、適切な対策が取れなくなります。
・業務が忙しくて回答時間が取れない
・面接で業務が止まって支障をきたす
・評価が下がって給料の減額や解雇されるのではないか
そのため、従業員が安心して正直に答えられるよう、実施の目的や結果の共有範囲、データの活用方法などについて、事前に十分な説明を行いましょう。
特に、本人の同意がなければストレスチェックの結果が上司に伝わらないことを明確に伝えることは、従業員が正直に回答するうえで大切なポイントです。
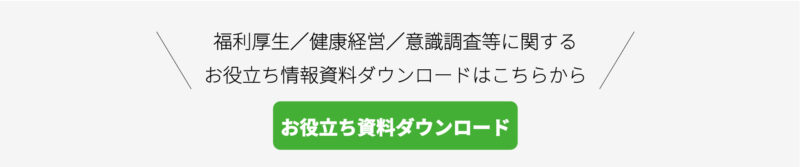
まとめ:ストレスチェックを実施して健康経営を効果的に進めるためには「オフけん」アプリがおすすめ!

健康経営を成功させるためには、ストレスチェックの結果に基づいて従業員自身が健康を意識し、行動できる環境を整備することが重要です。
ストレスチェックを実施する際は、オフィス業務のデジタル化にならって、パソコンやアプリで利用できるツールを導入しましょう。
その中でおすすめなのが、健康経営をサポートするアプリ「オフけん」です。
オフけんの体調管理アプリは、厚生労働省が推奨する項目を網羅したストレスチェックに対応しており、紙ベースよりも効率的に情報を扱えます。
結果は自動でデータ化され、ペーパーレスでの管理が可能です。
もちろん、ストレスチェックだけでなく、健康に関連した各種サービスも利用できます。
加えて、小規模な事業所であってもコストを抑えて気軽に導入できるよう、事業所単位での料金プランが用意されているため、コスト面での負担も抑えられます。
時間や手間をかけずに従業員の健康管理を徹底したいなら、ぜひこの機会に「オフけん」アプリの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>

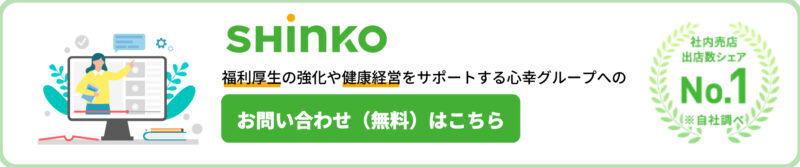
元気な会社は社員が元気!健康経営サポート

オフけん(運営:心幸ウェルネス)では、「健康経営優良法人」認定取得サポートを中心に、企業の健康経営をバックアップしています。形だけの健康経営ではなく、従業員の健康と幸福に真剣に向き合う取り組みを提案。真の健康経営を実現しています。「からだ測定会」では、体成分測定・体力測定により従業員一人ひとりのからだ年齢が明らかに!他にも、健康セミナー、禁煙サポートなどのサービスを通して、従業員の健康意識を向上させ、元気な会社づくりに貢献します。
オフけんはこちら