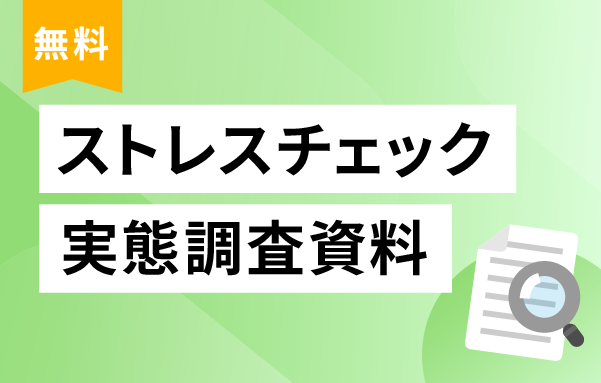健康経営アプリの選び方と導入メリットを企業現場の目線で解説

こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。
働き方の多様化や人手不足が進む今、企業にとって人材を「いかに健康に・長く働ける状態で維持するか」は、経営上の最重要課題のひとつです。
こうした背景から注目を集めているのが従業員の健康データを見える化し、組織全体のコンディションを継続的に改善できる「健康経営アプリ」です。
健康経営は、単なる福利厚生の一環ではありません。
本記事では健康経営の基本的な考え方から、アプリ導入のメリット・選定時のチェックポイントを実際の企業現場の目線でわかりやすく解説します。
福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉
目次
健康経営アプリの重要性と背景

企業の競争力を支えるのは「人の健康」です。
働き方の変化やメンタル不調の増加によって、健康経営の必要性は年々高まっています。
まずは健康経営の基本的な考え方と、企業にもたらす具体的なメリットを整理しましょう。
【企業向けに解説】 「健康経営」とは何か
「健康経営」という言葉は近年、企業経営や人事戦略のキーワードとしても頻繁に耳にするようになっていて、単なる福利厚生の一環ではなく従業員の健康を経営資源として捉え、積極的に投資・管理していく考え方を指します。
従来は「病気になったら治療を支援する」スタンスが主流でしたが、現代は働き方や社会情勢の変化によって“予防”と“メンタルケア”の重要性が高まっています。
経済産業省が推進する「健康経営優良法人」認定制度も広く知られるようになり、健康経営は企業価値の向上やブランド戦略の一部としても注目を集めています。
中小企業でも「人手不足の時代だからこそ、従業員に長く働いてもらうための基盤づくり」として、健康経営への投資を始める動きが加速しています。
健康経営が企業にもたらすメリット
健康経営の導入には、目に見える「コスト削減効果」と、長期的な「組織力強化」という二つの側面があります。
最も分かりやすいのが医療費・休職コストの削減で、横浜市立大学大学院国際マネジメント研究科の原 広司准教授(COI-NEXT拠点Minds1020Lab研究開発課題6リーダー)と、産業医科大学産業生態科学研究所の永田 智久准教授との共同研究によれば、日本全体では年間およそ7.6兆円の経済的な損失が生じていることがわかっています。(出典:メンタル不調の影響、年間7.6兆円の生産性損失に―GDPの1.1%に相当と試算)
企業規模で見れば、数百万円~数千万円規模の“見えない損失”が発生しているケースも珍しくないでしょう。
定期的な健康チェックやストレス測定、早期フォロー体制を通じて、発症前にリスクを察知して重症化を防ぐ術につながります。
また、健康経営は生産性やエンゲージメントの向上効果や採用市場におけるブランド力の向上もメリットです。
心身ともにコンディションが整った社員は集中力・創造力が高まって業務効率も上がりますし、「働きやすさ」「健康への配慮」を重視する傾向が強い求職者からは、健康経営に積極的な企業は「安心して働ける会社」の信頼を得やすい実態もあります。
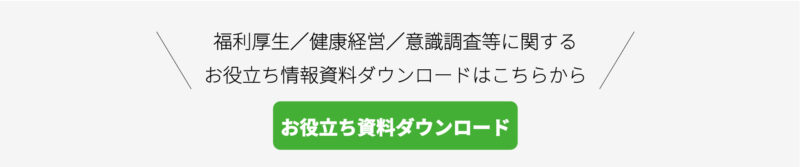
【導入事例をもとに分析】 健康経営アプリの機能と特徴

健康経営アプリは従業員の健康状態を「見える化」し、企業の健康施策を支援する多機能ツールです。
すでに一般的になっている機能のなかから、導入時に特に注目すべき主要機能を3つの観点から整理します。
【セキュリティ対策と個人情報保護】データ管理機能の重要性
健康経営アプリの導入において、最も重要視すべき要素のひとつがセキュリティと個人情報保護です。
従業員の健康データには、病歴・生活習慣・メンタル状態などの極めて機微な情報が含まれます。これらを適切に取り扱わなければ、企業の信頼を損なうだけでなく法的なリスクを招くおそれもあります。
そこで、アプリ選定の際にはまずデータの保存・通信における暗号化が実施されているかを必ず確認しましょう。
多くの優良アプリでは「SSL/TLS通信」の採用や、サーバーの国内保管、アクセス権限の分離管理などを行っています。
また、個人を特定できない形でデータを統計的に処理する「匿名化機能」も、安全性を高める上で有効です。
なお、プライバシーマークやISMS認証の有無も信頼性を測る重要な指標です。
【食生活・体重もセルフチェックできる】 健康サポート機能の多様性
健康経営アプリの中心となるのが、従業員一人ひとりの健康を支援する機能です。年々進化をしていて、「健康診断結果の管理」だけでなく日常の行動データを取り込み、予防的なケアを促す機能が主流となってきています。
アプリにある歩数や消費カロリー、睡眠時間などのライフログ記録や食事内容や栄養バランスを自動解析する食事管理機能、食事内容や栄養バランスを自動解析する食事管理機能などの機能を通じて、従業員は「健康維持を意識する機会」を日常的にもちやすく、これらのデータを個人単位だけでなく部署・年齢層・職種ごとに集計すれば、組織全体の健康傾向を可視化しやすくなります。
【従業員が主体的な取り組む】 インセンティブ機能の活用
健康経営を定着させる上での最大の課題は「続けてもらうこと」。高機能なアプリでも、従業員が日常的に利用しなければ意味がありません。
そこで注目したいのが、インセンティブ機能の活用です。
例えば歩数や睡眠、イベント参加などの成果に応じてポイントが付与され、そのポイントを社内カフェのクーポンや電子ギフトに交換できる仕組みには、健康行動が従業員の“楽しい・得をする体験”となって自発的な参加意欲を引き出す効果が見込めます。
なお、アプリの利用状況を分析して参加率や成果を可視化できる管理画面があると、企業側も施策効果を測定しやすくなるでしょう。
インセンティブ機能を単なる「おまけ機能」や「お得機能」としてではなく、継続と組織文化づくりを支える仕掛けとして活用するのがポイントです。
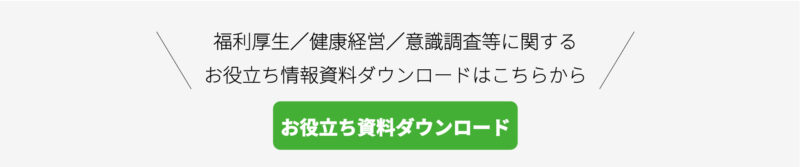
【実現に向けて】 健康経営アプリの選び方・運用方法

健康経営アプリの効果を最大限に発揮させるには、単に導入するだけでなく目的に合った機能の選定と、運用体制の整備が欠かせません。
導入前に押さえるべき選び方のポイントと、現場で定着させるための実践的な運用方法を解説します。
ポイント1:目的に応じた機能の選定
健康経営アプリの選定で最も重要なのは「自社のどんな課題を解決したいのか」を明確にする点です。目的が曖昧なまま導入すると「機能を使いこなせない」「現場で浸透しない」といった残念な事態を招きやすくなります。
そのため、従業員の生活習慣病リスクを減らしたいならば、歩数や食事、睡眠などの日常データを自動取得できる機能を用いたり、メンタルヘルス対策を重視するならストレスチェックやカウンセリング予約、セルフケアコンテンツを重視したりといった機能の選定が求められます。
また、現場作業員が多い企業ではスマートフォン操作が苦手な層にも使いやすい直感的なUIが好まれやすいなどの傾向を掴み、必要とするアプリの導入規模や社員層も考慮したうえで選定すると良いでしょう。
ポイント2:既存の業務システムとの統合・連携戦略:社内の課題の明確化と解決方法
アプリ導入の際に見落とされがちなのが「既存システムとの連携性」です。
健康経営アプリは単独で動くものではなく、人事システムや勤怠管理、ストレスチェックツールなどとデータを共有すると真価を発揮しますので、データの連携を図れる仕組みを選ぶと効果的です。
勤怠データと連携させれば「残業が多い部署ではストレス数値が高い」といった相関分析が可能になりますし、健康診断の結果を自動で取り込む仕組みを構築すれば毎年の紙ベース管理から解放され、管理部門の負担も大幅に削減できます。
中小企業では、システム統合に多くのコストをかけられない場合も少なくないので、API連携やCSVデータ出力などの柔軟に運用できる仕組みを持つアプリを選ぶと便利でしょう。
ポイント3:従業員の健康意識向上のための施策
どれほど優れたアプリを導入しても、従業員が積極的に活用しなければ効果は上がりません。
そのために必要なのが、健康意識を高めるための「仕組みづくり」です。
例えば、キャンペーンや社内イベントと連動をさせてウォーキングチャレンジや睡眠改善週間など、アプリのデータと連動した取り組みを実施すると社員同士の競争や応援が自然に生まれ、健康行動の習慣化につながります。
また、アプリの利用データを定期的に分析して社内報やミーティングで成果を共有するのも効果的で、「平均歩数が上がった」「睡眠改善率が向上した」など具体的な数字で見える化すると、モチベーション維持に直結します。
★従業員の使いやすさが好評の『オフけん 健康管理』がおすすめ!

心幸が提供する『オフけん 健康管理』なら、ストレスチェックや健診管理をアプリで行えます。
企業の業務を効率化できるだけでなく、従業員の皆様からも「使いやすい」「モチベーションが維持しやすい」と好評です!
従業員数の制限なしで、従業員5名でも100名でも1,000名でも、いつでも・どこでも、アプリで健康管理が可能です。ぜひご検討ください。
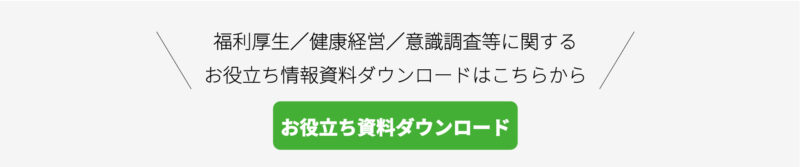
【従業員の意識変化・経営的な効果】企業における健康経営アプリ導入のメリット

健康経営アプリの導入は、単なる従業員支援にとどまらず、企業全体の成長戦略にも直結します。
導入によって得られる主なメリットを「従業員の意識変化」と「経営的な効果」の両面から解説します。
メリット:【社員の行動変容が狙える】 従業員の健康意識向上
健康経営アプリを導入する最大の利点は、従業員の健康への意識を「受け身」から「主体的」へと変化させる効果にあります。
従来の企業における健康施策は、健康診断やストレスチェックなど“年に数回のイベント”として実施されてきましたが、アプリの導入によって健康管理が日常業務の一部として自然な習慣化が図れます。
歩数や睡眠時間、食事内容を記録すると自分の生活リズムを可視化でき、「今日はもう少し歩こう」「夜更かしを減らそう」といった小さな行動変容が積み重なっていく効果も大きく、従業員にポジティブな健康文化が形成されます。
また、健康の見える化”と“共有化”は、従業員同士のコミュニケーションを活発にします。
メンタル面のケアやストレスマネジメントの機能を併用すれば、異変や症状の早期発見・離職防止にもつながるなど、組織の安定性を高める効果も期待できるでしょう。
健康経営アプリは「健康に気づく」だけでなく行動を変えるきっかけを提供するツールとして、企業の人材戦略を支えるのです。
メリット:【定量的評価とROI分析】 コスト削減と業務効率化
健康経営アプリを導入するもうひとつの大きなメリットは、経営的な投資効果を明確に測定できる点です。
アプリの活用によって従業員の健康状態や行動データを定量化すれば、コスト削減や業務効率化といった経営指標の改善を可視化できます。
さらに、データを継続的にモニタリングできると「どの施策が最も効果的だったのか」「次に注力すべき層はどこか」といった戦略的な意思決定も可能になるでしょう。
健康経営は“感覚的な取り組み”から、“数値で語れる経営戦略”へと進化しています。
★低コストでの導入にも定評あり!『オフけん健康管理』の魅力

初期費用0円で、従業員の健康を手軽に管理できる!と好評をいただいている『オフけん 健康管理』は、健康診断結果管理やストレスチェックの実施~管理、ストレスチェックデータ出力など企業が健康管理アプリを導入するメリットがギュッと詰め込まれたサービスの濃さが特徴です。
人数制限もなし!手頃な価格で高品質な健康管理アプリを導入するならば、『オフけん 健康管理』が断然おすすめです。
メリット:【ブランディング】企業のイメージ向上
健康経営アプリを導入すると、従業員の健康状態の改善だけでなく、企業全体の生産性やブランド価値の向上にもつながります。
近年、健康経営を積極的に推進している企業は「従業員を大切にする会社」「人に優しい企業」として社会的評価が高まる傾向にあり、導入によって実際の取り組みをデータで示すことができるようになります。
これにより、採用活動や顧客対応の場でも説得力を持たせられるでしょう。
また、社内外への広報活動を通じて「健康経営に強い企業」というブランドが確立できれば、企業価値向上にも直結します。
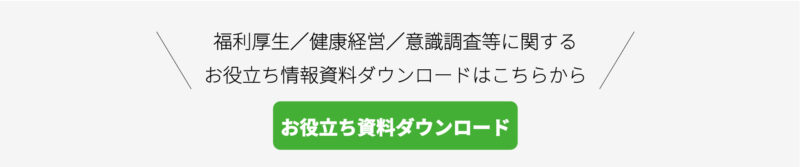
【失敗を避けるアドバイス】 健康経営アプリ導入に際する注意点

健康経営アプリの導入は企業の健康経営を推進するうえで強力な手段ですが、計画性なく進めると定着せずにコストだけがかかる結果にもなりかねません。
導入時に特に注意すべきポイントを整理し、従業員の理解と協力を得ながら成功へ導くための実践的なヒントを紹介します。
注意点:従業員のニーズを見誤らないようにする
健康経営アプリ導入の失敗要因として最も多いのが、「企業の想定」と「従業員の実際のニーズ」とのズレです。
例えば、企業側が「運動促進」を重視してフィットネス系機能を導入しても、実際には「睡眠の質改善」や「メンタルケア」を求めている社員が多いケースなどが挙げられます。
これを防ぐには、導入前にアンケートやヒアリングを実施し、従業員が「使いたい」と感じる機能を把握することが不可欠です。
年齢層や勤務形態によって健康課題は異なるので、柔軟に対応できるカスタマイズ性のあるアプリを選ぶのも選択肢です。
注意点:導入前のコミュニケーションを大切にする
どれほど優れた健康経営アプリでも、従業員の理解と納得がなければ定着しません。
そのため、導入前には「なぜこのアプリを導入するのか」「どんなメリットがあるのか」を具体的に説明し、従業員が自分ごととして捉えられるよう工夫をしましょう。
なお健康データの扱いに関しては不安を抱く人も多いため、プライバシー保護のルールや目的を明確に示すことで信頼を得やすくなります。
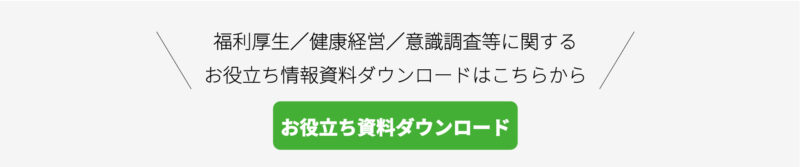
【まとめ】健康経営アプリ導入で期待できる未来と企業に求められる次のステップ

健康経営アプリは従業員の健康維持を支援するだけでなく、企業の生産性向上やコスト削減、さらにはブランド価値の向上にも寄与する戦略的ツールです。
ただしアプリ導入を成功させるには、従業員のニーズを把握した上で機能を選定する点や、導入前後の丁寧なコミュニケーションで理解と協力を得る努力が不可欠です。
また、健康経営アプリは企業の文化や働き方の変革を後押しするプラットフォームでもありますから、導入後はデータに基づいた改善サイクルを回しつつ、従業員が主体的に健康行動を継続できる環境を繰り返し整えることが、次のステップとなっていくでしょう。
福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>

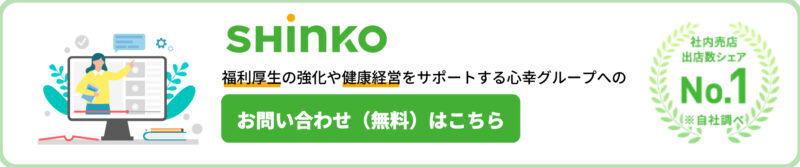
元気な会社は社員が元気!健康経営サポート

オフけん(運営:心幸ウェルネス)では、「健康経営優良法人」認定取得サポートを中心に、企業の健康経営をバックアップしています。形だけの健康経営ではなく、従業員の健康と幸福に真剣に向き合う取り組みを提案。真の健康経営を実現しています。「からだ測定会」では、体成分測定・体力測定により従業員一人ひとりのからだ年齢が明らかに!他にも、健康セミナー、禁煙サポートなどのサービスを通して、従業員の健康意識を向上させ、元気な会社づくりに貢献します。
オフけんはこちら