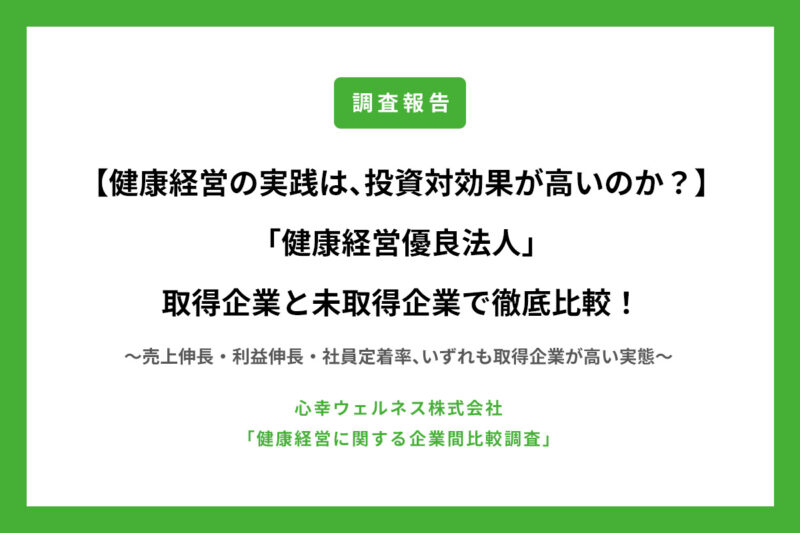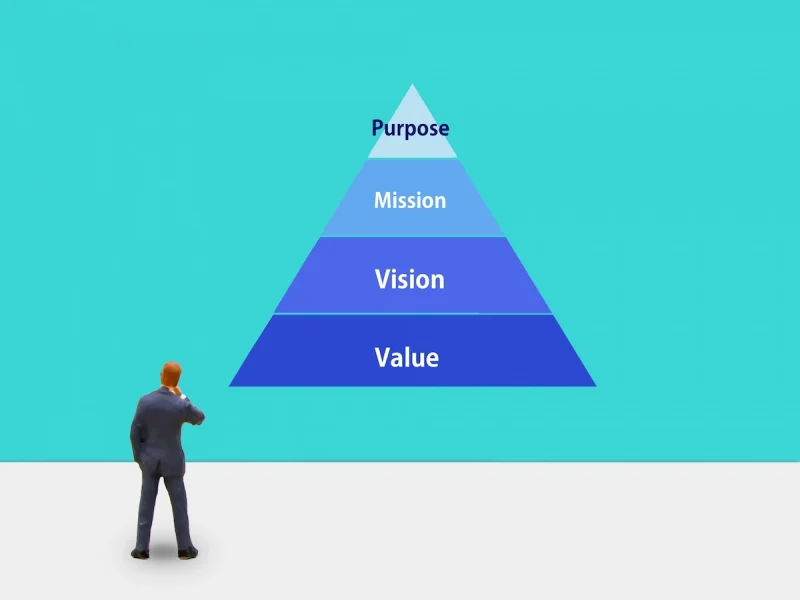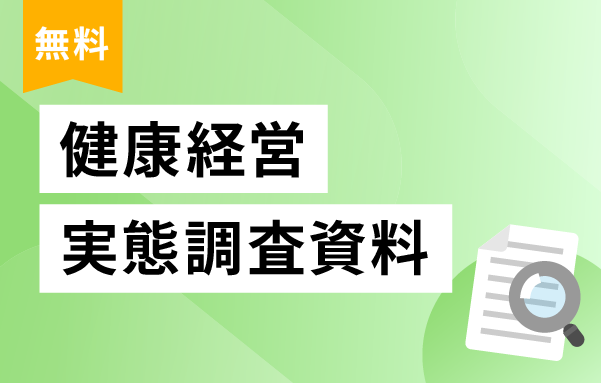健康経営の導入が推奨される企業の特徴は?導入の流れや失敗事例などとともに解説

業種や企業規模にかかわらず、健康経営はすべての企業において注目されている経営手法です。健康経営は、ただ単純に企業が従業員の健康管理を行うだけにとどまりません。業績向上やイメージアップにも大きく関わるなど、企業にとってプラスになる要素があることが、取り組む企業が増えている理由のひとつでしょう。
そこで本記事では、健康経営のメリットや導入の流れに加えて、失敗例や成功するポイントなどを解説します。
目次
健康経営の定義

経済産業省では、健康経営を「従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること」と定義しています。企業が従業員の健康に投資することが活力や生産性の向上をもたらし、結果的に企業の業績アップや企業価値の向上につながるというリターンが期待できることから、健康経営を導入する企業は近年増加傾向にあります。
参考/経済産業省「健康経営」
健康経営を見える化する顕彰制度「健康経営優良法人」
健康経営を導入する企業が増えていることを示すデータのひとつが、顕彰制度「健康経営優良法人」です。この制度は、大企業から中小企業で実践されている健康経営を見える化し、特に優良な健康経営を実践している企業が社会的な評価を受けられる環境整備を目的として、日本健康会議が認定しています。
健康経営優良法人認定事務局が運営するポータルサイトでは、健康経営優良法人として認定された法人一覧が掲載されています。「従業員の健康を大切にしている企業」として企業名が公開されることにより、企業イメージアップや金融機関からの融資や補助金の優遇が期待できるなど、健康経営優良法人として認定されることは企業にとって良い効果が期待できます。
参考/健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト「ACTION!健康経営」
企業で健康経営を導入するメリット

健康経営の導入には、前述した健康経営優良法人として認定されることによる良い影響をはじめとして、以下に挙げるメリットも期待できます。
従業員のモチベーション・生産性向上
ストレスや体調不良を抱えている従業員は、本来の能力を活かすことができなくなり、生産性を下げる原因となってしまいます。健康経営を行うと、従業員が心身ともに健康な状態で働ける環境が整いやすくなり、ストレス軽減や体調不良の原因となるメンタルヘルスの不調を解消できます。つまり健康経営を導入することは、従業員が個々の能力を最大限に発揮できる場を作る方法となるのです。
従業員が心身ともに健康な状態で働ける職場では、一人ひとりの企業への信頼感が高まり、勤務先企業に貢献しようという帰属意識が高まるでしょう。従業員の行動変容を促した結果モチベーションが向上し、意欲的に働ける状態が整ったことで組織全体の生産性が向上する効果が期待できます。
企業イメージの向上
積極的な健康経営への取り組みは、対外的な企業イメージを向上させる効果が期待できることも大きなメリットです。ワークライフバランスが重視される昨今、企業での働き方は世間一般にも関心が高まっています。そのような中で健康経営に取り組んで従業員の健康に投資することは、良いイメージを与えてくれます。
健康経営優良法人に認定されていればポータルサイトに企業名が掲載されるため、一般的なイメージ向上に加えて、取引先やステークホルダーなどからのイメージもアップして信頼性の向上も期待できるでしょう。
優秀な人材の確保
企業イメージの向上は、人材確保にも良い影響を及ぼします。従業員の健康を考えて働きやすい環境が整っている企業は、優秀な人材に選ばれる機会も増えることが期待できます。同様の条件の企業があった場合、健康経営に取り組んでいる企業の方がイメージが良いため、求職者に選ばれる可能性も高まります。
このように、健康経営に取り組むことによって企業全体のイメージがアップするに伴い、優秀な人材確保につながることも、健康経営を導入するメリットのひとつです。
健康経営の導入が推奨される企業

健康経営はすべての企業で導入されているものではありませんが、導入が推奨される特徴を持つ企業も存在します。以下では、健康経営の導入が推奨される企業の特徴をご紹介します。
残業や長時間労働が多い企業
残業や休日出勤が多い、または長時間労働が常態化している企業は従業員が健康を損なう恐れがあるため、健康経営の導入が推奨されます。労働時間は長ければ長いほど疲労やストレスを抱えこみやすく、従業員の健康に悪影響を及ぼす可能性があるので、従業員の健康管理するためにも労働環境の見直しとともに健康経営を導入することをおすすめします。
高ストレス状態の従業員が多い企業
現在、50人以上の従業員を抱える事業者には年1回のストレスチェックが義務付けられています。50人未満の企業でも努力義務となっており、2028年5月までに義務化されることが見込まれます。
多くの企業ではすでにストレスチェックが実施してされていますが、ストレスチェックの結果「高ストレス状態」に該当する従業員は、心身ともにさまざまな疾患のリスクが上がります。それが要因となり体調不良やメンタルの不調などで長期休業が必要となると、当然ながら従業員のモチベーションが低下し、企業全体の生産性低下を招くこともあります。
そのため、高ストレス状態の従業員が多い企業は、健康経営を導入する必要があるでしょう。
従業員の年齢層が高い企業
年齢が上がるにつれて、ケガや病気のリスクはだんだんと高まります。つまり、従業員の年齢層が高い企業は、ケガや病気を理由とした離職や休職のリスクも高いといえます。そのため、従業員の年齢層が高い企業は従業員の健康に配慮し、長く働ける環境づくりを進めるためにも健康経営の導入が求められます。
健康経営のROI(投資対効果)は?

ROIとは「Return On Investment」の略で、投資額に対してどの程度の利益を上げられたかの割合を示す指標です。健康経営によって期待できる効果は前述した通りですが、健康経営を導入するにはある程度の投資が必要となります。
しかし、従業員の健康状態や労働環境の改善などに対する健康経営の効果は短期的に判断することが難しく、具体的に健康経営のROIを評価するには、数年程度の長期的な視点で評価が必要です。その上で、従業員の欠勤率や健康状態、生産性や離職率などを総合的に評価すると、ROIを評価できるでしょう。
ROIは企業によって計測に必要な要素が異なり、長期的な評価が必要ですが、経済産業省が公開している資料では、健康経営の投資対効果の例として従業員の健康への投資はリターンが大きいという具体的な数字が挙げられています。
それによると、ニューズウィーク誌2011年3月号においてJ&J(ジョンソン・エンド・ジョンソン)グループが世界250社、約11万4,000人に対して健康教育プログラムを実施する形で投資した場合のリターンを試算したところ、健康経営への投資1ドルに対して3ドルのリターンがあったという結果が引用されています。リターンの内訳は、健康経営のメリットとして挙げた生産性向上や人材確保などとなっており、この調査では単純に3倍ものリターンが得られています。
同調査では、健康経営度調査スコア上位企業ほど低リスクで高リターンを得られる傾向が判明したほか、健康経営を経営理念に掲げて施策を実施することが利益率と相関関係があることも示されています。
また、健康経営は株価との関係性も指摘されています。経済産業省が公開した令和4年の「健康経営の推進について」によれば、健康経営銘柄2021に選定された企業の平均株価とTOPIXの推移を比較すると、TOPIXを上回る推移となっていました。
このことからも、健康経営は実施する企業への高いROIが期待できるだけではなく、ステークホルダーにとってもメリットが大きい施策といえるでしょう。
参考/経済産業省「健康経営の推進について」(平成29年)
経済産業省「健康経営の推進について」(令和4年)
健康経営を導入する流れ

健康経営を導入して自社で取り組むには、いきなり無計画で始めても効果は得られません。そこで、健康経営を導入するための基本的な流れを5つのステップで解説します。
1.健康経営を導入する旨を共有する
まず、健康経営を自社に導入する旨を社内外に宣言し、共有します。自社の従業員だけにとどまらず、加入している健康保険組合や全国健康保険協会にも健康経営の導入・実施を宣言、企業のWebサイトなどを通して健康経営導入に関する方針などの具体的なメッセージを発信することで、全社的に取り組むことを明示します。
健康経営の導入・実施は、従業員に理解してもらうことが重要です。そのため、従業員に対しては特に丁寧に健康経営の導入や詳細な実施内容、導入のメリットなどを詳しく説明しましょう。
2.運営体制を整える
健康経営導入を社内外に宣言した後は、実施するための運用体制を整えます。実質的な健康経営を展開するためのプロジェクトチームを立ち上げて、窓口となる担当部署や担当者を決定しましょう。
健康経営を運営するための担当者には健康経営に関する知識を持った人材を選任するのが最適ですが、必要に応じて産業医や外部の専門家などと契約を結んで協力を仰ぐこともあります。
3.健康課題の把握・分析を行う
健康経営を実施する前に、自社にどのような健康課題があるのかを把握・分析を行うことも健康経営を導入する上で大事なステップです。健康課題を正しく把握することが、適切な目標設定と施策の実行につながるからです。
定期健康診断の結果に加えて、ストレスチェックやアンケートの実施結果を分析し、従業員が抱える健康課題や問題の把握、勤務時間の実態とかけ合わせたデータ分析などを行います。
4.課題の分析結果を元に施策を実施する
3つ目のステップで自社が抱える健康課題を明確化した後は、その内容に沿った目標を定めて施策を実施します。そのためには、分析結果を踏まえた計画や施策の選定が必要です。
例えば、長時間労働や残業が多い場合はノー残業デーを定める、運動習慣が少ない場合は社内イベントの実施や勤務時間中の体操を日課にするなど、課題に沿った施策に取り組みましょう。
5.定期的に検証・改善を行う
健康経営は施策を実施して終わりではなく、運用後の効果を客観的に検証することも大事なポイントです。健康経営は短期間で効果が出ることは少なく、多くの場合は半年~年単位で取り組んで効果が得られる施策が多いものです。短期間で効果が出ないとしても、内容を検証して改善を繰り返すことで、効果が得られるでしょう。
健康経営を実施していく中で新たな施策や方法があった場合は、定期的に見直しを行い、必要に応じて柔軟に導入することも、健康経営の目標達成につながります。
健康経営でよくある失敗例

健康経営の基本的な導入の流れは前述した通りですが、この流れに沿って実施しても、必ずしも成功するとは限りません。取り組み内容や意識の持ち方によっては、健康経営が失敗することもあるでしょう。そこで以下では、健康経営の導入で失敗を防ぐために知っておきたい、よくある失敗例を2つご紹介します。
企業に合わない施策の実施
自社の職場環境や従業員に合わない施策を導入してしまうケースは、効果が出ずに目標達成ができない健康経営の典型的な失敗例です。
健康経営は、従業員の勤務体系や年齢層などによって適切な施策が異なります。他社で成功した施策であったとしても、まったく異なる職場環境に取り入れても効果は薄く、自社に合わない施策となる可能性が高くなります。従業員にとっても健康経営の施策は自身に合わないと感じてしまうこともあるため、参加に消極的になる要因となることも考えられるでしょう。
経営陣の理解不足
企業のトップである経営陣が健康経営への理解が不足していると、積極的な施策の展開が難しくなります。たとえ従業員が健康経営に意欲的に取り組んでいたとしても、健康経営に必要な予算や人員を割いてもらえなくなり、その結果十分な効果を得られずに施策そのものがストップしてしまうこともあり得ます。
健康経営は効果を得るには長期的な視点が必要で、すぐに効果が出るものではありません。理解不足により短期間で効果が出ないと経営陣が短絡的に判断してしまうことも、健康経営が失敗する一因となってしまいます。
健康経営を成功させるには

健康経営を成功させるには、まずは導入するための流れに沿って進めるのが基本となります。しかし、正しいステップで健康経営を導入したにもかかわらず目に見える効果が得られない場合は、失敗と判断されてしまうでしょう。健康経営を成功させるには、前述した失敗例を踏まえた上で、以下で解説する3つのポイントを意識して導入を進めてみましょう。
経営陣が率先して働きかける
健康経営の成功には、経営陣の理解が欠かせません。加えて、経営陣が率先して従業員に働きかけることが成功のポイントとなります。健康経営の失敗例にも挙げたように、経営陣が健康経営について理解しておらず消極的である場合、企業の健康経営の実践は難しくなります。
健康経営がどのように企業にメリットをもたらすか、企業の成長に寄与するかなどを明示してセミナーに参加してもらうなどの方法で、経営陣に健康経営を理解してもらうことも必要です。理解を深めてもらい健康支援への協力を働きかけることで従業員へのリーダーシップを発揮できるようになると、健康経営を成功に導けるでしょう。
目的を明確にする
健康経営を成功させるためには、施策を実施する前段階で目的を明確にしておくことが重要です。目的を明確化するためには、自社の従業員や職場環境とともに課題や問題を正確に把握する必要があります。
つまり、健康経営を導入する段階でしっかりと準備をしておかなければ、施策を実施した後の目標もブレてしまいます。その結果、なぜこのような施策を行っているのかわからないまま進められてしまうと、プラスの効果も得られないでしょう。
健康経営を導入する段階で明確な目的を設定できていれば、従業員が必要とする施策を打ち出すことができ、良い効果が期待できます。
自社に合った施策を実施する
目的の明確化と共通しますが、健康経営はそれぞれの企業に合った施策を行うことも成功のポイントのひとつです。業務内容や従業員の働き方は企業によって大きく異なるので、自社の従業員や職場環境に最適な施策を導入することが大事でしょう。
例えば、スマートフォンやアプリの操作を日常的に行う世代が多い場合は専用アプリを導入して健康管理を行う、社内イベントとしてウォーキング大会や運動会などを開催するなどの事例があります。このように自社で取り組みやすい施策や仕組みを設定すれば、従業員が主体的に参加しやすくなり、健康経営の効果を出しやすくなることが期待できます。
関連記事:健康経営の具体策でウォーキングイベントを導入する企業が増加!事例紹介
多様な働き方に対応するための健康経営

これまで、企業で働く従業員は毎日オフィスへ出勤して仕事をするのがごく普通の働き方でした。しかし近年、感染症流行や働き方改革による柔軟な働き方の導入が進められるなどの影響により、ワンパターンだった勤務体系が多様化しています。その代表的な例が、場所を問わず働けるテレワークです。
健康経営は、企業のオフィスで働く従業員を対象としているものと考えられがちですが、テレワークなどオフィス以外で働く従業員の健康管理も企業に求められます。したがって、多様な働き方が定着しつつある昨今、従来の勤務体系のみを対象とした健康経営が適さない可能性も出てきました。
では、働き方が多様化している中で企業はどのような健康経営を実施すればいいのでしょうか。
企業・従業員双方にリスクが予想されるテレワーク
2020年の新型コロナウイルス流行や働き方改革推進に伴い、多くの企業でテレワークの導入が進められました。
テレワーク導入は、特に新型コロナウイルス流行による影響が大きいことがデータでも判明しています。経済産業省の調査によると、感染症流行前の2019年までの雇用型就業者のテレワーク実施率は14.8%でしたが、流行後の2020年は23%に増加しています。業種別に見ると、比較的テレワークを導入しやすい情報通信業の導入率が突出して高く、2020年時点で66.1%となっていました。
新型コロナウイルスの流行が落ち着いた後、勤務体系を以前と同じオフィスへの出勤に戻す企業が増えていますが、テレワークはワークライフバランスを改善して生産性向上を図る目的としても導入されているため、現在も引き続きテレワークで働いている従業員が多い企業もあります。
しかし、従業員にとってテレワークは働きやすい環境が整うメリットがある一方で、企業側が従業員の健康状態を把握しにくくなること、自宅で働くことで従業員の作業環境が悪くなったり運動不足に陥ったりするなどのデメリットも存在します。
テレワークには、このような導入前にはあり得なかった健康リスクが発生するという問題が想定されます。従来のオフィスで働く従業員を前提にした施策ではテレワークで働く従業員をカバーすることが難しく、健康経営の実現も困難となることが予想されるでしょう。
参考/経済産業省「テレワークが産業に与える影響;事業継続に強い力を発揮」
働き方の変化に対応するには
オフィス勤務を前提とした施策のみで健康経営を導入しようとすると、テレワークのような働き方の変化には対応しきれません。
今現在は従業員全員が出勤している企業であっても、今後働き方改革や感染症流行などの影響により、再度テレワークを導入する動きが活発になる可能性はあるでしょう。働き方の変化に対応した健康経営を導入するには、テレワークの特徴を踏まえた施策を検討する必要があります。
例えば、体を動かすサポートツールやアプリの導入、福利厚生としてスポーツジム利用費用の一部負担などが、運動不足を解消するための対策の一例です。従業員の健康状態の把握についても、健康診断の受診した上での健康管理アプリの活用や産業医との面談の実施などで対策が可能です。
従業員が離れた場所で働いているからこそ、遠隔でも情報管理ができるツールなどを活用してデータを連携することで、働き方の変化に対応した健康経営を実践しやすくなるでしょう。
オフけんで実現する企業に最適な健康経営

健康経営を導入するには、自社の労働環境や従業員のニーズに合わせた施策を実施することが第一に求められます。しかし、事前準備や効果を出すための施策を一から構築するのは困難だと考えている企業も少なくないでしょう。そのような場合におすすめしたいのが、心幸グループが提供する「オフけん」です。
オフけんでは、従業員の健康管理をサポートし、ストレスチェックや健康診断結果管理もできる専用の健康管理アプリやオンライン診療、たばこをやめるサポート「卒煙チャレンジ」など、多彩な健康維持・増進サービスで健康経営をサポートします。
オフけんは専門コンサルタントが伴走する健康経営優良法人認定取得サポートも行っているので、毎年変わる認定基準に沿った申請業務にも対応可能です。将来的に健康経営優良法人の認定を受けたい企業にとっても、有益なサービスとなるでしょう。
まとめ
優良な健康経営を実施している企業を評価する認定制度として「健康経営優良法人」が設けられているなど、健康経営は従業員を抱えるすべての企業で重要度が高まっています。健康経営は、特に従業員の心身への負荷が高い職場環境を持つ企業や年齢層が高い企業に必要性が高いものです。
健康経営は一度導入しては終わりではなく、定期的な検証や改善も必要不可欠です。テレワークを導入している企業では、これまで行ってきた健康経営がすべての従業員に有効な施策とならなくなることもあるなど、働き方の多様化によって同じ施策では想定した効果が期待できなくなることも考えられるでしょう。
効果的な健康経営を実施するには、運営体制の構築と健康課題の把握や分析、定期的な検証を基本とし、経営陣が積極的に働きかけて導入することが求められます。今回解説した健康経営導入の流れや失敗例、成功のポイントを踏まえて、自社に最適な健康経営の施策を導入しましょう。