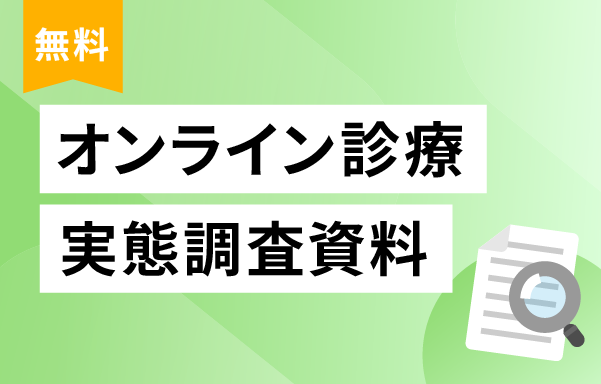オンライン診療システム導入ガイド|人事・総務が押さえるべき選定ポイントと選び方・メリットを考慮した成功のカギ

こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。
働き方の多様化に伴い、企業の健康管理のあり方も大きな転換期を迎えています。従業員の健康維持は単なる福利厚生ではなく、生産性や離職率・企業イメージにも直結する重要な経営課題です。
一方で、産業医面談や定期フォローを対面のみで行う従来の方法では、距離や時間の制約が壁となって十分な対応が難しくなっている実例も少なくありません。
こうした課題を解決する手段として、近年急速に注目を集めているのが「オンライン診療システム」です。遠隔での産業医面談や健康相談、生活習慣病のフォローアップ、メンタル不調者対応などの幅広いシーンで活用でき、従業員の負担軽減と健康管理の効率化を同時に実現しています。
本ガイドでは、人事・総務部門が押さえておくべきオンライン診療システムの選定ポイントと、導入を成功させるための実務的なステップを解説します。「検討段階」で止まらず、確実に実行へ移すためのヒントとしてお役立てください。
福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉
目次
【通院不要の取り組み】 企業の健康管理と医師によるオンライン診療・診察の現実

従業員の健康管理は、企業にとっては生産性やエンゲージメントに直結する重要な課題です。
特に近年は、テレワークの普及・副業容認・地方在住社員の増加などによって従業員の働き方が多様化しています。これに伴って対面型の産業医面談や診療の機会が減り、健康リスクの早期発見やフォローが難しくなるリスクが上がっています。
テレワークや従業員の多様化により変化する健康管理ニーズの特徴
テレワークや従業員の多様化によって、いまや従来のようにオフィス常駐の社員だけを対象にした健康管理フローでは不十分な時代に入りました。企業における健康管理の課題は、従来の「オフィス勤務」を前提とした仕組みでは対応しきれない局面が増えています。
生活習慣病の早期対応やメンタルケアはオンラインで補う必要性も高まっており、さらには健康診断後のフォローやストレスチェック後の面談も、オンラインを通じてスムーズに行う体制が求められている時代だと言えるでしょう。
企業は、変化している健康管理ニーズに速やかに応えていく必要があります。
★「検討」で止まっていませんか?――今こそ“行動に移す”タイミング
オンライン診療の導入は、制度設計や社内調整に時間を要します。現実には導入を検討する企業の多くが「費用対効果」や「社内体制の準備不足」を理由に足踏みしているのも事実です。
健康管理のニーズは確実に変化している一方で、その変化に合わせた仕組みづくりを後回しにすれば、見えない健康リスクが蓄積していく可能性が低くないでしょう。
そこで「いつか導入したい」と先延ばしにするよりも、次年度の健康経営施策や産業医契約更新のタイミングに合わせて具体的な準備を進めることが成功のカギです。
従業員のオンライン診療と健康管理を導入するなら、自社でゼロから作るよりも申し込んですぐに一元化できるサービスのほうがスピーディーです。
「検討」で止まっているならぜひチェックを!▶︎オンライン診療・健康管理を一元化できる「オフけん」の詳細はこちら

産業医対応とオンライン面談の法的整理と実務ポイントを紹介

産業医対応とオンライン面談には、密接な関係があります。
実務上、必ずチェックしておきたいポイントを整理します。
産業医のオンライン対応に関する厚労省通達に基づいた要件を整理しよう
オンラインでの産業医面談を進めるうえでは、厚生労働省が示す要件を正しく理解しておく必要があります。厚生労働省は次のように、産業医の面談や指導をオンラインで実施する場合の条件を明確にしています。
主な要件としては、
・面談の目的や内容を事前に明確化すること
・通信環境の安定性を確保すること
・面談時のプライバシー確保(第三者の同席回避、録音・録画の管理など)
などが挙げられます。
また、必要に応じて対面への切り替えができる体制も求められます。
高ストレス者への対応や復職面談での活用シーンも想定しよう
オンライン化は、高ストレス者面談や復職面談において有効な活用シーンが多々あります。
高ストレス者への対応では、時間や場所の制約を受けず迅速に面談が実施でき、心理的負担の軽減にもつながるでしょう。
復職面談でも、職場復帰前に段階的な面談を重ねやすくなり、スムーズな復帰計画を立てやすくなります。
オンライン化によって、対面のみの対応では実現が難しかった柔軟性を提供できるのは大きなメリットと言えるでしょう。
ストレスチェック結果が「高リスク」と判定された従業員の面談や、休職者への復職前・復職後フォロー、健康診断後の精密検査や生活指導などは、オンライン診療と特に相性のいい分野です。
オンライン化によって地方勤務や在宅勤務者でも診療への心理的・物理的ハードルを下げられるメリットは、現代において無視できないほど大きいものです。
オンライン化に必要な社内体制を整備しよう
オンライン面談を円滑に機能させるには、社内体制の整備が不可欠です。まずは、産業医・衛生管理者・人事担当者・IT部門の役割を明確にし、面談予約から実施、記録管理までのワークフローを定義する必要があります。
さらには通信環境や機器の準備、個人情報の取り扱いルール、トラブル発生時の対応フローも事前に整えておく必要があります。
オンライン化にあたりIT部門とセキュリティ要件を確認し、人事や総務、産業医・衛生管理者間での業務分担の明確化を丁寧に行いましょう。
また、社員が実際に活用しやすいよう、並行して利用マニュアルやFAQの作成も求められます。
★「産業医サービス」に関するより詳しい情報はこちら
産業医サービスについては、過去記事の「企業が利用できる産業医サービスとは?できることや選ぶ際のチェックポイントを解説」により詳しい情報を掲載しています。
ぜひ併せてご覧ください。

【今こそ特徴を知っておきたい】オンライン診療システムの基本機能と主な導入スタイル

オンライン診療システムには多様な機能があり、その組み合わせによって活用の幅が広がります。
つまり「オンライン診療システム」と一口に言っても、その用途や提供機能は多岐にわたりますので、自社のニーズに合うスタイルを採用することが大切です。
一般診療・定期フォロー・生活習慣病管理・メンタル対応の棲み分けとは?
オンライン診療システムの基本機能としては、体調不良時の初診・再診をオンラインで行う「一般診療型」だけでなく、健康診断後の経過観察や服薬指導などを対象とする「定期フォロー型」、血圧・血糖・体重などの健康データとシステムを連携させて日常的な健康管理をメインとする「生活習慣病管理型」、さらには心理カウンセリングや産業医面談に特化した「メンタル対応型」もあります。
自社の導入目的に応じて、適切な内容を選定すると良いでしょう。
LINE連携型・クラウド型…自社のIT環境に合うタイプを確認
システムの導入形態も、さまざまなバリエーションがあります。
たとえば「LINE連携型」は既存のコミュニケーションツールを活用できるために導入のハードルが低く、他方で「クラウド型(専用ポータル)」は高いセキュリティと拡張性が魅力です。
また、既存の健康管理システムと統合可能な「ハイブリッド型」もあります。
自社のIT環境や利用目的に応じて、適切なタイプを選定すると良いでしょう。
★【導入を安心サポート】 1つのサービスで完結させるなら「オフけん」
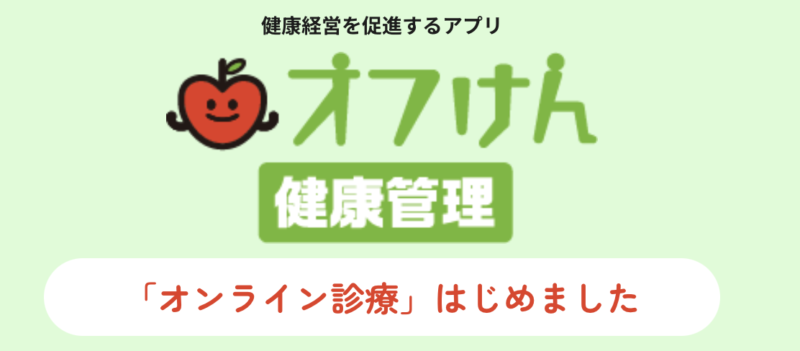
多様なサービス内容から機能や導入形態を決定するのが難しいと感じるようであれば、ひとつのサービスで完結する『オフけん』をぜひご検討ください。
健康管理アプリにオンライン診療機能があるので、スキマ時間でも「オンライン診療~処方箋発行」までをスマホで完結する利便性も高評価をいただいています。
アプリの使用料金は中小規模の法人なら1ヶ月あたり20,000円〜!

【導入ステップを解説】人事・総務部門が主導すべき具体的アクションのポイント

オンライン診療システムの導入を成功させるためには、人事・総務部門が中心となって現状把握から具体的な要件定義、コスト試算までを計画的に進めると良いでしょう。
ステップ1:現状の健康支援フローを棚卸しする
第一歩は、現状の健康支援フローを棚卸しすることが求められます。
健康診断やストレスチェック、産業医面談や休職者対応といった各プロセスを洗い出します。どこまでをオンライン化できるか、どの業務が優先度が高いかを明確にしましょう。
この段階で、対象となる従業員の勤務地や雇用形態、勤務形態(出社・在宅・ハイブリッド)も整理しておくと、後の設計がスムーズです。
ステップ2:システム要件の整理と、関係部署との調整を行う
次に、システム要件の整理と関係部署との調整を行いましょう。
IT部門とは通信環境やセキュリティ要件を、法務部門とは個人情報保護や契約条件を、産業医や衛生管理者とは運用フローや記録管理の方法をすり合わせます。
このプロセスで要件を曖昧にしたまま進めると、導入後にトラブルや追加コストが発生する可能性が高まるために初期段階での明確化は不可欠です。
ステップ3:プライバシーへの配慮や初期費用と運用コストを試算する
さらには、プライバシーへの配慮とコスト試算も並行して進めます。
診療データや面談記録は高度な機密情報ですので、暗号化通信やアクセス制限、保存データの管理場所などの条件を満たす必要があります。
加えて、初期費用と運用コストを具体的に試算して年度予算や健康経営計画との整合性を確認しましょう。
コストだけでなく従業員の健康改善や離職防止による効果も見込みとして提示できれば、経営層の理解と承認を得やすくなるでしょう。
こうしたステップを順序立てて進めることができれば、人事・総務部門が主導するオンライン診療システム導入にあたり成功の可能性が高まります。

【運用フェーズの特徴を解説】 社内への浸透と継続利用を促す工夫が必要不可欠

導入後の定着には、従業員のITリテラシーに応じた周知方法が効果的です。オンライン診療システムは導入そのものよりも「従業員が継続して利用する仕組みづくり」が成否を分けます。
従業員のITリテラシーに応じた周知方法を採用する
まず着手すべきは、従業員のITリテラシーに応じた周知方法の設計です。
社内全体に一斉メールを送るだけでは、IT操作に不慣れな層には十分に伝わらない場合もあります。システムの操作方法や予約手順を簡潔にまとめた動画マニュアルを用意して、イントラネットや社内ポータルからいつでも確認できるようにしておきましょう。
また、健康診断や安全衛生委員会のタイミングでデモンストレーションを行えば、実際の利用イメージが浸透しやすくなります。
定期的なフィードバックを実施し利用の実績を可視化する
導入後は、定期的なフィードバックの収集と利用実績の可視化が欠かせません。
利用率や満足度、改善要望を定期的に集めて改善点を迅速に反映しましょう。これにより、従業員からの信頼と利用意欲を高められます。
利用状況をグラフ化して社内に共有すれば「実際に使われている」という実感も広がり、利用促進にもつながるでしょう。
★使いやすいスマホ完結型・アプリ式なら運用も簡単です!
運用をよりスムーズに進めるためには、スマートフォンで完結するアプリ型システムの採用も検討に値します。
アプリであれば「予約・診療・支払い」までをワンストップで行えるため、従業員の利便性が向上し利用定着率の向上が期待できます。
▶︎健康経営を促進するアプリ『オフけん』の詳細はこちら!

今こそ不安解消! 検討から実行へ「とりあえず情報収集中…」から一歩を踏み出すタイミング

オンライン診療は“いつか必要になる”ではなく、すでに多くの企業が取り入れている健康管理の標準手段です。
特に健康経営優良法人の認定を目指す企業や、全国規模で従業員を抱える企業では導入の遅れが差別化の不利につながる可能性もありますので、早めに導入を検討するほうがメリットが大きいでしょう。
もしも検討段階で止まっているのであれば、まずは社内パイロット導入(部署限定トライアル)を実施して、実績を積みながら全社展開へと移行するのも一案です。
また、制度設計や社内調整に時間を要するのがネックとなっているならば、次年度の健康経営施策や産業医契約更新のタイミングに合わせてアプリだけで完結するサービスの活用を視野に入れることをおすすめします。
福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>


元気な会社は社員が元気!健康経営サポート

オフけん(運営:心幸ウェルネス)では、「健康経営優良法人」認定取得サポートを中心に、企業の健康経営をバックアップしています。形だけの健康経営ではなく、従業員の健康と幸福に真剣に向き合う取り組みを提案。真の健康経営を実現しています。「からだ測定会」では、体成分測定・体力測定により従業員一人ひとりのからだ年齢が明らかに!他にも、健康セミナー、禁煙サポートなどのサービスを通して、従業員の健康意識を向上させ、元気な会社づくりに貢献します。
オフけんはこちら