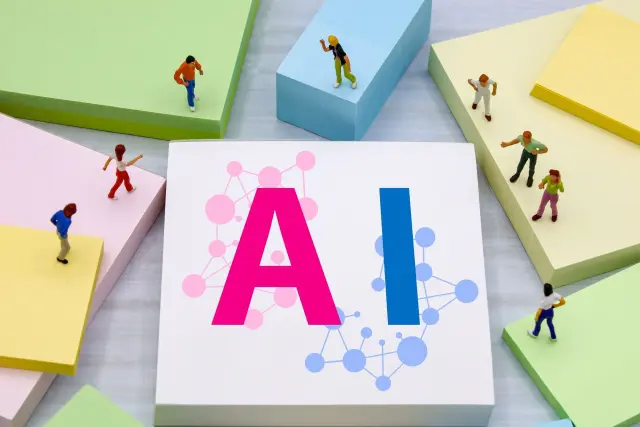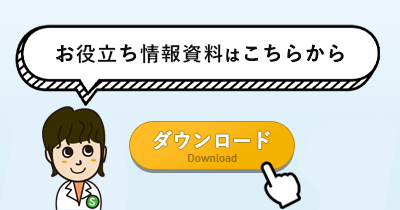フレックスタイム制を導入する企業が押さえたい基本情報!メリット・デメリットや成功事例も紹介

こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。
ワークライフバランスの向上につなげるためにも、今となって注目を集めているフレックスタイム制を導入することは重要です。
企業がフレックスタイム制を取り入れることで、業務や通勤ラッシュなどによる負担を軽減できるほか、生産性や従業員の定着率を高めることが可能です。
この記事では、企業がフレックスタイム制を導入する際に押さえたい基本情報をまとめました。
フレックスタイム制を導入するメリット・デメリットや、企業の成功事例などもわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。
福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉
目次
企業がフレックスタイム制を導入する際に押さえたい基本情報

最初に、フレックスタイム制の導入を検討している企業の悩みを解決できるように、知っておきたい基礎知識について紹介します。
フレックスタイム制とは?
そもそもフレックスタイム制(Flexible Time System)とは、従業員が日々の労働時間(仕事の開始時刻や終了時刻)を自身の判断によって決められる、柔軟な働き方を指します。
具体的には、1週間に40時間働く場合、一般的な勤務形態では1日8時間労働となります。
しかし、フレックスタイム制を導入することで、たとえば8時から17時までの勤務予定を、10時から19時までに変更するといった柔軟な対応が可能です。
さらに、各社が定める制度によっては、ある1日を6時間勤務に抑え、別の1日を10時間勤務として調整するといった働き方もできます。
フレックスタイム制は、従業員のワークライフバランスの向上や通勤ラッシュによる混雑緩和などを目的として、最近にかけて多くの企業が導入する傾向です。
企業はあらかじめ、全体の労働時間(総労働時間)やこれから紹介する「コアタイム」と「フレキシブルタイム」を定めて、従業員と取り決めを交わす必要があります。
フレックスタイム制の仕組み
フレックスタイム制は、1日の労働時間内で「コアタイム」と「フレキシブルタイム」を組み合わせて運用されるのが一般的です。
コアタイムとは、従業員が必ず勤務する必要がある時間帯のことです。
具体的には、コアタイムを10時から15時までと設定すると、この時間内は企業に出社して勤務することを必須にできます。
コアタイムは企業によって時間帯が異なりますが、従業員がコアタイムの開始時刻より遅れて出社した場合や、終了時刻より早く退社した場合は、遅刻や早退とみなすことが可能です。
多くの場合、社外とのやり取りや社内会議などの都合にあわせて設定され、コアタイムを設けることによって、フレックスタイム制であっても出社を求められます。
一方でフレキシブルタイムとは、コアタイムの前後の時間帯のことです。
従業員が自身の都合や業務の状況にあわせて、出社や退社の時間を自由に決められます。
たとえば、コアタイムを10時から15時とするなら、出勤は8時から10時まで、退勤は15時から18時といった時間帯がフレキシブルタイムに該当します。
また、フレキシブルタイム内であれば、一時的に業務を中断して外出する「中抜け」も可能です。
しかし、特定の期間(清算期間)内の総勤務時間が、規定の労働時間に満たなかった場合は、給与をカットするといった対応を行えます。
通常の労働時間制とフレックスタイム制の違い
これまで日本の企業で広く採用されてきた通常の労働時間制度は、「固定労働時間制」といわれています。
固定労働時間制では、仕事の開始時刻や終了時刻といった労働時間の配分が固定されているのが一般的です。
そのため、従業員はあらかじめ定められた労働時間の配分に沿って勤務します。
たとえば、9時に始まり18時に終わる勤務が定められている場合、9時から18時が勤務時間です。
また、昼休みをはじめとした休憩時間も、特定の時間帯に固定されているのが一般的です。
固定労働時間制は、労働時間の配分が決まっているため、従業員のスケジュール管理がしやすく、給与計算がシンプルでわかりやすいというメリットがあります。
従業員にとっても、予定が立てやすい制度といえます。
ただし、固定労働時間制では、従業員が自分の判断で勤務時間を変更することは基本的にできず、柔軟性に欠けるのがデメリットです。
一方でフレックスタイム制は、固定労働時間制とは異なり、従業員の裁量で労働時間を自由に決められるのが特徴です。
必ず勤務する必要がある固定された時間帯(コアタイム)はあるものの、それ以外の時間帯(フレキシブルタイム)については、従業員が自身の都合や業務の効率にあわせて、出社や退社の時間を自由に選べます。
また、フレックスタイム制では、1日の労働時間を固定せず、一定期間で総労働時間を定めます。
従業員は、決められた総労働時間の範囲内で、生活と仕事のバランスを考慮しながら、日々の労働時間や出退勤時間、休憩時間などを自身で決めることが可能です。
つまり、労働時間を従業員自ら管理できる点が、固定労働時間制とフレックスタイム制の大きな違いです。
さらに、フレックスタイム制をさらに発展させた形態といえる労働時間制度「スーパーフレックスタイム制」があります。
スーパーフレックスタイム制は、通常のフレックスタイム制とは異なり、コアタイムがないことが挙げられます。
これにより、従業員はコアタイムに縛られることなく、自身の判断で始業時間や終了時間、勤務時間を完全に自由に選ぶことが可能です。
ただし、フレックスタイム制と同様に総労働時間が定められているため、その範囲内で調整する形になります。
スーパーフレックスタイム制は、他の制度と比べて、個人の状況にあわせて勤務時間を調整しやすく、自由度が高い制度です。
生活・家庭・体調あるいは仕事の進捗状況に応じて、自分の判断で労働時間を配置することが可能です。
そのため、スーパーフレックスタイム制の導入によって、より高度なワークライフバランスの実現が期待できます。
しかし、労働時間の配分を従業員の自主性に任せるため、すべての企業で導入できる制度ではありません。
主に、以下のような企業が導入するケースが多いです。
・従業員の自律性や自己管理能力を高く評価する企業
・働く場所や時間に制約が少ない企業
・勤務時間よりも成果や業績を重視する企業
・完全な成果主義に基づいた評価が行われる企業
勤務時間よりも成果や業績が求められる理由として、従業員の実績や成果を判断する際に、労働時間や勤務状況を反映させることが難しいためです。
このようにスーパーフレックスタイム制は、ワークライフバランスのさらなる促進にはつながるものの、従業員は自己管理能力や具体的な成果が求められ、かえって負担やストレスを増やす原因になります。
スーパーフレックスタイム制を導入する際は、メリットだけでなくデメリットも考慮して、労働環境が悪化する可能性を踏まえる必要があります。
裁量労働制や変形労働時間制との違い
フレックスタイム制と内容が似ていて、特に混同しやすい制度「裁量労働制」と「変形労働時間制」について紹介します。
裁量労働制とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ決められた時間を労働時間とみなす制度のことです。
たとえば、裁量労働制の契約によってみなし労働時間を1日8時間とした場合、実際の労働時間が6時間であったり10時間であったりしても、契約した8時間働いたとみなして給与を支払います。
勤務時間を従業員がある程度自由に決められる点はフレックスタイム制と共通しているものの、裁量労働制では、実際に勤務していない日でも「働いた」とみなされる点が異なります。
一方で変形労働時間制は、一定期間内での労働時間の割り振りを自由に決められる労働時間制度です。
繁忙期や閑散期など、企業や部署全体の業務量に応じて勤務時間を調整します。
一定期間の合計労働時間で計算する点はフレックスタイム制と同様ですが、変形労働時間制の場合、従業員としては、プライベートな都合にあわせて柔軟に変更できない点が異なります。

フレックスタイム制を導入する企業のメリット

企業がフレックスタイム制を導入するメリットは、以下のとおりです。
・ワークライフバランスを向上できる
・通勤ラッシュによる負担の軽減につながる
・従業員の満足度とモチベーションをアップできる
・長時間労働を軽減できる
・従業員の定着率を高められる
・採用時のアピールポイントになる
・欠勤率を低下できる
・残業時間や労働力負担のカットにより生産性を向上できる
それぞれのメリットについて、順を追って解説します。
ワークライフバランスを向上できる
多様性が重視される現代社会において、従業員一人ひとりの個性や生活環境にあわせた働き方が求められるようになっています。
フレックスタイム制は、それぞれの従業員のニーズやライフスタイルに柔軟に対応できるため、多様性を受け入れやすい労働時間制度といえます。
フレックスタイム制を導入することで、家庭の状況や健康状態、趣味や学習の時間など、個人の生活と仕事の時間をバランスよく調整し、ワークライフバランスの実現が可能です。
たとえば、子育て中の従業員は子どもを保育園や学校に送ってから出社し、資格取得を目指している方は早めに退勤して専門学校に通学できます。
また、ケガや病気などで通院が必要な場合であっても、通院後に会社に来たり早く帰宅したりできるため、体調管理がしやすくなる傾向です。
このように、一人ひとりのライフスタイルにあわせた柔軟な働き方ができる環境を整えることで、従業員のワークライフバランスを向上できます。
通勤ラッシュによる負担の軽減につながる
通勤ラッシュは従業員にとって大きなストレスの原因となり得るため、できれば避けたいものです。
フレックスタイム制度は、通勤時の混雑緩和を目的として導入されることがあります。
誰もが同じ時間帯に出退勤すると公共交通機関が混雑しますが、フレックスタイム制を導入することで、出退勤の時間をずらすだけで、簡単に通勤ラッシュを回避することが可能です。
これにより、ストレスの少ない快適な通勤が期待できます。
また、車通勤の場合であっても、主要幹線道路の混雑を避けられるため、通勤時間の短縮にもつながります。
快適な通勤を実現することで、従業員の疲労を軽減し、業務効率の向上にも寄与するため、企業にとっても大きなメリットです。
従業員の満足度とモチベーションをアップできる
従業員が自分の働き方を自由に選べるようになると、仕事への満足度やモチベーションが高まる傾向にあります。
フレックスタイム制は、従業員が個々のライフスタイルや価値観にあわせた働き方を実現できるため、結果として職場全体の満足度やエンゲージメントの向上につながります。
長時間労働を軽減できる
通常の労働時間制度では、出勤・退勤時間が固定されているため、仕事が多い日は残業が避けられない一方で、仕事が少ない日は退勤まで時間を有効活用できないことがあります。
フレックスタイム制の場合、一定期間に定められた総労働時間の範囲内なら、従業員自身が出勤・退勤時間や1日の労働時間を自由に決められます。
そのため、仕事が少ない日は早めに退勤し、その分の労働時間を仕事が多い日に振り分けることが可能です。
時間を効率的に使えるようになることで、不要な時間外労働が減り、従業員の負担軽減につながります。
従業員の定着率を高められる
フレックスタイム制は、ワークライフバランスの向上や通勤ラッシュを避けた快適な通勤が可能になるため、結果として優秀な従業員の離職を防ぐ効果が期待できます。
これにより、人材不足が叫ばれる中、従業員の定着率を高められるため、多くの企業が抱える課題解決の一助となります。
採用時のアピールポイントになる
個々のライフスタイルに合わせた働き方ができるフレックスタイム制は、人材の募集や採用においてアピールポイントとなります。
柔軟な働き方ができる企業として、新卒採用や転職などに関する情報サイトにてアピールすることで、より多くの人材を引き付け、従業員が自社で長く働くことを選択する可能性が高まります。
特に、若年層や多様な経験を持つ人材にとって魅力的です。
日本ではまだフレックスタイム制の導入企業が少ないため、採用競争において他社との差別化を図りましょう。
欠勤率を低下できる
突発的なプライベートな予定や健康上の問題などによる予期せぬ事情での欠勤は、従業員と企業の双方にとっても望ましくありません。
フレックスタイム制の導入により、従業員は自分の状況や必要に応じて勤務時間を調整できるため、急な欠勤や遅刻が減少する可能性が高まります。
残業時間や労働力負担のカットにより生産性を向上できる
フレックスタイム制は、生産性の向上が期待できる制度です。
人間のバイオリズムは、一日を通して一定であるとは限りません。
特定の時間帯に眠くなったり、集中力を欠いたりすることがある一方、集中力が高まる時間帯もあります。
フレックスタイム制であれば、集中力が高まる時間帯に業務を集中させることが可能です。
これにより、業務の質や効率アップにより、生産性の向上が期待できます。
また、仕事が多い日は早めに出勤したり、夕方から仕事が増えるとわかっている日は遅めに出勤したりすることで、残業時間を減らし従業員の負担を軽減することが可能です。
企業にとっては、高い生産性や成長を維持しながら、残業代(時間外労働の割増賃金)を削減できるというメリットがあります。

フレックスタイム制を導入する企業のデメリット

フレックスタイム制には数多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。
・社内でのコミュニケーションが不足しやすい
・勤怠管理が複雑になる
・職場の連帯感や結束力が低下する
・業務の進行や外部とのやりとりに支障が生じる場合がある
・自己管理ができない従業員への対応が求められる
メリットとデメリットの両方を把握したうえで、適切に制度を運用できるよう準備を進めましょう。
社内でのコミュニケーションが不足しやすい
フレックスタイム制では、従業員が異なる時間に出退勤するため、全員が同じ時間帯に企業にいる機会が減少します。
これにより、対面でのコミュニケーションが減り、情報の共有や連絡が取りにくくなる傾向です。
特に、必ず勤務する必要がある時間帯(コアタイム)を設けないスーパーフレックスタイム制を導入した場合、従業員同士が顔を合わせる機会がさらに少なくなり、情報共有の遅延やチームワークの低下などを引き起こす原因となることがあります。
コミュニケーション不足は、緊急の判断や迅速な意思決定が必要な際に大きな妨げとなり得るため、注意が必要です。
こうした課題を解決するためには、Web会議システムやチャットツールなどを活用し、遠隔でのコミュニケーションを可能にするといった、何らかの対策を講じる必要があります。
勤怠管理が複雑になる
従業員の勤怠管理が複雑になることも、フレックスタイム制のデメリットの一つです。
一般的な労働時間制では、基本となる出退勤時間が全従業員で共通のため、勤怠管理は比較的シンプルになります。
一方でフレックスタイム制は、各従業員が自分の裁量で出退勤時間を決めるため、一人ひとりの出退勤時間がバラバラで複雑となり、勤務時間や労働状況を正確に把握するのが難しくなる傾向です。
また、勤怠管理にミスが発生すると、給与計算に誤差が生じたり、法定労働時間や36協定で定められた時間外労働の規定に抵触したりして、不要なトラブルを引き起こす原因になります。
よって、フレックスタイム制の導入は、人事や労務の管理を担当する部門の業務負担が増える可能性があります。
勤怠管理は、企業に従業員の数が多いほど複雑化するため、給与計算ソフトや勤怠管理システムなどを導入し、一人ひとりの従業員の勤怠状況を迅速かつ正確に把握できる体制を構築することが不可欠です。
職場の連帯感や結束力が低下する
フレックスタイム制の導入によって、従業員同士の交流が減ると、職場内の一体感や連帯感が薄れることがあります。
その結果、会社の結束力が失われ、企業文化やチームワークに悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、企業の生産性やブランド力が低下するおそれがあるので注意が必要です。
業務の進行や外部とのやりとりに支障が生じる場合がある
複数の従業員で1つのプロジェクトを進める場合、フレックスタイム制が業務の進行に影響を与える場合があります。
その理由として、特定の時間帯に業務に必要な従業員全員を集めることが難しくなるためです。
従業員間で同時に作業が確保できないと、事業の遅延や業務に非効率が生じる可能性があります。
また、フレックスタイム制では、従業員が企業にいる時間が不規則になるため、顧客やビジネスパートナーといった外部とのやり取りが必要な業務において、調整が難しくなる傾向です。
よって、通常の労働時間制を持つ顧客やパートナー企業との電話会議や商談のスケジューリングなどで、日程調整が複雑化する可能性が高まります。
そして、調整が複雑になればなるほど、人為的なミスが増えるおそれがあるため注意しましょう。
さらに、クライアントからの緊急連絡や突発的な会議などが発生した場合、対応が遅れてしまう可能性があることも考慮する必要があります。
自己管理ができない従業員への対応が求められる
企業は、フレックスタイム制を有意義に活用できている従業員とそうでない従業員がいることを理解しておく必要があります。
特に、時間の使い方が苦手な従業員は、フレックスタイム制の導入によって、業務効率が低下したりモチベーションが下がったりする可能性があります。
高い生産性を維持するためにも、業務内容や進捗状況を明確に把握できる仕組みを整え、適切なサポートを行うことが重要です。
もし、全体を通してフレックスタイム制の利用方法が十分に周知されていない場合、コアタイムやフレキシブルタイムの取り扱いなどを教える説明会やセミナーを設けましょう。

企業がフレックスタイム制を導入する際の注意点

企業がフレックスタイム制を導入・運営するにあたって、以下の注意点を意識しましょう。
・企業が労働時間の管理を行う
・時間外労働の計算は通常の労働時間制と異なる
・似たような制度(裁量労働制や変形労働時間制など)と混同しないようにする
・定例の会議や外部との打ち合わせなどを踏まえて、コアタイムを設定する
・偏りなくフレキシブルタイムを設定する
・コアタイムがないと遅刻・早退の概念がなくなる
・規定労働時間よりも実労働時間の方が長い場合、欠勤控除ができない
・休憩時間は通常の労働時間制と変わらない
・休日出勤をさせる場合、法定休日と割増賃金に気をつける
事前にこれらの注意点を踏まえて、フレックスタイム制を取り入れるかを検討しましょう。

フレックスタイム制の導入による企業の成功事例

フレックスタイム制を導入して成功した事例一覧を、企業ごとに以下の5社を紹介します。
・アサヒビール株式会社
・三井物産株式会社
・ソフトバンク株式会社
・アステラス製薬株式会社
・旭化成ホームズ株式会社
自社が目指している事例を参考にし、福利厚生の一環としてワークライフバランスの向上につなげてください。
アサヒビール株式会社|時間・場所に縛られない働き方でフレキシブルな対応を可能にした
アサヒビール株式会社は、全従業員が安全で健康に働ける環境を構築することが企業の使命と捉え、従業員にとって最も適したワークライフバランスが実現できるような取り組みを積極的に推進しています。
その取り組みの一環として、フレックスタイム制を導入しています。
単にコアタイムを設けたフレックスタイム制だけでなく、コアタイムのないスーパーフレックスタイム制も採用し、時間に縛られずに従業員のライフスタイルにあわせた柔軟な働き方を取り入れているのが魅力です。
こうしたアサヒビール株式会社の働き方への取り組みは、育児や介護が必要な従業員に対しても働きやすい環境を整備していると高く評価され、厚生労働省から「プラチナくるみん」の認定を受けています。
無駄な労働時間を削減するという考えのもと、ビデオ会議や在宅勤務制度なども取り入れ、生産性を落とすことなく成果を出し続けています。
参照元:アサヒビール株式会社「アサヒビールのサステナビリティ」
三井物産株式会社|フレキシブルタイムを幅広く設けたことでパフォーマンスの最大化につながった
大手総合商社の一つである三井物産株式会社は、働き方改革の一環として、全社的にフレックスタイム制を取り入れています。
同社では、10時から15時をコアタイムとし、フレキシブルタイムをそれぞれ5時から10時、および15〜22時と設定する範囲が幅広いのが特徴です。
これにより、従業員のワークライフマネジメントが向上したという報告が上げられています。
また、労働時間を従業員の判断に委ねることで、一人ひとりのパフォーマンスを最大限に引き出し、従業員エンゲージメントの向上にも貢献しました。
その他にも、インターバル時差出勤やリモートワーク制度も段階的に導入しており、従業員にとって働きやすい環境を整えています。
参照元:三井物産株式会社「働き方|三井物産の人材マネジメント」
ソフトバンク株式会社|スーパーフレックスタイム制によって従業員のワークライフバランスを維持している
ソフトバンク株式会社は、スーパーフレックスタイム制を導入し、従業員に自由な労働環境を提供しています。
同社は2017年からコアタイムを廃止し、1万人規模でのスーパーフレックスタイム制を導入しています。
これにより、従業員は勤務時間を自由に調整しやすくなったため、混雑を避けて通勤したりスキルアップの時間を確保したりするなど、メリハリのある働き方が可能になりました。
その他にも、以下のような取り組みを行っています。
・介護や育児との両立を支援する「時短勤務制度」の整備
・サテライトオフィスの利用促進
・毎月の最終金曜日に15時退社を勧める「プレミアムフライデー」の設置
・テレワークの実施
上記の取り組みを実施したことで、ワークライフバランスを維持し、すべての従業員が快適に働ける環境を実現しています。
参照元:ソフトバンク株式会社「スマートワークスタイルの推進」
参照元:ソフトバンク株式会社「SoftBank流 働き方改革」
アステラス製薬株式会社|柔軟な働き方により家庭との両立がしやすい環境が整っている
アステラス製薬株式会社では、グローバルな視点から魅力的な職場環境を築くことを目指しています。
社員一人ひとりの充実した生活と、生産性・創造性そして納得感のある働き方の両立を重視し、柔軟な働き方を積極的に推進しているのが特徴です。
同社では、フレックスタイム制の導入に加えて在宅勤務制度や、認可保育所に入れない場合に産休・育休からの復職者を支援する「託児費用補助制度(月最大16万円を最長6か月間の補助)」など、家庭との両立をサポートする制度を複数導入しています。
これらの取り組みは高く評価され、「プラチナくるみん」認定を受けています。
参照元:アステラス製薬株式会社「一般事業主行動計画公表サイト|企業データ詳細」
旭化成ホームズ株式会社|DXの推進や各種制度の充実により自分らしく働ける環境を実現している
旭化成ホームズ株式会社は、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進し、各種制度を充実させることで、従業員にとって働きやすい環境を実現しています。
具体的には、ワークライフバランスや生産性の向上を目的として、以下のような取り組みを実施しています。
・フレックスタイム制度の導入
・在宅勤務制度の実施
・フリーアドレスの活用
・有給休暇・育児休業の取得促進
・マネージャーを対象にした考課者勉強会
・職場環境向上に向けた委員会活動
・イントラネットの導入
・施工力把握と現場管理の精度向上を目的としたシステム「A-Smart」の活用
・工事ごとの施工記録を保管する「A-Skai工事報告書システム」の利用
最新のテクノロジーを活用した業務の効率化も同時に進めることで、従業員のパフォーマンスを最大限に発揮し、より効率的に働ける環境を実現できます。

フレックスタイム制が普及しやすい職種・導入が難しい職種

フレックスタイム制は、従業員の自由な働き方を促し、企業にも数多くのメリットがありますが、すべての業界に適しているわけではありません。
ここでは、フレックスタイム制が普及しやすい職種と、反対に導入が難しい職種について紹介します。
関連記事:フレックスタイム制はなぜ普及しない?ずるい?デメリットは?を全て解説
フレックスタイム制が普及しやすい職種
一般的に、個人の裁量で業務を進めやすく、ある程度独立して取り組める仕事は、フレックスタイム制との相性が良いといわれています。
たとえば、厚生労働省が実施した「就労条件総合調査(令和3年)」の資料によると、フレックスタイム制の導入率が高い業種は以下のとおりです。
| 業種 | 説明 |
| 情報通信業(30.0%) | ・通信業や放送業(メディア業)、情報サービス業やインターネットに附随したサービス業などが挙げられる ・その中で、システムエンジニアをはじめとしたエンジニアやプログラマー、Webデザイナーなどの職種は、個人の裁量で仕事を進行・完結できるケースが多いため、特にフレックスタイム制の導入率が高い |
| 金融・保険業(14.7%) | ・他の業種よりも女性の比率が高い傾向にある ・妊娠・出産、育児や介護などによってライフスタイルが変化しやすい女性が働きやすいよう、フレックスタイム制を導入している企業が多い |
| 電気・ガス・熱供給・水道業(14.2%) | ・人々のライフラインに直結する業務のため、基本的に24時間365日体制で稼働している ・その分、従業員の働き方に柔軟性を持たせるという意味では、フレックスタイム制の導入率が高い |
その他にも、外部からの影響が少なく、作業の区切りをつけやすい事務職や企画職も、フレックスタイム制は適しています。
参照元:e-Stat 政府統計の総合窓口|就労条件総合調査(令和3年)
フレックスタイム制の導入が難しい職種
労働時間配分の自由度が高いことが、かえって業務に悪影響を及ぼすおそれがある職種が存在します。
そのような職種は、フレックスタイム制があまり適していません。
たとえば、以下の職種が一例として挙げられます。
・社内外との頻繁な連絡が欠かせない営業職や営業アシスタント
・持ち場を離れられない接客サービス業
・特定の場所での業務が必須となる工場作業員
・他の部署との連携が密な職種
・取引先と頻繁なやり取りが求められる職種
・複数人でチームを組んで一つのプロジェクトに携わる職種
フレックスタイム制を導入すると、通常の労働時間制を持つ取り引き先との時間をあわせるのが難しくなり、商談や打ち合わせ、会議などの進行に支障が出るおそれがあります。
また、チーム内での出勤時間がばらつくと、従業員同士の密な連携やコミュニケーションができなくなり、業務の進行が遅れて生産性の低下につながる可能性があります。
したがって、フレックスタイム制を導入する際は、業務の特性やチームの働き方、そして必要なコミュニケーションのあり方を十分に考慮することが重要です。

企業がフレックスタイム制を導入する際の流れ

フレックスタイム制の導入は、企業と従業員の双方にとって大きな変化をもたらします。
そのため、不要な混乱を避けるためにも、適切な手順を踏んで慎重に進めることが重要です。
ここでは、フレックスタイム制の導入手順を紹介します。
・対象となる部署や従業員を決める
・就業規則に規定を定める
・労使協定を締結する
・労働基準監督署長に届け出る
・企業全体に対して周知を徹底する
それぞれ順を追って解説します。
対象となる部署や従業員を決める
フレックスタイム制を導入するにあたって、まずは対象となる部署や従業員を定めることが大事です。
業務の性質上、すべての部署や従業員に対して、フレックスタイム制を導入するのは難しいです。
そのため、各部署の管理者や必要に応じて各従業員に対して、フレックスタイム制の概要に関する研修を個別で実施し、業務内容に支障が生じないかを事前に相談・確認したうえで、フレックスタイム制を取り入れましょう。
就業規則に規定を定める
常時10人以上の従業員がいる企業にフレックスタイム制を導入する際は、就業規則に始業および終業時刻を対象となる従業員の決定に委ねる旨を明記しなければなりません。
また、コアタイムやフレキシブルタイムを設定する場合、それぞれの時間帯や内容についても就業規則に記載することも求められます。
就業規則を新たに作成したり変更したりする場合は、行政官庁への届出が義務付けられています。
もし、就業規則の作成や届出を怠った場合、30万円以下の罰金が科される可能性があるので注意しましょう。
労使協定を締結する
フレックスタイム制を取り入れるときは、労働組合(組合がない場合は従業員の代表者)と企業の間で書面による労使協定を締結することが求められます。
労使協定には、主に以下の項目を中心に定める必要があります。
・フレックスタイム制を適用する従業員の範囲
・清算期間(労働時間を計算する期間)およびその起算日
・清算期間内の総労働時間(所定労働時間)
・標準となる1日の労働時間
・コアタイム(任意)
・フレキシブルタイム(任意)
・超過時間および不足時間の取り扱い
・有効期限(清算期間が1か月を超える場合)
なお、就業規則に規定を定め、労使協定を結んだとしても、18歳未満の従業員にはフレックスタイム制を適用できない点には注意が必要です。
労働基準監督署長に届け出る
就業規則に変更があった場合や、フレックスタイム制の清算期間が1ヶ月を超える労使協定を結んだ場合は、管轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
もし、届出を怠ると罰則が科されるおそれがあるため、忘れずに手続きを行いましょう。
企業全体に対して周知を徹底する
一通りの手続きを済ませたら、フレックスタイム制に関する内容を企業全体に徹底して周知しましょう。
変更内容の周知を怠ると、就業規則の変更は有効になりません。
そして、今後の円滑なフレックスタイムの運用をするためにも、導入の背景や目的、メリット・デメリットなども従業員にしっかりと伝える必要があります。
特定の部署や従業員のみに対して、フレックスタイム制を導入する場合であっても、関連する部署や従業員への情報共有は欠かせません。
同様に、取り引き先にもフレックスタイム制の導入について伝え、理解を促しましょう。
また、フレックスタイム制の導入が企業に及ぼすリスクやデメリットを、できる限り最小限に抑えるための対策を講じることも重要です。
たとえば、取引先への対応強化として担当者を増員したり、コアタイムにあわせて会議時間を調整したりするなどが挙げられます。
こうした対策を実施することで、フレックスタイム制をスムーズに導入し、効果的な運用を実現できます。
まとめ:フレックスタイム制を導入するときは企業全体で話し合って正しい理解を得よう!

フレックスタイム制を導入することで、従業員はワークライフバランスが向上したり、業務や通勤ラッシュなどによる負担を軽減できたりします。
これにより、企業は生産性や従業員の定着率を高められ、労働者の満足度とモチベーションをアップできます。
ぜひ、本記事で紹介した各企業の成功事例を参考に、企業全体での話し合いを通して正しい理解を得てから、フレックスタイム制の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>