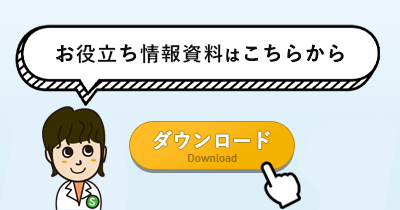年末年始の有給取得ルール徹底解説|休暇促進とトラブル回避の実践ガイド
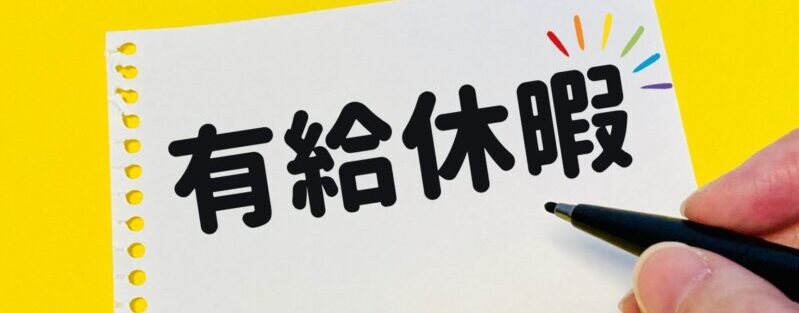
こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。
年末年始は、多くの人にとって1年の疲れを癒やし、新しい年に向けてリフレッシュする大切な時期です。しかし同時に、「有給休暇は自由に使えるのか」「年末年始休暇とどう違うのか」「繁忙期に休んでも大丈夫なのか」といった不安や疑問を抱く会社員も少なくありません。実際、法律で保障された権利であるにもかかわらず、日本の有給取得率は依然として低水準にとどまっています。特に年末年始は休暇希望が集中しやすいため、申請が通らなかったり、同僚との不公平感が生まれたりと、トラブルの原因にもなりがちです。だからこそ、労基法に基づく基本ルールを正しく理解し、会社ごとの制度や計画的付与を柔軟に活用することが欠かせません。本記事では、年末年始に押さえておきたい有給取得ルールを徹底解説し、休暇促進とトラブル回避のための実践的な対策をご案内します。
福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉
目次
年末年始に押さえておきたい有給取得ルール

労基法で定められた有給休暇の基本ルール
年次有給休暇(年休)は労働基準法によって定められた、すべての労働者に平等に与えられる権利です。入社から6か月以上継続して勤務し、出勤率が8割以上であれば、10日間の有給休暇が付与されます。その後は勤続年数に応じて増加し、最長で20日まで付与される仕組みです。付与された有給休暇は2年間有効で、未消化分は翌年度に繰り越すことが可能です。重要なのは、この有給休暇は労働者が「自由に取得できる」ことが原則とされている点です。会社側が時季変更権を行使する場合もありますが、それは業務に著しい支障があるときに限られます。法的にもしっかりと認められた正当な行動なので、これからも年末年始に有給を組み合わせて長期休暇を作ることは可能です。
年末年始休暇と有給休暇の違い
多くの会社員が誤解しやすいのが「年末年始休暇」と「有給休暇」の違いです。年末年始休暇は、会社が就業規則や慣例に基づき一斉に休業日とするもので、12月29日から1月3日までの6日間を設定しているケースが一般的です。一方で有給休暇は、労働者一人ひとりに付与される休暇であり、本人の意思で自由に申請・取得できるものです。つまり、会社が定めた年末年始休暇は“全員一律の休日”であるのに対し、有給休暇は“個人が選択して休む権利”だと言えます。年末年始をより充実させるためには、この違いを理解し、柔軟に計画を立てて活用することが重要です。
会社ごとに異なる年末年始の休暇制度
年末年始の休暇制度は会社によって大きく異なります。たとえば製造業や金融業などでは年末年始に長期休暇を設定する企業が多く、10日近くの休みを設けるところもあります。一方で、サービス業や小売業、医療・介護の分野では、年末年始がむしろ繁忙期にあたり、休暇が短縮されたり、交代制で勤務が必要となるケースが少なくありません。さらに、一部の企業では「年末年始特別休暇」として有給とは別枠の休日を設けている場合もあります。自分の会社がどの制度を採用しているのかを理解することが、計画的な有給取得の第一歩です。同じ“年末年始休暇”という言葉でも、勤務先によって内容は大きく異なるため、就業規則を見直し、手続きの流れを確認しながら正確に把握しておきましょう。
計画的付与制度を利用した有給取得のポイント
有給休暇を計画的に消化する仕組みとして「計画的付与制度」があります。これは、労使協定を結ぶことで、付与される有給休暇のうち5日を超える部分について、会社側があらかじめ取得日を指定できる制度です。例えば、年末年始やお盆など、多くの社員が一斉に休みを取りやすい時期に設定することで、社員は安心して休暇を取得でき、企業側も業務を効率的に管理できます。これにより、有給消化率の向上や、計画的な休暇取得の促進が期待できます。年末年始に計画的付与が適用される会社であれば、カレンダーに合わせて自動的に長期休暇が作れることもあります。制度が導入されているかどうかは就業規則や労使協定で確認できますので、これからの働き方を見直す上でも、自分の会社のルールをしっかり押さえておくことが重要です。
参考:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf

有給取得の現状とよくある悩み

「有給休暇は取りにくい」という会社員の懸念
有給休暇は法律で定められた権利であるにもかかわらず、多くの会社員が「本当に自由に取れるのだろうか?」という疑問を抱いています。実際、日本の有給休暇の取得率はOECD諸国の中でも低い水準にあり、職場の雰囲気や上司の姿勢によって申請のしやすさが大きく左右されるのが現状です。特に年末年始は誰もが休みたい時期であるため、「自分だけ休むと迷惑になるのでは?」という心理的なプレッシャーが強まります。このため、有給を取ること自体が遠慮され、結果として権利が十分に行使されないまま消化期限を迎えてしまうケースも少なくありません。疑問を解消するためには、有給休暇が「労働者に必ず付与される権利」であることを再認識することが大切です。さらに、上司や同僚と早めに相談し、堂々と計画的に申請することで取りにくさを緩和できます。
年末年始に集中する休暇申請の課題
年末年始は多くの社員が同時期に休暇を希望するため、申請が集中しやすい時期です。特に帰省や旅行を予定している人は、限られた期間に有給を重ねたいと考えるため、同じ日程に希望が集まりがちです。その結果、業務が停滞するリスクが高まり、上司や管理職の判断によっては希望が通らないこともあります。こうした課題を解決するためには、まず「申請の早さ」が重要です。早めに有給取得の希望を出すことで優先度が上がり、他の社員との調整も円滑になります。また、会社によっては「申請締め切り」や「抽選方式」を導入するなど、公平性を担保する工夫をしている場合もあります。年末年始に有給をしっかり取るためには、自分の予定をできるだけ前倒しで確定させ、早めに職場へ伝える姿勢が欠かせません。
繁忙期ならではの業務調整の難しさ
年末年始は多くの企業にとって特別な時期です。営業職であれば年末の取引先対応や新年の挨拶準備、経理では年末調整や決算関連業務、物流や小売業では繁忙期の対応など、通常よりも業務が立て込みやすくなります。このような状況で有給休暇を取得しようとすると、業務の引き継ぎや分担が不十分になり、同僚や取引先に影響が出るリスクがあります。そのため、繁忙期に休む際には「前倒し作業」と「引き継ぎの明確化」が不可欠です。具体的には、休暇前にできるだけ業務を片付け、残るタスクについては担当者を明示しておくことが重要です。さらに、緊急対応が必要になるケースを想定し、連絡手段をチームに伝えておくのも有効です。繁忙期だからこそ、事前準備を徹底することで安心して有給を活用できるのです。
休暇取得で生じやすい同僚との不公平感
年末年始に有給を取得すると、職場によっては「誰かが休めば誰かが働く」という構図になりがちです。そのため、同僚との間で不公平感が生じやすいのも大きな悩みです。特に少人数の部署や、業務が属人化している職場では、1人が休むと残りのメンバーに大きな負担がのしかかります。この状況は、不満や摩擦の原因となり、休暇を申請しにくい雰囲気を作り出します。これを解消するには、チーム全体で「休暇の見える化」を進めることが大切です。社内カレンダーや共有ツールで予定をオープンにし、休暇取得の公平性を担保する仕組みを作ると不満は軽減されます。また、引き継ぎを丁寧に行うことで「迷惑をかけない」という姿勢を示せば、同僚の理解も得やすくなります。お互いに休暇を尊重し合う文化が根付くことで、不公平感の解消につながります。

有給取得促進につながる工夫

早めのスケジュール共有とチーム内調整
有給休暇の取得をスムーズに進めるためには、個人の申請タイミングだけでなく、チーム全体でのスケジュール共有が欠かせません。特に年末年始は多くの社員が休暇を希望するため、同じ時期に申請が集中すると調整が難しくなり、トラブルの原因となります。これを防ぐには、早めに自分の予定を周囲に伝えることが基本です。社内カレンダーや共有システムを活用して誰がいつ休むのかを見える化すれば、休暇の重複を減らしやすくなります。さらに、チーム内で「誰がどの業務を引き継ぐか」を事前に決めておくことで、業務の停滞も防げます。早めの情報共有は、上司の承認をスムーズにする効果もあり、職場全体に安心感をもたらします。結果として、有給取得のハードルが下がり、計画的な休暇促進にもつながるのです。
管理職による有給取得促進の声かけ
有給休暇の取得を促進するうえで重要なのが、管理職の姿勢です。上司が率先して休暇を取り、部下にも積極的に声をかけることで、職場には「有給を取って良い」という前向きな雰囲気が広がります。逆に、上司が全く休まず「有給を取らないのが当たり前」という空気があると、部下も申請しづらくなってしまいます。年末年始のように休暇希望が集中する時期には、管理職が「早めに申請してね」「交代で休もう」といった声かけをすることで、計画的な取得が進みやすくなります。また、面談や定例会で「有給取得率」や「残日数」を確認し、取得を推奨するのも効果的です。管理職自身が模範を示しながら部下に働きかけることが、組織全体での有給取得促進を実現する大きな力になります。
会社全体で取り組む有給取得促進の仕組み
有給休暇を職場全体で取りやすくするためには、個人や部署の努力だけでなく、会社全体での仕組みづくりが必要です。政府も「年5日の有給取得義務化」などの施策を進めていますが、制度があるだけでは十分に機能しません。例えば、会社が「有給推奨日」を設けて一斉に休めるようにしたり、残日数を見える化して取得を促す仕組みを整えたりすることで、従業員は安心して休暇を計画できます。また、年末年始のような繁忙期でも、事前に休暇を組み込んだスケジュールを作成することで公平性を担保できます。さらに、人事部門が定期的に取得状況を確認し、取得率の低い部署に働きかけを行うことも有効です。会社全体で「休みやすい文化」を育てる取り組みが、従業員満足度や働き方改革の推進にも直結します。
業務の前倒しと分担でスムーズに休める環境づくり
有給休暇を安心して取得するためには、休む前の業務整理が非常に重要です。特に年末年始は業務が集中しやすいため、前倒しでタスクを処理しておかないと、休暇中に同僚へ負担をかけることになりかねません。そのため、休む前には「やるべき業務」と「引き継ぐ業務」を仕分けし、必要に応じて周囲に分担を依頼することが大切です。また、属人化している仕事を減らし、チームで共有できる仕組みを日頃から整えておくことも効果的です。例えば、業務マニュアルの作成や進捗管理ツールの活用によって、誰でも作業を引き継げる体制を整えると安心です。こうした準備を徹底することで、自分も安心して休めるだけでなく、同僚にも余計な負担を与えません。結果的に、職場全体で休暇取得がしやすくなる環境が育まれ、有給取得促進にも直結します。

まとめ

年末年始の有給休暇を充実させるためには、まず「労基法で定められた基本ルール」を理解することが出発点です。有給休暇は労働者の権利であり、会社が必要に応じて日程を変更できる場合はありますが、原則として自由に取得できるものです。さらに、年末年始休暇と有給休暇の違いを正しく押さえ、会社ごとの制度や計画的付与制度を柔軟に活用すれば、より効率的に長期連休をつくることが可能になります。しかし一方で、年末年始は誰もが休みを希望するため、申請が遅れると予定が合わず、同僚との不公平感や業務停滞といったトラブルが発生しやすいのも現実です。だからこそ、早めのスケジュール共有や丁寧な引き継ぎ、チーム内での調整が欠かせません。また、管理職や会社全体で有給取得促進の取り組みを行うことで、職場に「休んでも大丈夫」という文化が根づきます。こうした仕組みを支えるには、一人ひとりが意見を出し合い、質問やお願いをしやすい雰囲気づくりも重要です。結果として、誰もが安心して休暇を計画できるようになります。年末年始は旅行や帰省、リフレッシュの絶好の機会です。案内されたルールや制度を活用し、トラブルを回避しながら計画的に取得することで、新しい年を心身ともに健やかに迎えられるでしょう。
福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>