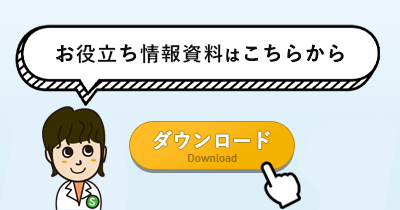輸入コスト高騰時代の福利厚生戦略|円安・物価高を乗り越えるコスト削減を見直す管理方法とは?

こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。
輸入コストが高騰し続けている今の時代は、企業における福利厚生でも戦略的な姿勢が求められています。
円安と物価高を乗り越えるためには、従来の制度のままではなく適宜適切な見直しも必要です。
この記事では、輸入コスト高騰時代に円安と物価高を企業が乗り越える福利厚生戦略の見直し策を解説します。
福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉
目次
【貿易・関税・物流・輸送etc…】 海外からの輸入コスト高騰の現状と日本企業への具体的影響

貿易の課題、関税、物流…とさまざまな要因が絡まって海外からの輸入コストが高騰し続けている現状は、企業に大きな影響が発生しています。
主な影響について解説します。
円安による原材料・食材・日用品コストの上昇が発生
近年、円安が加速していることによって輸入に依存する多くの原材料や製品の価格が上昇しています。特に2022年以降の円安基調は顕著で、小麦や食用油、燃料、日用品など、企業活動に不可欠な資源の価格が上がり続けています。こうした価格上昇は製造業に限らず、飲食、流通、小売などの幅広い業種で調達コストを引き上げ、企業経営に大きな圧力を与えています。
業務に欠かせない物資の高騰は企業の仕入れコストを直撃していることから、仕入れ価格への注目は、これまで以上に重要な視点にならざるを得ません。
また関税や国際物流コスト・国内における輸送コストの上昇といった影響による不透明な要素も多いことから、多くの企業にとって不安が大きくなっています。
福利厚生における「見えにくいコスト増」の常態化
コスト増の影響は、目に見える材料費や光熱費だけではありません。
円安や物流コスト上昇における影響は直接的な原材料費だけでなく、企業が提供する福利厚生のコストにも波及しています。
社内食堂で提供されるランチや、オフィスに設置された無料のドリンク・軽食など、従業員向けの無償または低価格のサービスに用いる物資も値上がりを続けています。たとえば社員食堂で使う油や冷凍野菜ひとつとっても値上がりしていますし、無料ドリンクの見直しや副菜を一品削るなどから「気付かないうちにじわじわと質の低下」が起きているのも現実です。
これらは一見すると小さな支出に見えても、年間を通じて積み重なることで「見えにくいコスト増」の常態化となり、企業の総支出に大きく影響しています。
食堂運営や飲料・軽食で見られるコスト圧迫を象徴する影響例は?
ほんの一例ではありますが、輸入コスト増の影響を受けたケースを挙げると、次のようなものがあります。
これはどんな事業所にも起こりうる典型的なパターンとも言えるでしょう。
・社員食堂で提供する定食のコストが昨年比で1食あたり30〜50円上昇したことから、従業員負担を増やさないように価格据え置きを行った結果として年間で数百万円規模のコスト増となった事例
・オフィスで提供していた無料コーヒーやスナック類について、仕入価格の上昇を理由に内容量の見直しや提供回数の制限を行っている事例
こういった例は、日常のオペレーションに潜むコスト圧迫の実態を象徴しています。

【コスト高騰を乗り切る企業の視点】 日本の企業で福利厚生制度の見直しが今、必要な理由

コスト高騰が叫ばれている今こそ、福利厚生制度の見直しが求められている理由について解説します。
“福利厚生=コスト”ではなく「投資」として再定義する必要性
物価上昇の影響を受け、福利厚生にかかる費用が増加している今こそ、その捉え方を見直すべき時期に来ています。福利厚生は従来では「コスト」とみなされることが多く、不況時には真っ先に削減対象となることもありました。
しかし現代では削減一辺倒ではない建設的な制度の見直しが求められ、従業員の満足度や働きやすさに直結する重要な“投資”として捉える視点が主流となってきています。
適切な福利厚生は人材の流出を防ぎ、生産性を高める原動力となるという視点からも、各企業では再定義が進められています。
従業員満足度と企業の生産性・定着率との関連
福利厚生の充実は従業員のエンゲージメントを高め、企業への愛着や忠誠心を育みます。
その結果として離職率の低下や社内コミュニケーションの活性化、生産性の向上といった好循環も生まれやすいでしょう。
今の時代に働き手が企業に求める価値は「給与」だけではなく「働く環境と安心感」という側面も強いことから、福利厚生が従業員の満足度に与える影響は従来よりも大きくなってきています。
満足度の高い職場環境であれば従業員が長期的に働き続けやすくなるため、採用・教育にかかるコストの削減にもつながります。また、働きやすさが確保されることで業務効率も向上し、企業の収益性にも好影響を与える可能性が広がります
【最新情報に注意!】 変化に応じた柔軟な制度設計が求められる時代背景
働き方改革や多様な人材の活用が進むなかで、従来型の一律型福利厚生ではニーズに応えきれなくなってきている現状もあります。
また、働き方の多様化や経済情勢の変化が著しい現代においては、画一的な制度では従業員のニーズに応えることが困難になりつつあります。
具体的にはフレックスタイム制やリモートワーク支援、ポイント制の福利厚生など、柔軟かつ選択肢のある設計が求められているほか、変化に対応できるよう従来よりも実効性の高い福利厚生制度の構築も望まれています。
近年におけるライフスタイルの変化やテレワークの普及、物価の変動といった急速な社会変化に対応しながらも、コスト効率と満足度のバランスを図る施策が重要です。
柔軟かつ個別対応可能な制度設計によって、企業としての持続可能性が高まると考えられています。

【実践的な取り組み事例】 課題が山積する円安・物価高に対応する見直し策の具体案

ここでは課題が山積している円安・物価高に対応するべく、具体的な見直し策について解説します。
企業側の視点で、実践しやすいポイントをまとめました。
地産地消・国産品の積極活用を検討
輸入コストの高騰に対応するためにも、調達構造の見直しは有効な方法です。
たとえば社員食堂で地元の農産物や国産品を優先的に利用すれば、輸送コストの削減と安定的な価格確保を実現できますし、コスト削減と地域貢献を両立する術にもなるでしょう。
また地域経済への貢献という視点も含めて、企業価値、ブランディングの向上にもつながります。
現物支給からポイント・選択制への移行
社内カフェや軽食提供などの「現物支給型」での福利厚生は、コスト管理が難しい側面もあります。
その代わりに、福利厚生ポイント制度や電子クーポン制度といった「社員による選択型」を導入すれば、不要な支出を抑えられ予算管理の透明性を図れると同時に従業員満足の両立まで目指しやすい選択となるでしょう。
柔軟性のある選択制の仕組みは、従業員一人ひとりのニーズに合う対応をしやすいメリットもあります。
福利厚生の共同購買・外部委託によるコスト最適化
福利厚生の一部を外部企業に委託したり、他社と共同で仕入れを行ったりして、スケールメリットを享受する方法もあります。
単独企業での調達では、コスト削減効果にも限界があります。たとえば福利厚生食材や備品なども共同購買を選択肢に入れると、1社あたりのコスト負担を大きく軽減できるでしょう。

【ビジネスメリットを重視】 福利厚生の再構築によって企業が得られる効果

福利厚生の再構築によるメリットは、決して小さくありません。つまり、再構築を後回しにするほど得られる効果が先送りになるとも言えるでしょう。
再構築によって得られる効果を、企業側の目線で解説します。
コスト削減と従業員満足度向上の両立
福利厚生制度の再構築は、限られた予算でも従業員の満足度を上げる方法です。
たとえば、選択制やデジタル化によって従来から続く無駄は削減しながらも個々のニーズに合ったサービスを提供できれば、コストと満足のバランスが取りやすくなっていくでしょう。
今の時流における福利厚生は会社が一方的に与えるのではなく、従業員にとって「自分のための制度」と感じられることがポイントで、これが社員のモチベーションにもつながっていきます。
離職率の低下・採用力の向上など従業員の環境整備
整備された福利厚生制度は、働きやすい環境を支える基盤です。
従業員の定着率向上や離職率の低下につながるほか、求職者へのアピールポイントとしても有効な施策でしょう。
特に若年層は「働きやすさ」や「ワークライフバランス」を重視する傾向が強く、制度の充実は採用競争力を高めるカギにもなりえます。
人材流出を防ぐ効果だけでなく、企業ブランディングの一環としての価値のある取り組みです。
サステナブル経営や地域貢献への波及効果
福利厚生の見直しは単なる社内施策に留まらず、企業の社会的責任(CSR)やESG経営の一環としても機能します。
たとえば地産地消の推進や地域産業との連携は、地域経済への貢献を通じて企業の信頼性を高める取り組みとなるでしょう。また地域イベントへの参加は、地域の最新情報を得る貴重なチャンスにもなりえます。
企業の環境意識が問われがちな今こそ、地域社会との連携による相乗効果や波及効果は、持続可能な経営の土台づくりにも寄与します。

【リスクが少ないコスト削減の最適化】 原材料や輸入コスト高騰における今後の展望と企業に求められる姿勢

原材料や海外からの輸入コストの高騰は、しばらく継続すると見込まれています。
現時点での今後の展望と、企業に求められている姿勢についてまとめました。
海外からの輸入コストの高止まりは、一過性ではない
今起きているコスト高騰には、地政学的リスクや円安基調の継続などの外部要因が複雑に絡み合っていることから、輸入コストの高止まりは一過性ではなく、今後もしばらくは続く中長期的な課題といえるでしょう。
企業はこの前提を受け入れ、継続的にコスト構造を見直す必要が求められています。
自社の価値観に沿った制度の再設計がポイント
制度を見直す際には、単にコストカットを目的とするのではなく「自社は何を大切にし、どんな従業員体験を提供したいのか」という理念に基づいた再設計が求められます。
“自社らしさ”をうまく福利厚生に反映させられれば、企業のブランド価値も高まる一助にもなるでしょう。
つまり他社が行なっている施策をそのまま真似るのではなく、自社の特性や従業員のニーズに合った施策を組むことが大切です。
継続的な見直しと従業員との対話が将来の差を生む
今の時代に求められているのは、目まぐるしく変化をするコスト高騰環境に応じた柔軟な見直しと、従業員との継続的なコミュニケーションです。つまり、制度を構築したあとに「つくりっぱなし」にしない心がけも大切です。
制度の形骸化を防ぐためにも関係者の意見を取り入れながら改善を重ねることは有益で、従業員の信頼と納得感を醸成しながら持続可能な経営基盤を築く術になるでしょう。
対話の有無によって施策による将来の効果への差も生じますし、実効性の少ない施策を実施するリスクを回避する術にもなります。

【企業の持続可能性を視点に】 単純な削減でなく「質を保つ賢いコストダウンを」

円安・物価高という外的要因に対して企業が抗うことは難しいものの、どう向き合ってどう対応するのかは企業次第です。
コスト高騰への施策が単なる削減ではなく「質を保ちながら無駄を省く」「削るのではなく工夫をする」という“賢いコストダウン”になれば、持続可能な企業運営の一助となります。
福利厚生はその好例であり、今こそ制度の見直しを通じて、従業員と企業双方が納得できる価値を創出していくことが求められていると言えるでしょう。
福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら〉〉