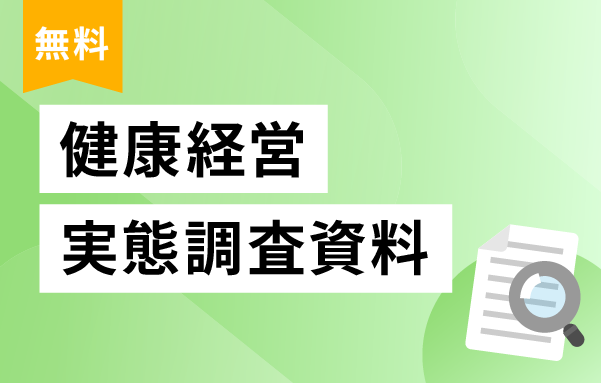最新のスポーツエールカンパニー認定基準と成功事例を2026年版で紹介

こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。
企業の健康経営や福利厚生への関心が一段と高まる中、「スポーツを通じた企業価値向上」を目指す動きが広がっています。従業員の運動促進を支援する「スポーツエールカンパニー」は、まさにその中心的な施策として注目を集めています。スポーツ庁が認定するこの制度は、働き盛り世代の運動不足を解消しながら、生産性向上や職場コミュニケーション改善といった経営効果も期待できる取り組みです。2026年版では、運動習慣の定着や経営層のコミットメント、データ活用など「効果が続く仕組みづくり」が一層重視され、制度としてさらに進化しました。本記事では、最新版の認定基準や変更点を踏まえつつ、実際に成果を上げている企業の成功事例までわかりやすく紹介します。
福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉
目次
スポーツエールカンパニーとは?

制度の目的と概要
スポーツエールカンパニーとは、従業員の健康増進を目的に「日常的なスポーツ活動を推進する企業」をスポーツ庁が認定する制度です。運動機会の提供や社内イベントなど、従業員が自発的に体を動かす環境づくりを行っている企業が対象となります。認定を受けた企業は、公式ロゴの使用が許可され、健康経営の取り組みとして広報活動にも活用できます。スポーツを通じて心身のリフレッシュを促し、社員同士のコミュニケーション活性化や生産性向上にもつながる点が特徴です。単なる“健康促進”に留まらず、企業文化として運動を定着させることを目的とした制度といえます。
スポーツ庁が創設した背景
スポーツ庁がスポーツエールカンパニー制度を創設した背景には、働き盛り世代の深刻な運動不足があります。特に30〜50代は仕事や家庭の多忙さから運動時間を確保しにくく、生活習慣病やメンタル不調のリスクが高まる傾向にあります。こうした課題を解決するため、国は「働く人が自然に運動できる社会づくり」を目指して企業を巻き込んだ取り組みを開始しました。企業にとっても、社員の健康維持は医療費削減や生産性向上、離職率低下などに直結する重要な経営課題です。スポーツを軸にした健康経営の推進は、企業と従業員の双方にとって大きなメリットをもたらしています。
認定数の推移・対象企業の傾向(2025→2026)
スポーツエールカンパニー制度は年々広がりを見せており、2025年には全国で**1,354社(団体)**が認定されました。2026年も引き続き関心は高く、企業規模や業種を問わず多様な組織が申請に参加しています。特に中小企業や自治体、医療・教育・サービス業など、これまで運動推進が難しかった業界からの応募が増加している点が特徴です。
また、2026年版では「スポーツエールカンパニーPLUS(プラス)」の認定制度が継続され、単なる運動奨励にとどまらず、経営戦略としてスポーツを位置づけている企業が高く評価されるようになりました。デジタルツールを活用した健康データの見える化や、社員の自発的な運動参加を促すインセンティブ設計など、より実効性のある取り組みが求められています。
全体として、「スポーツ=福利厚生」から「スポーツ=企業価値向上の一要素」へと進化しており、健康経営とブランディングを両立する企業が増加しています。
参考:文部科学省スポーツ庁 スポーツエールカンパニー2026募集要項

2026年版の認定基準と変更点

2026年版の基本方針と新たな評価視点
スポーツエールカンパニー2026では、「働く世代の運動実施率向上」と「職場での運動機会の定着」をより明確に掲げています。これまでの単発的な運動奨励から一歩進み、社員が“自ら参加したくなる仕組み”づくりが評価対象になりました。特に2026年版では、企業が実施する運動プログラムの「継続性」「波及効果」「経営層の関与度合い」を重視。運動機会の創出だけでなく、職場文化として定着しているかが審査のポイントです。また、健康経営優良法人やホワイト企業認定との連携を意識し、従来よりも経営戦略の一部として健康づくりを推進する企業を高く評価する方針へと進化しました。
認定対象となる企業・団体の条件(2026年版)
2026年も、民間企業、地方公共団体、医療・教育機関、NPO法人など、幅広い団体が対象です。
応募条件としては、
①従業員のスポーツ・運動機会を提供していること
②取り組みを社内外に発信していること
③活動の継続性が見られること
の3点が中心となっています。新たに、オンライン・ハイブリッド形式での実施や、地域連携型イベントなども正式に認定対象に含まれました。これにより、リモート勤務が多い企業や多拠点展開の組織でも取り組みやすくなっています。また、従業員数の規模を問わず「小規模でも実行可能な健康づくり」が評価される点も中小企業にとって追い風です。
スポーツエールカンパニー「プラス(PLUS)」の継続と評価強化
2025年から導入された「スポーツエールカンパニーPLUS」は、2026年も継続され、評価基準がさらに明確化されました。PLUSは、通常認定企業の中でも特に先進的で効果的な取り組みを行う企業を選出する制度です。
2026年版では、
①数値目標を設定して運動実施率を改善している
②経営層が積極的に関与している
③地域や他社と連携して取り組みを拡大している
などの観点が追加されました。単なる「運動を奨励する企業」ではなく、「スポーツを企業経営に戦略的に組み込む企業」が選ばれる傾向が強まっています。認定ロゴの使用やメディア紹介など、広報面での効果も期待できます。
提出書類・報告内容の変更点
2026年は、提出書類の様式が見直され、より具体的な記入が求められるようになりました。申請書では、活動の実施内容に加えて「目的」「頻度」「参加人数」「実施後の効果」などを定量的に記載する欄が新設されています。これにより、従来の「実施した事例の羅列」ではなく、「成果につながる取組」であることを示すことが重要になりました。また、活動写真や社内広報物の添付を推奨しており、取り組みの“見える化”が重視されています。報告内容を社内で定期的に蓄積しておくことで、次年以降の申請をスムーズに行うことができます。
申請スケジュールと審査プロセス(2026年版)
2026年の申請期間は、2025年9月16日(火)~11月14日(金)とされています。申請はスポーツ庁ウェブサイト上で行い、原則としてWEBフォームにて必要事項を入力し、申請をします。審査は書類選考のみで、12月頃に審査会を実施し、翌年1月下旬に認定結果を発表予定です。審査では、活動の具体性や継続性に加え、「経営層の関与」「社内外への発信度合い」「地域との連携」もチェック項目です。また、認定後には活動報告書の提出が求められ、翌年以降の継続認定の参考となります。審査体制の透明化が進み、企業が自らの取り組みを客観的に振り返る機会にもなっています。
健康経営との統合的推進と今後の方向性
2026年版では、スポーツ施策を単体のCSR活動として扱うのではなく、企業の健康経営戦略と一体的に推進する方針が示されています。スポーツエールカンパニー認定を「健康経営優良法人」「スマートワーク経営」「ホワイト企業認定」などと組み合わせることで、より高い評価を得る企業が増加。スポーツは生産性向上、離職率低下、メンタルヘルス改善など多面的な効果をもたらすため、経営の重要指標として位置づけられています。今後は「運動+食事+メンタルケア」を含む包括的な健康支援が求められ、企業の社会的責任(ESG・SDGs)の観点からも注目されています。

スポーツエールカンパニーの成功事例

大東建託パートナーズの取り組み
大東建託パートナーズでは、社員全員が運動を楽しめる環境づくりをテーマに、朝礼でのストレッチや「歩数対抗ウォーキングイベント」を実施しています。部門別に競い合うチーム戦を採用し、ゲーム感覚で体を動かす文化を醸成。社内アプリで歩数ランキングを共有することで、自然と運動が会話のきっかけになり、部署間のコミュニケーションも活性化しました。さらに、経営層自らが参加する姿勢を見せることで、社員のモチベーションも向上。結果として、社内アンケートでは「体調が良くなった」「運動を続けたい」と答える社員が増え、健康づくりが社風として定着しています。
参考:https://www.kentaku.co.jp/corporate/pr/info/2025/information_sportyell2025_20250203.html
トヨタ自動車健康保険組合の取り組み
トヨタ自動車健康保険組合は、健康データを活用した「見える化」によって社員の健康行動を促進しています。独自の健康アプリ「からだのミカタ」を導入し、歩数や食事、睡眠などのデータを自動で記録。参加者には健康ポイントを付与し、社内食堂や商品券と交換できる仕組みを設けています。また、運動イベントや地域マラソンへの参加を推奨し、企業と地域が連携して健康づくりを推進。社員が自発的に健康行動を取れるようサポートする体制が整っています。こうしたデータドリブンな健康経営の取り組みは、他社からも高く評価される成功事例です。
参考:https://www.toyota-finance.co.jp/about/health_and_productivity.html
美津濃(ミズノ)の健康経営施策
ミズノは、スポーツメーカーとしての知見を活かし、従業員の運動を日常に取り入れる仕組みを展開しています。オフィス内にストレッチスペースを設置し、プロトレーナーが監修する「ミズノ体操」を全社で導入。昼休みや会議前の短時間運動で、リフレッシュと集中力向上を両立しています。また、リモート勤務者にもオンライン運動プログラムを配信し、全国どこからでも参加できる体制を整備。さらに、自社製品を用いた「体験型フィットネスイベント」も開催し、社員が商品を通じて運動の楽しさを実感できる工夫をしています。ミズノの事例は、「運動を企業文化として根づかせる」理想的なモデルといえます。
参考:https://corp.mizuno.com/jp/news/20250131

認定を受けるメリットと企業イメージへの効果

社員の健康意識・モチベーション向上
スポーツエールカンパニー認定を受けることで、社員の健康への意識が格段に高まります。社内イベントやキャンペーンを通じて体を動かす楽しさを再認識することで、「自分の健康は自分で守る」という主体性が生まれます。また、運動が習慣化されることで、ストレス軽減や集中力の向上、欠勤率の低下といった効果も期待できます。企業としても、社員が元気で働ける環境を整えることは、生産性や職場の雰囲気を良くする重要な要素です。健康づくりをきっかけに、社内の一体感やモチベーション向上にもつながります。
健康経営優良法人認定など他制度との相乗効果
スポーツエールカンパニー認定は、健康経営優良法人やホワイト企業認定など他の制度と併用することで、相乗効果を発揮します。運動促進を中心とした施策が、生活習慣病対策やメンタルヘルスケアなど幅広い健康経営項目に貢献するためです。たとえば、ウォーキングイベントやストレッチ習慣の導入は「健康維持への取組み」として評価され、他の認定申請でもプラス要素になります。また、複数制度を取得している企業は社会的信頼度が高まり、採用・広報・取引先へのアピールにも有利です。戦略的に認定を活用することが、企業価値の向上につながります。
採用・ブランディング・広報活用のメリット
スポーツエールカンパニー認定は、外部への発信にも大きなメリットがあります。採用活動では「社員の健康を大切にする企業」という印象を与え、応募者の安心感や好感度向上につながります。また、企業ホームページや採用サイト、名刺、展示会などで認定ロゴを活用することで、企業イメージを高めることが可能です。さらに、社内報やSNSで活動内容を発信すれば、社員のモチベーション維持にも効果的です。健康経営を継続的に実践する姿勢を見せることは、企業ブランディングの強化にも直結します。

スポーツエールカンパニー認定のプロセス

申請準備:活動内容の整理と社内体制の確認
申請にあたってまず重要なのは、過去1年間に実施した運動・スポーツ関連の取り組みを整理することです。朝礼でのストレッチ、ウォーキングイベント、健康アプリ活用など、社員の運動促進につながる活動を一覧化し、実施回数や参加人数などの定量データも記録しておきます。加えて、社内で健康づくりを主導する担当部署(人事・総務など)を明確にし、経営層の関与を確認することが求められます。スポーツ庁は「全社的な取組みであるか」を重視しており、部門単位の活動のみでは評価が低くなります。申請前に、社内報告書や写真、アンケート結果を整理し、活動を“見える化”する準備が不可欠です。
申請方法と提出書類
2026年の申請は、スポーツ庁ウェブサイト内の募集ページから行い、電子データでの提出が原則です。提出書類は「申請書(様式1)」「活動概要シート(様式2)」「添付資料(活動写真や広報物など)」の3点が基本構成。記載項目には、実施目的・内容・頻度・参加人数・実施後の効果などを具体的に記入する必要があります。単なる事例紹介ではなく、取り組みの継続性や成果が示されているかが重要です。
審査フローと認定発表までの流れ
提出された申請書は、スポーツ庁および有識者による審査委員会で内容が確認されます。審査は主に「取組の具体性」「継続性」「経営層の関与」「社内外への発信」の4点を中心に実施。企業規模や業種による優劣はなく、どの企業でも公平に評価されます。審査会は12月頃に開催され、翌年1月下旬に認定企業一覧がスポーツ庁ウェブサイトで公表されます。認定企業には「認定証」と「ロゴマーク使用許可書」が交付され、広報活動や採用資料への掲載が可能です。特に先進的な取り組みを行った企業は「スポーツエールカンパニーPLUS」として追加選出されます。
認定後の報告義務とフォローアップ
認定後も活動を継続し、その成果を報告することが求められます。認定企業は翌年に「活動報告書(様式3)」を提出し、取り組みの進捗や社員の反応、今後の改善点などを記載します。この報告は次回申請時の評価材料となるため、日常的にデータを蓄積しておくことが重要です。また、スポーツ庁は継続的な活動を支援するため、オンラインセミナーや好事例共有会を実施しており、認定企業同士のネットワークづくりも促進しています。認定をきっかけに、単発的なイベントから“文化としての運動推進”へ進化させる企業が増えています。
PLUS認定へのステップアップ
「スポーツエールカンパニーPLUS」への選出は、通常認定企業の中でも特に優れた成果を上げた組織に与えられるものです。選考対象は、運動実施率の数値目標を設定し改善を実証している企業や、地域・他団体と連携して活動を広げている企業など。申請時に「PLUS申請希望」と明記し、実績データや社員アンケート結果を添付する必要があります。認定を受けると、スポーツ庁公式サイトで個別に紹介され、PR効果も高まります。2026年は、社員自らが参加を楽しむ仕掛けを設けている企業が多数選ばれており、従来の“運動推進”から“自発的健康文化”への転換が評価の鍵となっています。

スポーツエールカンパニー認定をきっかけに“健康経営”を次のステージへ

心幸グループでは、従業員の健康を「食」と「運動」の両面から支援する健康経営サービス「オフけん」を展開しています。健康管理アプリによるストレスチェック、健康診断結果管理に加え、オンラインセミナーや職場イベントを通して、社員が自発的に健康づくりに参加できる仕組みを整備。また、置き社食サービス「オフめし」との連携により、バランスの取れた食生活支援も実現。スポーツエールカンパニーの理念と親和性が高く、健康経営を実践する企業としてのモデルケースです。

まとめ

スポーツエールカンパニー認定は、社員の健康維持だけでなく、企業の信頼性やブランド価値を高める重要な制度です。2026年版では、より実践的で継続性のある取組が求められており、「運動を文化として根づかせる」企業が増えています。申請準備を通じて、社内の健康施策を見直す良い機会にもなるでしょう。スポーツは、福利厚生・モチベーション・チーム力を高める最良の手段です。これを機に、自社でも“健康経営の次のステージ”を目指してみてはいかがでしょうか。
参考:文部科学省スポーツ庁 「スポーツエールカンパニー2026」の申請受付について
文部科学省スポーツ庁 スポーツエールカンパニー2026募集要項
文部科学省スポーツ庁 スポーツエールカンパニー認定制度実施要項
文部科学省スポーツ庁 スポーツエールカンパニー認定制度実施細則
福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>