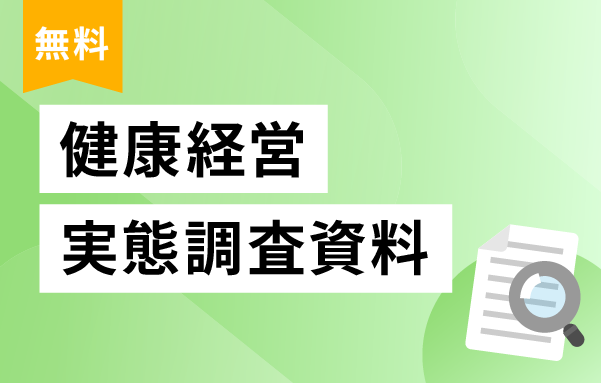秋でも高リスク?真夏以外も要注意の熱中症・脱水症の原因や症状、予防ポイントを解説

こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。
夏の猛暑はここのところ毎年暑さを更新しており、これまでは涼しくなるはずの9月以降も厳しい残暑が続いています。暑い時期は熱中症や脱水症のリスクが高くなるため、熱中症警戒アラートなどをチェックして外出時や日常生活で対策を講じていた方でも、秋に入り気温が低くなると熱中症リスクはないだろうと気がゆるむことが多いのではないでしょうか。しかし、熱中症や脱水症は真夏の暑い時期だけがリスクが高いわけではなく、秋などの季節の変わり目も要注意です。
そこで本記事では、真夏が過ぎた後も気をつけたい熱中症や脱水症を予防するためのポイントを、熱中症・脱水症の原因や症状、対処法などとともに解説します。
福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉
目次
熱中症と脱水症とは?

熱中症とは気温が高い環境で起こる体調不良の総称、脱水症とは体の水分や電解質が汗によって同時に失われた状態を指します。脱水症の症状が進行して体温調節が働かなくなることで、熱中症を引き起こすリスクが高くなります。
熱中症と脱水症は年齢にかかわらずすべての人にかかる可能性がある症状ですが、特に高齢者は加齢に伴う身体機能の低下により体温調節機能が衰えて暑さや喉の乾きを感じにくくなるので、熱中症や脱水症になりやすいといわれます。
なお、暑い時期の体調不良について、一昔前まで「日射病」や「熱射病」という名称がありましたが、2000年にこれらの症状はすべて「熱中症」に統一されています。
熱中症と脱水症の原因
環境省が公表している熱中症予防情報サイトでは、熱中症の要因として「環境」「からだ」「行動」の3つを挙げています。
「環境」とは気温や湿度の高さ、風が弱く日差しが強い場所などに加えて、急激に暑くなった日などが含まれます。「からだ」は、乳幼児や高齢者、肥満の方のほか、糖尿病や低栄養状態、精神疾患などの持病、体調不良時や風邪・インフルエンザなどで脱水症状の状態で汗が出にくく体温が上昇しやすい状態を指します。そして「行動」は、長時間の屋外での作業や激しい運動、水分補給が難しい状況など体温調整がうまくいかなくなる行動が該当し、これら3つの要因で熱中症を引き起こすとされています。
通常、暑いとき熱を逃がすために体温を調整しようと発汗し、皮膚に血液を集めて皮膚温を上昇させます。しかし、脱水状態で血液の流れが悪くなり体内に溜まった熱をうまく逃がすことができなくなると体内に熱が溜まります。これが、熱中症を引き起こすメカニズムです。
脱水症の原因は、体から水分や電解質が失われることです。発汗や感染症などによる下痢や嘔吐、発熱などの原因に加えて、朝食を食べないときや夜ふかしをしたとき、寝すぎたときも水分不足に陥りやすく、脱水症のリスクが高まります。
また、体が緊張状態になると体温や心拍数が上がり水分を失いやすくなるため、強いストレスも脱水症の原因の一つとされています。
熱中症と脱水症の分類と症状
熱中症は、症状の重さによって4種類の分類があります。
・Ⅰ度(軽症):めまい、大量発汗、たちくらみなどの症状。水分と電解質の補給で対応可能。
・II度(中等症):頭痛、嘔吐、倦怠感、集中力・判断力の低下などの症状。水分と電解質の補給に加えて医療機関での診察が必要。
・Ⅲ度(重症):意識障害、けいれん、小脳症状の中枢神経症状、肝・腎機能障害、血液凝固異常のいずれかの症状がある場合。入院治療が必要。
・Ⅳ度(最重症):深部体温40度以上でけいれんや意識障害などの重篤な症状があり、意思疎通不可能。集中治療が必要。
2023年以前までは熱中症の分水はⅠ~Ⅲ度の3種類でしたが、2024年に日本救急医学会が公表した「熱中症診断ガイドライン2024」においてⅢ度が細分化され、Ⅳ度が追加となっています。
脱水症は熱中症の原因となる症状ですが、脱水症には症状の種類によって以下の3種類のタイプに分けられます。
・高張性脱水:汗を大量にかき水分が失われた状態。血中ナトリウム濃度が上がり、喉の乾きやふらつき、けいれんなどの症状が出る。
・低張性脱水:汗をかいたときなどに、電解質が含まれていない水などを大量に飲んだ場合などに電解質が不足して起こる状態。血中ナトリウム濃度が下がり、頭痛や吐き気のほか、血圧低下や意識障害など重篤な症状が起こる場合もある。
・等張性脱水:下痢や嘔吐などにより、体内の水分と電解質がほぼ同じ割合で失われた状態。出血によって起こることもあり、血液量が減少し、めまいや倦怠感、脱力などの症状があり、血圧低下や腎機能低下、ショック状態に陥る可能性もある。
熱中症は、適切に処置をすればⅠ度であれば数時間程度で回復が見込めますが、II度は医療機関での処置で数時間~1日、入院治療が必要となるⅢ度は回復まで数日~数週間かかります。
脱水症も同様に、軽度であれば数時間~1日程度で回復が見込めますが、重度の場合は数日程度かかります。

熱中症や脱水症にかかりやすい時期は?

熱中症や脱水症は、1年で気温が最も高くなる真夏にかかりやすい症状と思っていませんか?実際に気温が高く暑い夏は熱中症にかかる人が多いことは確かですが、熱中症や脱水症に気をつけるべき季節は、真夏に限ったことではありません。
熱中症と脱水症は、湿度が高い時期にかかりやすい症状です。その理由は、湿度が上がって汗が乾きにくくなることで体温が下がりにくくなるからです。また、暑さに体が慣れていない時期も熱中症の発生が増えることから、梅雨の晴れ間や梅雨の終わりかけの湿度が高く気温が上がっている時期は、熱中症や脱水症にかかりやすい状態といえます。
脱水症に関しても、暑い時期に限らず1年を通してかかるリスクがあるため、寒い時期にも要注意です。風邪やノロウイルス感染が増える時期は、下痢や嘔吐の症状で体の水分が減ることで、脱水症になりやすいからです。夏の暑さが一段落した秋も、夏の疲れが残って体力が落ちている状態で秋の気候に慣れない状態が続くこと、水分摂取量が減ることで脱水症に陥る場合があるので注意です。
近年は気候変動などの影響によって9月以降も残暑が厳しく、暑い時期が長くなっています。しかし、気温が極端に高い時期だけ気をつけて、気温が下がった秋以降に油断していると思わぬときに熱中症や脱水症の症状が出ることが考えられるため、気温にかかわらず熱中症や脱水症には注意しましょう。

熱中症や脱水症になったときの基本的な対処法

熱中症や脱水症は、重症度によっては命に関わる重篤な状態になる恐れがあるため、速やかな対処が必要です。もし周囲の人に熱中症や脱水症の症状が出た場合は、まず以下でご紹介する基本的な対処法を実践しましょう。
ただし、基本的な対処法で一時症状が改善したとしても再度症状が現れることがあるので、重い症状でなかったとしても医療機関を受診することをおすすめします。
涼しい場所へ移動
直射日光が当たる気温が高い場所に居続けることは、熱中症や脱水症のリスクを高めます。体調不良が出た際は、まずクーラーが効いた屋内、近くに建物がない場合は風通しの良い日陰に移動させましょう。
体を冷やす
熱中症となった場合は、体を外側と内側から冷やす必要があります。まず、衣服をゆるめる、または脱がせて体の熱を逃がして体の外側を冷やしましょう。その上で、皮膚に水をかけ、うちわや扇風機などで風を当てて体の熱を冷やします。
ワキの下や首筋、太ももの付け根など太い血管が通っている場所に水で濡らしたタオルや氷のうを当てると、効果的に体温を下げられます。
水分と塩分を補給
熱中症や脱水症は、水分だけではなく電解質も失っている状態です。冷たい水とともに、塩分の補給も忘れずに行いましょう。水分と塩分を同時に摂取できる経口補水液やスポーツドリンクを飲ませるのがおすすめです。
経口補水液やスポーツドリンクがない場合は水と塩飴、梅干しなどの塩分が含まれている食品でも対処可能ですが、スポーツドリンクの場合は糖分の摂りすぎ、塩飴などは塩分の摂りすぎにならないよう注意が必要です。
もし嘔吐や吐き気の症状が出ている場合、胃腸の働きが落ちていることが考えられるので、口から水を飲ませることは避けましょう。自力で水を飲めない状態は点滴が必要となるため、医療機関を受診しましょう。
「かくれ脱水」に要注意
熱中症や脱水症とともに注意したいのが、気づかないうちに脱水症の症状一歩手前の状態になっている「かくれ脱水」です。かくれ脱水は、はっきりとした脱水症の症状の自覚がないにもかかわらず、体が水分不足となっている状態です。
かくれ脱水は、汗をかいているが体の不調は感じていないとき、水分摂取を控えているとき、エアコンなどで乾燥した屋内にいるときなどに起きやすいといわれます。寒い冬でも、空気が乾燥しているため皮膚から水分が蒸発しやすい状態となるので、水分を失いやすくなります。水分摂取量の自己管理が難しい高齢者や乳幼児はかくれ脱水のリスクが高くなりますが、その他にも糖尿病や高血圧、精神疾患の方も高リスクだといわれます。
かくれ脱水の症状は、口の乾きや手足の冷え、便秘など日常的にも起こり得る症状なので、自分が脱水状態一歩手前であると自覚することは難しいかもしれません。しかし、体の水分が減少傾向にあるかくれ脱水の状態は、熱中症リスクも高まるため、脱水状態の進行を防ぐには適度な水分補給を心がけることが大事です。

真夏以外にも気をつけたい熱中症や脱水症の予防ポイント

熱中症や脱水症は、気温が高い真夏以外の季節でもかかることがある症状なので、季節を問わず予防を心がけたいところです。具体的に、どのように熱中症や脱水症対策をすればいいのか、予防のポイントをご紹介します。
こまめに水分を取る
熱中症や脱水症の第一の予防ポイントとなるのが、水分の摂取です。いずれも体から水分が失われることによって起こる症状なので、体が水分不足にならないように1年を通してこまめに水分を取ることを意識しましょう。
水分不足を補うには、大量の水を一気するのがいいのでは、と考えてしまう方がいるかもしれませんが、水の飲み過ぎにも注意が必要です。短時間で多量の水を飲むと、低ナトリウム血症を引き起こす「水中毒」のリスクがあります。1日に必要な水分摂取量はおよそ2.5リットルといわれ、この量を超える量の水は摂取しすぎとなります。そのため、喉が乾いてから一度に大量の水を飲むのではなく、喉が乾く前のタイミングで少しの量をこまめに取りましょう。
高齢者の場合は反対に、加齢による体の変化によって喉の乾きを感じにくく水分摂取量が減る傾向があります。そのため、高齢者は熱中症や脱水症のリスクが高くなってしまいます。無理なく水分を摂取するには、毎日水分を摂取する時間を決めて、スケジュール通りに水分を取ってみましょう。常温の飲み物を飲むと、胃腸への負担を軽減できるのでおすすめです。
暑い時期は、水分の補給方法を工夫すると効率的に内側から体を冷やすことができ、熱中症予防効果が期待でき ます。そこで近年注目されているのは、微細なシャーベット状のドリンク「アイススラリー」です。
アイススラリーは氷よりも小さい結晶の粒子が液体に分散された状態なので、流動性が高い特徴があります。凍らせたドリンクなどよりも飲みやすい上、摂取後に体を内部から効率的に冷やして深部体温を下げられる点もメリットです。アイススラリーはドラッグストアやコンビニエンスストアでも販売されているので、熱中症対策として用意しておくのにおすすめです。
塩分も補給する
汗には塩分やミネラルなどの電解質も含まれているため、水分だけを補給しても失われた汗の代わりにはなりません。塩分を取らずに水分だけを大量に補給すると、体内の電解質バランスが崩れてしまい、倦怠感やけいれんなどの症状を引き起こす原因となってしまいます。
熱中症や脱水症の予防には、水分とともに塩分も補給することが重要です。水を飲む際は、すでにご紹介した塩飴や梅干しなどで塩分を適度に摂取しましょう。食品から電解質を摂取するなら、カリウムを多く含むバナナやトマト、マグネシウムを多く含む海藻類や豆類、ナッツなどがおすすめです。
規則正しい生活を送る
熱中症や脱水症の予防として意外と見落とされがちなのが、生活習慣です。生活習慣の乱れは体調を崩しやすく一因となるため、熱中症などのリスクが高まる可能性があります。
朝食を抜いたり不規則な時間に間食を取りすぎたりすることは避け、1日3食栄養バランスの取れた食事を取りましょう。翌日まで残るほどのお酒の飲み過ぎを避けてしっかりと睡眠を取るなど、規則正しい生活を送るように心がけることも熱中症・脱水症予防対策として有効な方法です。

オフけんで熱中症予防につなげる健康管理を

心幸グループでは、企業の健康経営をサポートするサービス「オフけん」を提供しています。オフけんでは、従業員の健康診断結果やストレスチェック、体の状態などを見える化できる体調管理アプリの提供や生活習慣改善セミナー、たばこをやめる卒煙をサポートする「卒煙チェレンジ」など、従業員の健康に関わるさまざまなサービスを利用できます。
さらにオフけんの健康管理アプリでは、多忙な方でもスキマ時間に診療から処方箋発行まで受けられるオンライン診療もスタートしました。全国どこでも場所を問わず受診が可能で、従業員の体調不良に速やかに対応できるサービスとなっています。
熱中症は、体調不良時にかかるリスクが上がる症状です。企業の健康経営の一環としてオフけんを導入することで、従業員一人ひとりの健康管理が容易になり、熱中症を予防して健康的に働ける環境づくりができるでしょう。
関連記事:【2025年6月義務化】職場での熱中症は労災対象?企業が行なうべき熱中症対策とは?

まとめ
熱中症は真夏の暑い時期だけではなく、1年を通してかかるリスクのある症状です。近年は気候変動などの影響によって厳しい残暑が続き、暑い時期も長くなっています。しかし、熱中症や脱水症は真夏だけに起こるものではなく、涼しくなりかけの秋や暑さが厳しくなる前の梅雨などの季節の変わり目も、要注意です。
熱中症や脱水症は、自分で予防ができる症状です。予防のためには、水分摂取だけではなく塩分もきちんと取ること、規則正しい生活を送って体調を整えることが大切です。日常生活の過ごし方でリスクが変わるため、暑さが和らいだ時期や季節の変わり目は特に生活習慣や水分摂取に気をつけて、健康的な毎日を過ごしましょう。
福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>


元気な会社は社員が元気!健康経営サポート

オフけん(運営:心幸ウェルネス)では、「健康経営優良法人」認定取得サポートを中心に、企業の健康経営をバックアップしています。形だけの健康経営ではなく、従業員の健康と幸福に真剣に向き合う取り組みを提案。真の健康経営を実現しています。「からだ測定会」では、体成分測定・体力測定により従業員一人ひとりのからだ年齢が明らかに!他にも、健康セミナー、禁煙サポートなどのサービスを通して、従業員の健康意識を向上させ、元気な会社づくりに貢献します。
オフけんはこちら