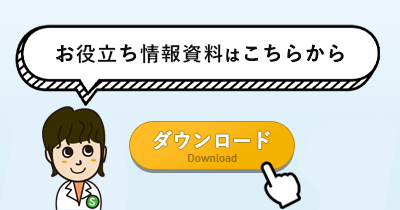再び注目のトランプ関税の日本への影響は? 食品・飲料業界に迫るコスト増リスクと企業の備えと対応

こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。
2025年のトランプ関税によって、食品・飲料業界は輸入原材料の価格上昇や物流コストの増加といった大きな影響を受ける可能性が指摘されています。
これからしばらくのあいだ、日本企業にとっては円安・物価高も重なって調達コストや消費者価格への転嫁をめぐる課題がより一層深刻化するでしょう。
食品・飲料業界に迫るコスト増リスクを整理し、企業が取るべき備えや現実的な対策について考察します。
福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉
目次
【過去から学ぶ】 これまでのトランプ関税措置と食品価格への影響の振り返り

今、再び注目される「トランプ関税」。「トランプ関税」とは、トランプ大統領のもとで実行されているアメリカの関税措置のことです。
今、各国の通商政策が再び大きく揺さぶられるのではないかと、金融市場や産業界では警戒感が高まっています。
特にこれまで食品・飲料業界は、原材料から包装資材に至るまで輸入依存度が高いために、過去の関税政策で大きな影響を受けてきました。
これまでのトランプ関税措置と食品価格への影響を振り返ってみましょう。
【主要な影響を確認】 2018〜2020年頃のトランプ関税の内容概要と対象品目は?
2018年3月からは鉄鋼に25%・アルミに10%の追加輸入関税が課されたために、食品缶や飲料缶の製造コストに直結しました。
また2018年から2019年には中国からの輸入品への大規模な追加関税が実施され、食品原料や調味料、包装材、機械部品などが含まれたことによって食品・飲料業界にも影響が波及しました。
さらにはEUなど他国への報復関税措置も実行されたためにワインやチーズ、オリーブオイルといったヨーロッパ産食品が対象となり、米国内での価格上昇を引き起こしました。
【食品・日用品価格に与えた実例】 当時はどんな影響があったのか?
消費の現場では、当時も関税政策がじわじわと価格高騰につながりました。
たとえば、アルミ関税によって缶飲料への影響が出たビールや炭酸飲料メーカーは、原材料コストを消費者価格に転嫁せざるを得ずに値上げに踏み切りましたし、中国産の冷凍野菜・調味料・乾燥果物などは輸入コストが増加し、仕入れコスト増といった影響が及んでいます。
また、ヨーロッパ食品ではワインやチーズ、オリーブオイルが関税対象となったために、米国内での小売価格が10〜20%程度上昇しています。
一方、関税の影響は食品だけにとどまらず日用品・キッチン用品など広範囲にまで及び、結果として「生活コスト全般の上昇」につながったとも指摘されています。
★軽減税率が企業に及ぼす影響との関連も併せてチェックを!
トランプ関税に関連するテーマについては、過去記事『軽減税率が企業や消費者に及ぼす影響とは?メリット・デメリットやトランプ関税の影響も併せて解説』にて掲載していますので、こちらも併せてご覧ください。

【影響する製品は拡大傾向?】 2025年のアメリカ「トランプ関税」政策内容と食品への影響見通し

2025年に発動された「トランプ関税」は対象国や商品の範囲がかつてなく広がっています。そのため、食品・飲料業界に深刻な波及が予想されています。
現状での影響の見通しを解説します。
現状は? 今回は「15%関税に縮小」で決定? 適用条件は?
2025年8月中旬現在では「15%関税に縮小」という報道も一部で出ていますが、その背景と条件としてはトランプ政権が交渉を行わない国に対し一律で15〜20%の「世界関税」を課す方針を打ち出したことや、EUとは交渉の末にほとんどの欧州産品に対して15%の関税を課すことで合意したことなどが挙げられます。
また、EUや日本など既に協定を結んだ相手には緩やかな関税設定が見られる背景もあります。2025年のトランプ関税は一律で「15%関税に縮小」が決定されたわけではなく、国・地域別の交渉状況に応じた柔軟性がある制度設計になっていると言えるでしょう。
【トレンドチェック】 2025年8月中旬現在でのトランプ関税による影響の見通しは…
2025年8月中旬現在で多くの国への関税率が定まったものの、その関税率は15〜50%の幅で不透明な状態が継続しています。
また中国からの輸入品への高関税については延長措置をとって30%に据え置くなど、一時的な関税猶予や延期措置も行われています。
一方ですでに日本国内の現場では食料品や日用品、素材価格の上昇を見せていて、卸売価格はかなり速いペースで上昇しています。消費者価格にも波及の懸念は大きいと言えるでしょう。

【貿易・輸出だけではない】 企業が考えるべきアメリカ関税への「もしもの備え」
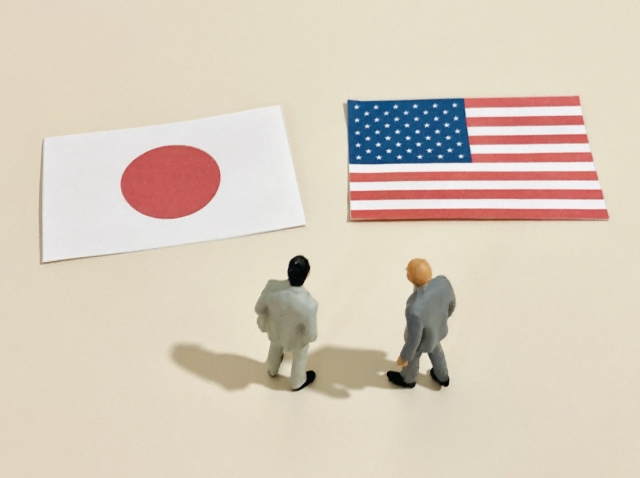
関税政策は政治や外交の動向次第で大きく変化するので、食品・飲料業界をはじめ幅広い産業のコスト構造に直結します。
2025年の「トランプ関税」をめぐる混乱は、まさにその典型例でしょう。
企業にとって重要なのは「予測できない変動」を前提にした備えを整えること。3つの観点から“もしもの備え”を考えます。
多角的な仕入れルート確保の重要性
特定の国や地域に依存した調達構造は、関税リスクが高まったときに即座にコスト増へと跳ね返ります。
そのため同一商品であっても、中国、東南アジア、欧州など複数の国から仕入れルートを確保しておく「調達先の分散化」や可能であれば国内メーカーや地域農産物を一部調達に組み込み「国内調達」や「代替素材の検討」を視野に入れるべきでしょう。
品質やコストは変動しても「最悪のシナリオに備えた選択肢」を持つことは、リスク管理につながります。
値上げへの備えと顧客理解の促し方
関税によるコスト増は、ある程度まで消費者価格に転嫁せざるを得ない場面が出てきても不思議ではありません。
値上げの際に重要なのは「値上げの納得感」です。
「原材料コストの上昇」や「輸入品への新たな関税適用」など値上げの背景を具体的に説明することは、消費者の理解を得る第一歩で、透明性のある情報発信につながります。
また一度に大幅値上げを行うと反発が強まりやすいので、小幅な改定を段階的に進めて消費者に受け入れられる余地を残す工夫も有効でしょう。
単なる値上げではなく「品質向上」や「環境配慮」「地域生産者支援」などの付加価値とセットで伝えられると、より顧客理解が得やすい傾向にもあります。
社員・従業員の生活支援に向けた福利厚生の見直し
関税による価格上昇は消費者だけでなく、社員やその家族の生活コストにも直撃しています。
企業は内部にも目を向けた支援策を講じる必要に迫られています。
具体的には、社員食堂の補助や昼食手当、地域スーパーや提携飲食店の割引などの生活必需品に直結する支援は従業員の安心感を高める施策として注目を集めていますし、物価全体の上昇に備えて住宅手当や交通費支給の拡充を柔軟に検討し従業員の実質的な可処分所得を守る動きも出ています。
これまで以上に、社員や従業員の生活支援に関連する福利厚生の重要性が高まっていると言えるでしょう。

【中小企業も対象】 「食のコスト対策を兼ねた福利厚生サービス」は現実的なソリューション

物価高や関税リスクの影響で、食費の負担は企業で働く社員・従業員の生活に直結する大きな課題になっています。
今の状況に対応するには給与や手当の引き上げだけでなく「食」を切り口にした福利厚生サービスを導入・拡充するのも有効な選択肢です。具体的な選択肢とともに解説します。
社員食堂の補助拡充
社員食堂は、最も直接的に社員の食費負担を軽減できる仕組みです。
従来は一食あたり数百円程度の自己負担で利用できる仕組みが一般的でしたが、昨今の物価高を受けて補助額を増やす企業も増えています。
「より安く・より栄養バランスの取れた食事」を提供するサービスが人気です。
また健康志向メニューへの関心も高まっており、“低カロリー・減塩・高たんぱく”といった料理への補助は、企業側にとって単なるコスト支援に留まらず従業員への「健康投資」としての効果も期待できます。
★『心幸キッチン』なら独自の運営を実現できる!
『心幸キッチン』は、おいしさを追求したメニューのみならず食べる人の健康まで考えたメニューを、管理栄養士資格を保持する開発チームで考案。厚生労働省の基準をクリアした「スマートミール」は、栄養バランスや塩分量・カロリーまで計算したメニューとして好評をいただいています。
全国統一のマニュアル的な調理ではなく、できる限り地元の食材も使用!地産地消で地域に貢献する社員食堂の運営が叶います。
従業員への健康投資として、ぜひ『心幸キッチン』をご検討ください。
提携デリバリーサービスの割引制度
働き方の多様化に合わせ、外部サービスと連携した「食の支援」も広がっています。
デリバリーサービスと提携し社員に一定額の割引クーポンを配布する仕組みは、オフィス勤務だけでなくリモート勤務の社員にも適用しやすく、このような生活スタイルに合った柔軟なサポートは福利厚生の満足度を高め、採用や定着にもプラスの効果をもたらす施策です。
★デリバリーサービスの代わりにキッチンカーの選択肢も!
心幸の『ごちショウ』は、キッチンカーや屋台を企業に派遣するサービスです。近隣にレストランが少なくデリバリーサービスを活用しにくいエリアでも、職場にいながら手軽に出来立ての食事がとれます。
さまざまなジャンルの料理をラインナップ。従業員の満足度アップやモチベーションアップに貢献します!
健康食材の宅配支援
食費対策と健康増進を両立させる手段のひとつとして「食材宅配サービスの福利厚生化」も注目されています。
野菜のセットや食材などの定期宅配に企業が補助を行ったり、従業員が調理済みのミールキットや下ごしらえ済み食材を利用しやすくしたりといったきめ細かな「食」の補助は、買い物や料理が苦手な従業員にも健康的な食生活を提案しやすいだけでなく、社員食堂を設置していない企業にとっては福利厚生による社会的評価を高める効果も期待できます。
★『心幸ネットストア』で質の良い訳あり特価商品をゲット
『心幸ネットストア』はお菓子や食品の卸売、社食・社内コンビニ運営などを行う心幸が、独自の流通網を活かしてお得な商品をネット販売しているサービスです。
無料のメール会員登録でお得なセール情報をゲット!▶︎ぜひこの機会にこちらからご登録を!

【まとめ】不安定なコスト増リスクへは「食」への福利厚生が有益な選択肢

関税や物価高騰といった外部要因によるコスト増リスクは、今の企業にとって避けることのできない経営課題です。
食品・飲料業界では原材料価格が直撃している一方で、消費者や従業員の生活にも負担が重くのしかかっています。
こうした状況で有効な施策のひとつが「食」を切り口にした福利厚生の充実でしょう。
単なる食費対策にとどまらず、社員の健康促進や満足度向上につながる施策を打てれば、従業員のエンゲージメントや採用競争力を高める投資にもつながり、長期的には人材定着や生産性向上という形で還元される効果も期待できます。
今や、従業員の生活を支える福利厚生が企業の安定経営を支える戦略としても有益な時代になっているのです。
福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>


はたらく人を元気にする会社

グループ間協力で、売店・食堂・企業内福利厚生をワンストップでサポートいたします。売店とカフェの併設や24時間無人店舗など、個々の会社では難しい案件も、グループ間協力ができる弊社ならではのスピード感で迅速にご提案します。
心幸グループ WEBSITE